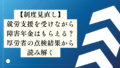近年、日本では外国からの観光客が増え、観光地や電車が混み合うことが多くなってきました。こうした「オーバーツーリズム」は、地域の暮らしや、障がいのある方・高齢の方にとっても負担になることがあります。
たとえば、新幹線で予約した席に他の人が座っていたり、大きな荷物で通路が通りにくくなったり。SNSで話題になった場所に観光客が集まり、マナーの問題が出ることもあります。
この記事では、みんなが安心して旅を楽しめるよう、混雑を避けるコツや、旅のうえでの工夫などをご紹介します。

【あわせて読みたい!】メジャーサポートサービスブログ
🔗障がいのある人も、ない人もいっしょに。暮らしやすい社会をつくろう~バリアフリーとユニバーサルデザインのちがい
🔗【ライブ】これはお得!JR乗車券障がい者割引とは?ライブ遠征がもっと自由に!
😥人気観光地の“オーバーツーリズム”にどう向き合う?
観光地が困ってる?「オーバーツーリズム」ってなに?
「オーバーツーリズム」とは、観光地に人が集まりすぎて、地元の暮らしや観光の楽しさに影響が出てしまうことをいいます。
人気の観光地ではゴミや騒音、交通の混雑が問題になったり、観光客同士のトラブルが起きるケースも。実際に、京都・祇園では舞妓さんへの過度な写真撮影が問題になり、2023年から一部エリアで撮影が禁止されました。
こうした問題を減らすには、観光マナーを守ることや、訪れる場所や時期を分散させる工夫が大切です。地元の人と観光客、どちらにとっても気持ちのよい環境をつくっていきたいですね。

ゆったり旅のすすめ 〜混雑を避ける「分散型観光」〜
有名な観光地は魅力的ですが、どうしても混雑しがちです。特に、体に不自由がある場合、大量の人が押し寄せている観光地に出向くのは、とても体力のいることです。そんなときは、少し視点を変えて、その周辺エリアに足を伸ばしてみるのもおすすめです。
たとえば京都では、清水寺のような人気スポットは人が多くなりがちですが、少し離れた山科、宇治、伏見などを訪れると、落ち着いた雰囲気の中で歴史ある街並みや地元グルメを楽しむことができます。
このように、少しルートをずらして巡る「分散型観光」は、混雑を避けつつ、その土地の魅力をより深く味わえる旅のスタイルです。

安心して旅を楽しむためのちょっとした工夫~障がいのある方~
体に不自由があると、観光地では移動や人混みが大きな負担になることがあります。電車やバスで座れなかったり、エレベーターの混雑や、人混みで車いす・杖の使用が難しい場面も少なくありません。そうした不安を減らすためには、あらかじめ少し工夫をして旅の計画をしておくことが大切です。
<あらかじめの工夫の例>
・行き先のバリアフリー情報&タクシー乗り場を事前に詳細に調べておく
・休憩場所も設定して、無理のないスケジュールにする
・バリアフリーを意識するなら、地下鉄より地上の電車、電車よりバス、バスよりタクシー
・電車を利用する時は、なるべく新しい駅や路線を選択(バリアフリーの整備が進んでいます)
・観光タクシーがある場所では観光タクシーも◎(運転手さんが見どころへ連れて行ってくれます。)🔗Tower Network 全国観光タクシー一覧
・荷物をなるべくコンパクトに(ヤマト運輸の🔗「宿泊施設往復宅急便」が便利!)
※利用する場合は、先に荷物の受け取りについて宿泊施設へ確認を取っておきましょう。
※京都では、駅から宿泊施設への荷物配送サービスや、手荷物預かりサービスがあります!詳しくはこちら👉🔗京都市公式:HANDS FREE KYOTO
安心して旅を楽しむために、事前の準備を忘れずにしておきたいですね。

😣マナーが壊れつつある今、できることとは?
SNS時代、「マナー、ちょっと気にしてみませんか?」
スマートフォンで写真を撮ってSNSに投稿するのは、今では当たり前のこと。でも、その“当たり前”が、誰かにとって迷惑になっているかもしれません。
たとえば、撮影が禁止されている場所での写真や、知らない人の顔が写った写真を許可なくアップすることは、プライバシーの問題につながります。
京都市では、海外からの観光客にもマナーを伝えるため、多言語のマナーポスターを設置するなど、対策を進めています。
自分が「これ嫌だな」と思うことは、他の人も同じように感じているかもしれません。
だからこそ、マナーは“おたがいさま”の気持ちで意識していきたいですね。

誰もが気持ちよく過ごせるために 〜心のバリアフリーって?〜
バリアフリーというと、段差をなくしたり、エレベーターを設置したりといった「設備面」が思い浮かびますが、一番大切なのは、相手を思いやる気持ち——いわゆる「心のバリアフリー」です。
たとえば、車いすの方が困っていたら声をかけてみる、ベビーカーを持ち上げるのを手伝う、外国の方に道を教えてあげるなど、ちょっとした配慮や行動が大きな安心につながります。
言葉が通じなくても、表情やジェスチャーで思いやりは伝わります。
誰もが心地よく過ごせる社会は、小さな優しさの積み重ねから。気づいたときに、できることから始めてみませんか?
そんな心のバリアフリーについて、私の実体験を次の項目でご紹介します。
🙋♀️「困ったときは声を出してもいい」 〜思いやりが繋ぐ助け合いの輪〜
私は足に不自由があります。
今回は、先日外出先で感じた「思いやり」について、少しお話ししたいと思います。
先日、大都市で荷物を持っていたとき、事前に調べきれていなかった段差に出くわし、足元の段差に苦労して立ち止まっていたところ、外国人の男性がすぐに助けてくれ、荷物を階段の上まで上げてくれました。その時ひとりだった私は、本当に助かりました。
その時ふと、外国の方は日本人に対して、あまり警戒心を持たないのかもしれないと感じました。もちろん全ての人に当てはまるわけではありませんが、地方では似たような価値観の中で育った人が多く、困っている人に自然と手を差し伸べる雰囲気があります。
一方、大都市ではさまざまな背景を持つ人が集まっているため、「声をかけても大丈夫かな?」と迷ってしまう人も多い印象です。
そんな、困ったときは、「助けてください」と声をあげてもいいんですよね、きっと。でも、やっぱり恥ずかしかったり、「迷惑をかけちゃいけない」と思ってしまったりもして。
それでも、ふと考えるのです。もし自分が誰かに「助けて」と言われたら、きっとできる限り手を差し伸べると。
小さな思いやりが、大きな安心につながるのだと、改めて感じた出来事でした。
<参考>視覚に不安がある方が、白杖(はくじょう)を高く掲げるしぐさをすることがあります。これは「白杖SOSシグナル」と呼ばれ、助けが必要なときのサインです。見かけたら、正面から優しく「どうされましたか?」と声をかけ、必要なサポートを聞いてみてください。

🚅新幹線の混雑をどう避ける?快適な移動の工夫
新幹線の混雑を避けるコツは“時間と路線、新幹線の種類選び”
新幹線で快適に移動するには、利用する列車の種類はなるべく、停車駅が多い新幹線を選ぶことがポイントです。また、「時間帯」や「路線」も工夫する必要があります。
<停車駅が多い新幹線の種類>
東海道・山陽新幹線:「こだま」。次に「ひかり」、「のぞみ」の順。
東北新幹線:「やまびこ」。「なすの」も原則各駅停車。次に「はやぶさ」の順。
九州新幹線:「つばめ」。次に「さくら」、「みずほ」の順。
北陸新幹線:「あさま」・「はくたか」。次に「かがやき」の順。
※上越・山形・秋田新幹線は、同じ種類でも停車駅が異なるので、事前によく確認しましょう。
特に観光シーズンや週末は、東京〜京都〜大阪を走る東海道新幹線がとても混み合います。平日で午前中の早い時間帯や、夜遅めの時間帯を選べば、若干混雑が緩和し、移動がスムーズです。
また、東海道・山陽新幹線であれば、JR東海の「スマートEX」がおすすめ。混雑状況を事前にチェックしながら予約ができて便利です。障がい者手帳をお持ちの方も、障がい者割引の乗車券は窓口での購入が必要ですが、特急券(e特急券)はスマートEXで予約が可能です。以下の参考のリンクに詳細があるので、併せてご参照ください。
混雑を避ける工夫をするだけで、移動がぐっと快適になりますよ。
参考:🔗新幹線の利用に朗報!障がい者手帳を所持していても先に予約できる「EX予約」
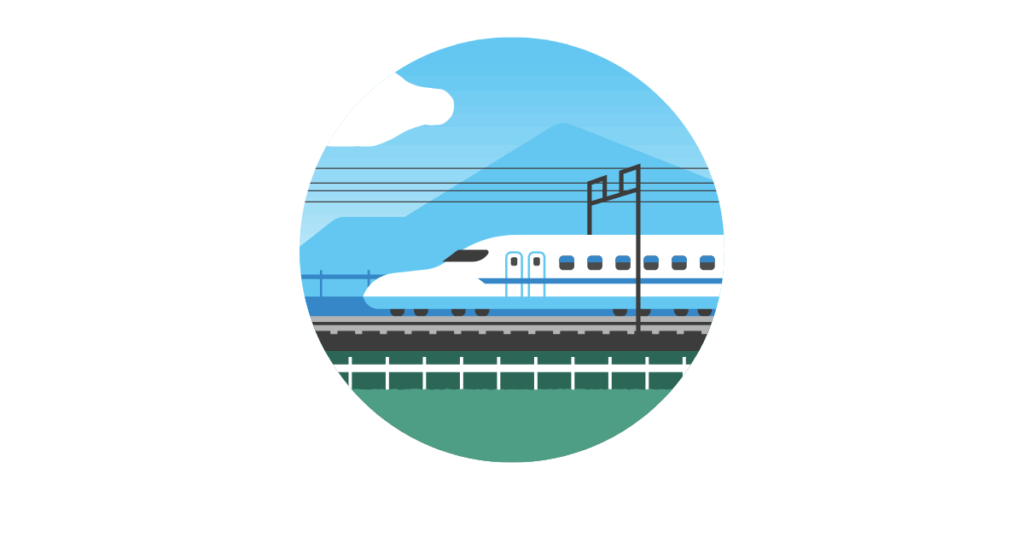
安心して新幹線に乗るために 〜バリアフリー席の上手な使い方〜
新幹線には、車いすの方や高齢の方も安心して利用できる「バリアフリー席」が用意されています。代表的なものには、車いすのまま乗れる「車いすスペース」と、座席に移って利用できる「車いす対応座席」があります。
これらの座席はすべての列車にあるわけではなく、車両によって設備が異なるため、事前の確認と予約が必要です。
バリアフリー席の種類
- 車いすスペース(移乗なし):
車いすのまま乗車できるスペースです。JIS規格の車いすが基本対応ですが、利用可能なサイズや場所は列車によって異なります。 - 車いす対応座席(移乗あり):
車いすから座席へ移りやすいように、ひじ掛けが跳ね上がる席や回転シートが設置されています。長時間の移動も快適に過ごせます。
予約窓口について
予約は先ほどのスマートEXや、「みどりの窓口」、専用予約フォームで可能です。各JRのウェブサイトで、乗りたい新幹線車両にバリアフリー設備があるか事前にチェックしてから予約しましょう。
【車両の設備確認ページ】
・JR東海:🔗車両のご案内(N700系・N700A、N700Sの中から対象の車両を選択して下さい。)
・JR東日本:🔗JR東日本の列車たち(新幹線の欄から対象の車両を選択してください。)
・🔗JRおでかけねっと:東海道・山陽・九州・北陸新幹線の各車両の設備が確認できます。
【バリアフリー席予約窓口】
・🔗JR東海スマートEX(車いす対応座席の予約)
・JR東海:🔗東海道・山陽・九州新幹線「車いす対応座席受付フォーム」
・JR東日本:🔗東北・北陸・上越新幹線「車いす対応座席 WEB申込みのご利用案内」
歩くのが少し不安なときの新幹線の座席選び
歩行に少し不安がある方の、新幹線の座席選びについて、筆者の体験をもとにポイントをまとめました。
座席選びは「歩く距離の少なさ」「混雑のしにくさ」「安心して座れるスペース」がポイントです。事前にしっかり準備して、快適な移動時間を過ごしましょう。
座席の種類は?
ゆったりしたいなら「グリーン車」がおすすめ。
座席が広く、たいていホームのエレベーター近くに停車するので、乗り降りが楽です。体に負担をかけたくない方には特に向いています。
自由席より指定席を。
「グリーン車」が難しい場合は、自由席もしくは指定席となりますが、自由席は混みやすく、座れない可能性も。事前に指定席を予約することをお勧めします。
どの車両を予約しよう?
新幹線は真ん中あたりの車両が、駅のホーム出口に近く便利ですが、予約が集中します。混雑を避けたい場合は、端の方の車両を予約しましょう。
しかし、端の車両はホームを長く歩く必要があるので、歩く距離を減らしたい方は、中間車両の早め予約が安心です。体の状態に応じて選びましょう。
座席の位置はどこがいい?
新幹線(グリーン車や九州新幹線指定席などを除く)の座席は、1列に「3席」と「2席」が並んでいます。
比較的、隣の席が空きやすいのは3席側の窓側か通路側で、曜日や時間帯によっては、ゆったり座れることがあります。
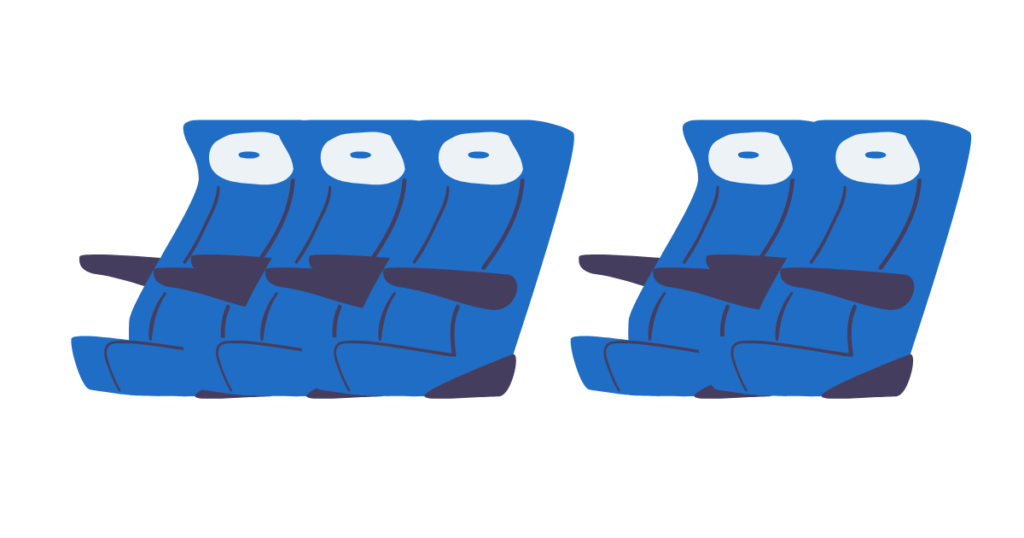
体に不自由がある方や、静かに過ごしたい方には、隣に人が来にくい席を選ぶと乗り降りもしやすく安心です。
さらに、車両の一番前の席は前に座席がないため足元が広く、コンセントも必ず付いていて便利。乗り降りもしやすい位置にあります。
一方、一番後ろの席は背中側が大型荷物スペースになることがあり、荷物の影響でリクライニングが倒せない場合もあるので注意が必要です。
快適に過ごしたい方は、3席側の窓側か通路側、さらに一番前の席を選ぶのがポイントです。
📱外国人観光客との共存を考えるツールとアイデア
「翻訳アプリ」で言葉の壁をやさしく乗り越えよう
言葉の違いがあっても、翻訳アプリがあれば安心です。
技術を上手に使うことで、文化や言語の違いを気にせず、コミュニケーションがとれます。お互いに助け合うための準備として、ぜひ活用してみてください。
<おすすめツール>
・🔗VoiceTra(ボイストラ):国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が提供する多言語翻訳アプリで、公共機関でも推奨されています。アプリでインストールし、スマホで使用可能です。
・🔗Google翻訳:音声認識だけでなく、カメラ翻訳も可能で、街中でも役立ちます。

みんなが使いやすい観光デジタルマップのすすめ
インバウンド対応が進む観光地では、デジタルマップや音声ガイドの導入が増えています。
観光デジタルマップとは、自治体・施設・店舗などが、マップの作成・構築、情報の入力や管理を行い、観光する側がそこにアクセスして、地図を観たり、音声ガイドで確認したり、混雑状況を把握したり、お店を予約したりと、パンフレットやお店ごとの検索などの必要がなく、効率よく観光地の情報を把握できるシステムです。

<おすすめツール>
・🔗プラチナマップ:日本語・英語・中国語・韓国語などに対応しており、電車・バスの乗換えや観光スポット情報も掲載。音声ガイドで確認したり、経路案内もスムーズです。
・🔗UDトーク:聴覚障がい者にも対応したリアルタイム文字起こしアプリです。
🌇【まとめ】思いやりでつくる、心地よい旅時間
現在、観光が地域の活性化につながる中、訪れる人と住んでいる人、どちらにとっても気持ちよく過ごせる環境づくりが大切になっています。
最近では、外国人観光客の増加により、文化や価値観の違いからマナーが守られず、地域の暮らしに影響が出ることも。また、混雑やマナーの問題は、体に障がいのある方にとっても負担になることがあります。
SNSなどでは意見の対立も見られますが、思いやりを持って寄り添うことで、お互いが快適な旅の時間を過ごすことができたらとても素敵ですね。
「自分だけが快適であればいい」という考えを少し手放して、少し周りへの気配りを意識してみませんか?次の旅が、ちいさな気づかいや優しさで、もっと素敵な思い出になりますように。