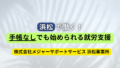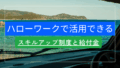「車いすを使っている」「精神障がいがある」──そんな状況で一人暮らしだと、部屋探しも簡単ではありません。不動産屋さんで断られたり、大家さんの了解が得られなかったり、審査に通らないことばかり。
この記事では、障がいのある方が住まいを探すときに直面しやすい課題や、利用できる支援制度・住まいの選び方について紹介します。公営住宅の申し込み方法や、民間賃貸での注意点、生活保護を利用している場合のポイント、そして2025年10月に改正・施行された「住宅セーフティネット制度」についても紹介します。
障がいのある方の一人暮らしや部屋探しは、決して簡単なことではありません。だからこそ、少しでもお力になれたらうれしいです。
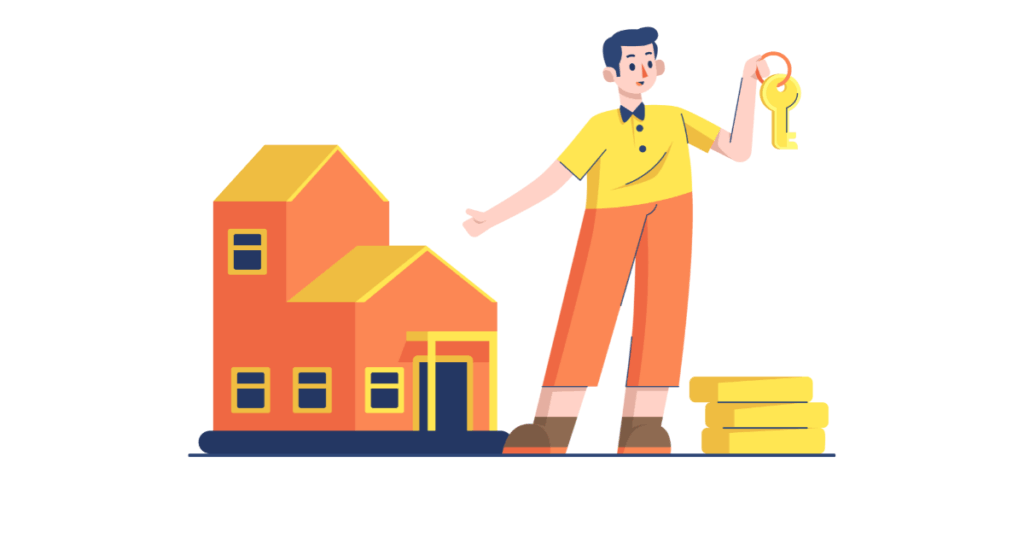
👩🦽障害のある方が「公営住宅(市営・都道府県営住宅)」を借りる時
公営住宅は家賃が安く、生活保護受給者も入居可能
公営住宅は、所得の少ない人向けに家賃が安く設定され、生活保護受給者も入居できる場合があります。
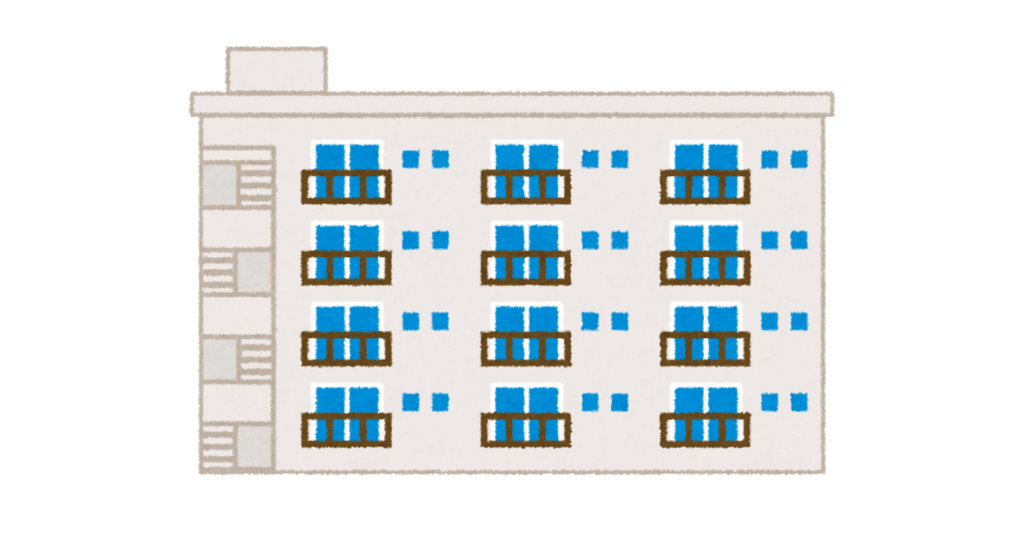
また、公営住宅は、家計の負担を軽くしながら安心して暮らせる住まいを提供しています。経済的に困っている方にとって大きな助けとなります。
市営住宅:静岡県浜松市の場合 🔗浜松市 市営住宅
県営住宅:静岡県の場合 🔗静岡県住宅供給公社「県営住宅物件」
公営住宅の申し込み方法
公営住宅に住みたい!という場合、おおまかには以下のような方法になります。(各自治体によって詳細が異なるため、お住まいの自治体のHPで必ずご確認ください。)
1.募集時期を確認する
年に数回(例:春・秋など)決まった時期に募集されるので、各自治体の住宅課や市役所のHPで確認する。
2.募集要項・申込書を入手する
市役所や出張所、またはWebサイトからダウンロードできる場合もあります。募集要項で、入居資格があるかを確認する。
3.必要書類をそろえて申し込む
住民票、所得証明、課税証明などをそろえ、窓口または郵送で提出。
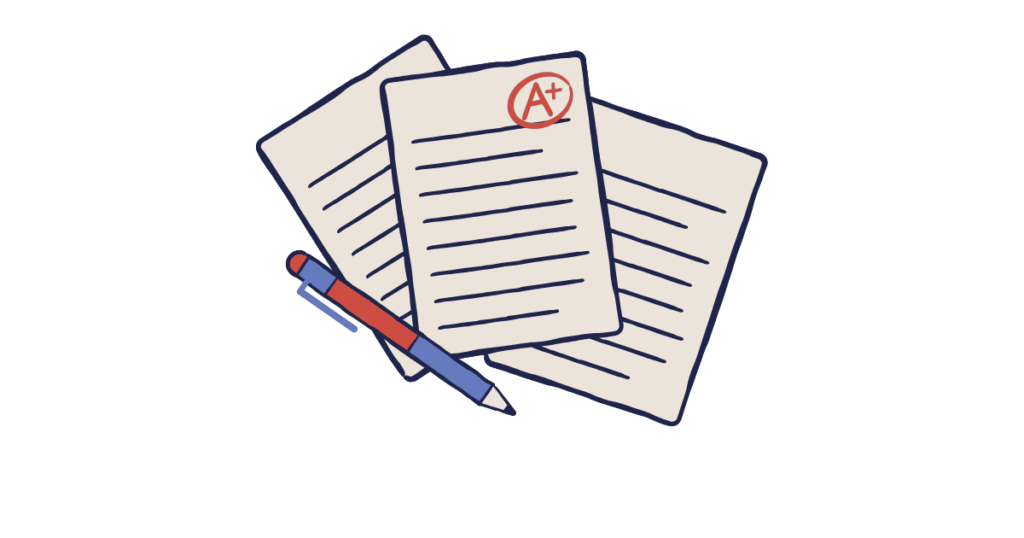
4.抽選(または選考)
応募多数の場合は抽選となります。(世帯構成や緊急性によっては優先されることも)
5.当選したら、契約・入居
公営住宅は情報収集と根気が「カギ」
公営住宅には、障がい者や高齢者、生活保護受給者、ひとり親家庭などを対象とした「優先入居制度」もありますが、築年数が浅く、交通の便の良い所などはすでに空きがないことも。
バリアフリー対応住宅になるとさらに数が少なく、倍率が高いため抽選や空室待ちになることも。応募にはタイミングや細かな書類準備なども必要なため、「待つ力」と「調べる力」が求められます。
また、治安への不安の声もありますが、地域によって状況は異なるため、実際の雰囲気を事前に調べることが大切です。自治体の福祉窓口や公式サイト、近隣の口コミ情報を活用して、こまめに情報をチェックしましょう。
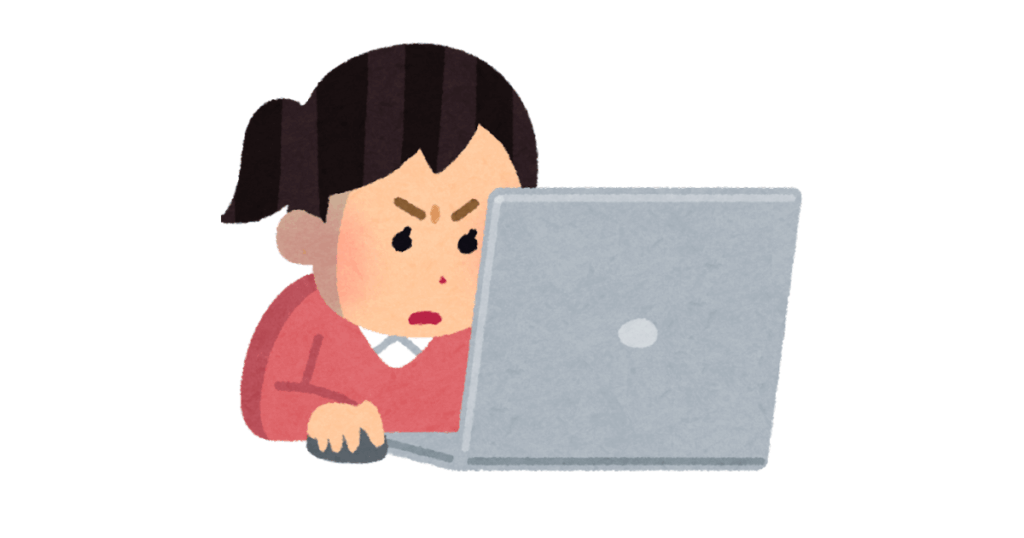
生活保護を受給している人の場合
生活保護を受けていても、税金の滞納などがなければ、公営住宅に入居することができます。
ただし、生活保護受給者に支給される、住居費をまかなう「住宅扶助」には上限額があります。(地域や家族の人数で異なります)
公営住宅の多くはこの上限内に収まりますが、住宅扶助以上の賃料の物件だと引っ越せなかったり、自己負担となる場合や、引越しにあたって「正当な理由」がないと、住宅扶助や引越し費用(敷金や引越し代など)自体が支給されないこともあるため、注意が必要です。
公営住宅への引越しを考えている場合は、まず、担当のケースワーカーさんや相談員さんに相談しましょう。
【ちなみに】「UR賃貸住宅」とは?
かつては「住宅公団」という国の機関が建設・管理していた賃貸住宅で、現在は、UR都市再生機構(UR:Urban Renaissance Agency)という独立行政法人によって運営されています。
残念ながら、静岡県には物件はありませんが、関東だけでなく、中京圏や関西圏、福岡や札幌などの地方都市に物件があります。家賃は、市場相場よりやや安く、礼金・仲介手数料・更新料不要で入居でき、入居時の費用を抑えることができます。
しかし、入居時、おおむね家賃の約4倍以上の月収があることが目安になります(例:家賃6万円なら月収24万円程度)。最低収入基準などもあるため、民間の賃貸より入居時の費用を抑えられますが、少し入居の壁が高くなります。
公営住宅に空きがなく、住む予定の地域にUR賃貸住宅がある場合は、検討してみてもよいかもしれません。
UR都市再生機構:🔗UR賃貸住宅
🏢障がいのある方が、「民間の賃貸物件」を借りる時
障がいがあると賃貸住宅を借りにくい?
障がいがある方の中には、民間の賃貸住宅を借りるとき、審査(※)で断られてしまうことがあります。
生活保護を受けている場合や、保証人がいない場合は、特にハードルが高くなることがあります。
また、審査では現在の収入や勤務先について聞かれることも多く、とてもつらい所ではありますが、就労支援事業所などに勤めている場合は、不利に見られてしまうケースもあるようです。
<賃貸物件での「審査」とは?>家賃をきちんと払えるかどうかなどを、大家さんや家賃保証会社が確認するものです。収入や勤務先、人柄などがチェックされます。
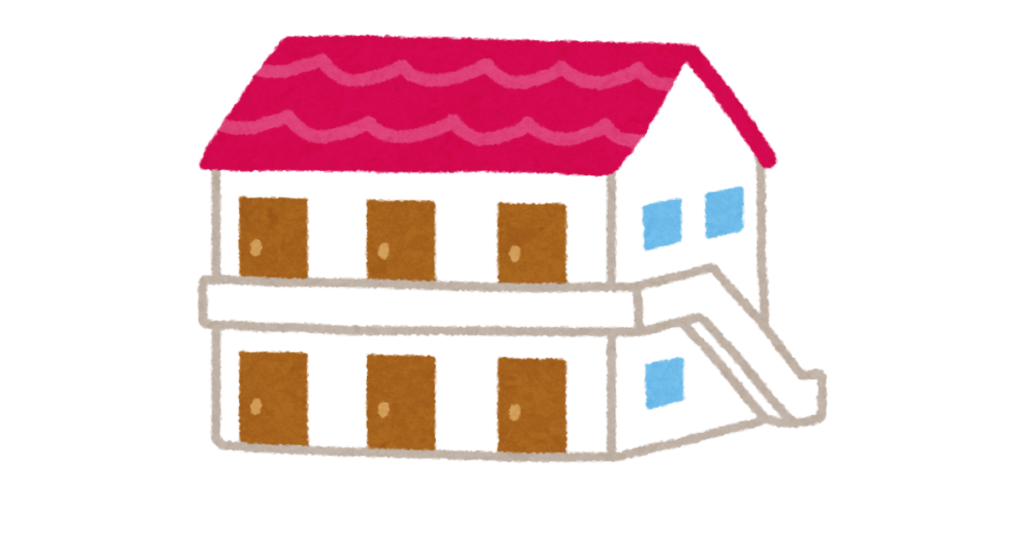
障害がある方の賃貸の審査、なぜ通りにくいのか?
障がいのある方が賃貸住宅を借りる際、審査で不利となる主な理由として、以下のようなことがあります。
・収入が安定していないと思われる(特に生活保護受給者の場合、家賃の滞納リスクと見られがち)
・保証人などの支援体制がはっきりしない
・トラブルが起きやすいのでは?と思われたり、トラブル時の対応が難しいと判断される など
こうした不安や誤解が、大家さんや不動産会社に「リスクが高い」と思わせてしまう要因になっているようです。
借りるための工夫とは?
障がい者向けの家賃保証会社を活用
以前は賃貸契約に「連帯保証人」が必要でしたが、最近は、不動産会社や大家さんが指定する家賃保証会社に加入するケースが一般的になっています。家賃保証会社は、借主が家賃を払えない場合、保証会社が立て替え、後で借主に請求する仕組みです。(入居時は保証会社の審査があり、別途保証料や更新料、手数料が発生する場合があります。)
なお、保証会社による審査では、収入などの条件によっては契約できないこともあります。
契約できない場合などは、障がいのある方向けに配慮された専門の家賃保証会社もあり、一般的な保証会社よりも柔軟な対応が期待できます。ただし、物件によっては利用できないことがあるため、不動産会社に「障がい者向けの保証会社が使えるか」を事前に相談するのがおすすめです。
珍しい制度として、東京都板橋区は、自治体が家賃保証の支援を行っています。この制度を利用したい場合にも、制度に対応している不動産会社かどうかを確認してみましょう。
障がい者向け家賃保証会社:新日本信用保証🔗「AIR<エール>保証」
板橋区の家賃保証支援事業:🔗家賃等債務保証支援事業
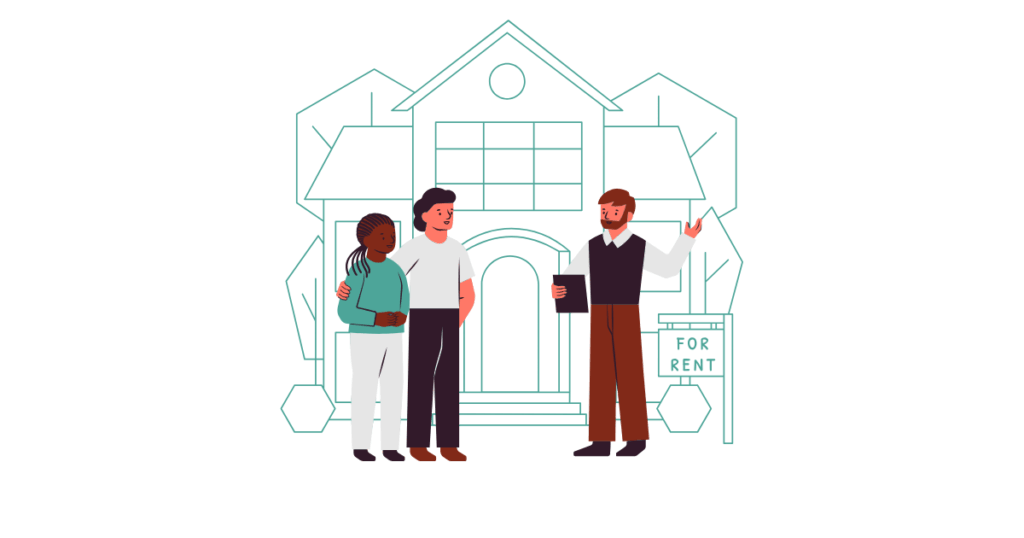
福祉専門の不動産サービスを探す
障がいのある方や生活保護を受給されている方を対象に、物件の紹介や住まい探しのアドバイスを行っている不動産会社もあります。以下のようなサービスの利用も、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
- 🔗アイフルホームズ「FRENDRY DOOR」:障がい者や生活保護受給者など、様々なバックグラウンドを持つ人が安心して住まいを見つけるためのサービス
- 🔗ドコモ・プラスハーティ障害者福祉制度「居住サポート」:不動産会社への物件紹介の依頼や、家主との契約手続きのサポート、保証人が必要な場合の調整、家主への相談・助言、入居後の緊急対応などを行います。(利用は、先に市町村の福祉の窓口や、相談支援事業所への相談が必要。)
自治体の福祉窓口へ相談する
障がいのある方や生活保護を受給されている方で、住まい探しなどにお困りの際は、お住まいの市区町村の福祉窓口や担当の相談員さんへ相談してみましょう。自分が知らない支援制度を教えてもらえたり、良いアドバイスをもらうことができます。
また、公営住宅や令和7年10月に始まった「住宅セーフティネット制度」についても、あわせて相談することをおすすめします。これらの制度については、後ほど詳しくご紹介します。
【番外編】民間の賃貸に引っ越す場合の注意!
地域で大きな差が!こんなに違うぞ!「更新料」
賃貸物件にある「2年に1回の更新」。この更新料、実は地域で大きく違います。
例として、物件の家賃にもよりますが、関東の場合は、更新時に10万円以上かかる場合も。
全国的に2年に1回の更新+火災保険の更新があるという点は変わりないですが、東京など関東圏では、更新時に大家さんへ更新料として家賃1か月分、不動産会社に手数料を数千円~1万円程度を徴収する場合が多く、さらに火災保険料の更新(おおむね1~2万円程度)と合わせると2年に1回、10万円以上かかることも。
一方、関西(大阪・兵庫)を含む、おおむね静岡以西では、更新料・手数料なしの物件も多く、更新時の費用負担は、火災保険の更新のみとなり、かなり軽め。
福岡・北海道などでは、更新料がないか、あっても数千円〜数万円程度+火災保険料というケースが一般的です。
つまり、引っ越す地域によって、賃貸にかかる維持費は大きく変わります。
これから引っ越しを考える際は、「家賃」や「共益費」だけでなく「更新費用」にも注目してみてください。
※家賃保証会社に入っている場合は、その年会費がかかります(年1万〜2万円が主流)。中には月額家賃の1〜2%を支払う「月額制」のタイプもあります。
東日本でよく見る「礼金」、マジか!
礼金とは、大家さんに対する「お礼」として支払うお金で、退去しても戻ってきません。
この礼金制度には、東日本と西日本で違いがあります。
東日本では、入居時に家賃1〜2ヶ月分の礼金が必要な物件が多く見られます。西日本では礼金が不要、あるいは制度自体がない場合もあり、その代わりに敷金(退去時の修繕費などに使われ、一部返金されることもあります)が重視されます。
引っ越しの際は、地域によって初期費用が変わるため、礼金の有無も確認ポイントです。
たとえば、「礼金2ヶ月・敷金1ヶ月」の物件より、「礼金1ヶ月・敷金2ヶ月」の物件のほうが、大家さんの対応が柔軟な可能性があります。
なお、「セーフティネット住宅」や「居住サポート住宅」の礼金は、その意味が大きく違ってきます。詳細は、このあとご紹介します。

【朗報!】「住宅セーフティネット制度」が改正されました
「住まいに困らない社会へ」 〜住宅セーフティネット制度とは〜
高齢の方や障がいのある方、ひとり親家庭などが、住まい探しがむずかしいという声と、高齢化や独り暮らしの増加で、大家さんの懸念が増えているという両方の声を支えるしくみが、国土交通省が進める「住宅セーフティネット制度」です。
受け入れ可能な賃貸住宅を増やし、家賃補助や入居サポートも行います。自治体やNPO団体、不動産会社と連携し、安心して暮らせる住まいを見つけやすくすることを目指しています。
国土交通省:🔗住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~
「住宅セーフティネット制度」には、従来からある「セーフティネット住宅」と、この2025年10月から始まった「居住サポート住宅」の2つがあり、ざっくりとは以下のようになります。
▶ セーフティネット住宅=「入居しやすさ」に重点
▶ 居住サポート住宅=「入居後の暮らしの安心」に重点
詳しくは以下にご紹介します。
「セーフティネット住宅」と「居住サポート住宅」の違いって?
「セーフティネット住宅」とは
「セーフティネット住宅」は、従来からある制度で、住宅の確保が難しい人(高齢者・障がい者・低所得者など)が入居しやすいよう、大家さんが「入居を断らない」と約束して国や自治体に登録された賃貸住宅です。
大家さんへ回収補助が支給される場合もあり、大家さんを助け、安心して物件を貸出して(登録して)もらい、その物件と入居したい人をつなぐための制度でもあります。
なお、セーフティネット住宅は、家賃が相場よりやや安い一方で、礼金が高めに設定されている物件が多く見られます。
これは、「原則断らない」という入居方針のもと、大家さんがリスクに備えるためや、敷金ゼロで入居しやすくする代わりに、退去時に礼金を修繕費に充てる目的があるためです。地域差よりも、セーフティネット住宅ならではの事情が大きく影響しています。
浜松市の場合:🔗住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)
静岡県の場合:🔗静岡県の住宅セーフティネット制度
<セーフティネット住宅として登録された物件を検索する場合はこちら>
🔗セーフティネット住宅 情報供給システム
「居住サポート住宅」とは
「居住サポート住宅」は、2025年10月に始まった新しい制度で、セーフティネット住宅をさらに進化させた支援強化型の住宅制度です。入居後の見守りや福祉サービスとの連携が制度上の要件となっており、支援があることが前提です。
<「居住サポート住宅」の主なポイント>
・見守り・支援つきの住宅
入居後、居住支援法人などが安否確認や福祉サービスの案内などを行います。
例:人感センサー付き照明で長時間反応がないと通知が届く仕組みなど。
・大家さんとの連携
支援団体と大家さんが協力して、入居者の生活をサポートします。
・工事への補助制度あり
バリアフリーや見守り設備の設置などに対して、1戸あたり最大50万円の補助が受けられる場合もあります。
・家賃保証つき
一定の条件を満たせば、認定保証会社が家賃保証を引き受けるため、大家さんも安心です。
居住サポート住宅の制度はまだ始まったばかりで、現時点(2025年10月)では、福岡の🔗NPO法人抱僕(ほうぼく)の🔗「プラザ抱僕」のみの登録となっていますが、今後は少しずつ広がっていく見込みです。
セーフティネット住宅や、居住サポート住宅に入居できる人とは?
この制度は、「住宅の確保に特別な配慮が必要な方」(住宅確保要配慮者)が対象です。具体的には、以下のような方が該当します。
■ 主な対象者(例)
- 障がいのある方(身体・精神・知的など)
- 高齢者(特に一人暮らしの方など)
- 生活保護受給者や低所得の方
- 子育て世帯(ひとり親家庭など)
- 低額所得者(月収15.8万円[収入分位25%]以下)
- 被災者、DV被害者、住まいを失った方 など
こうした方々は、一般の賃貸住宅では入居を断られてしまうケースも少なくないため、「セーフティネット住宅」や「居住サポート住宅」は、安心して暮らせる新たな住まいの選択肢として期待されています。
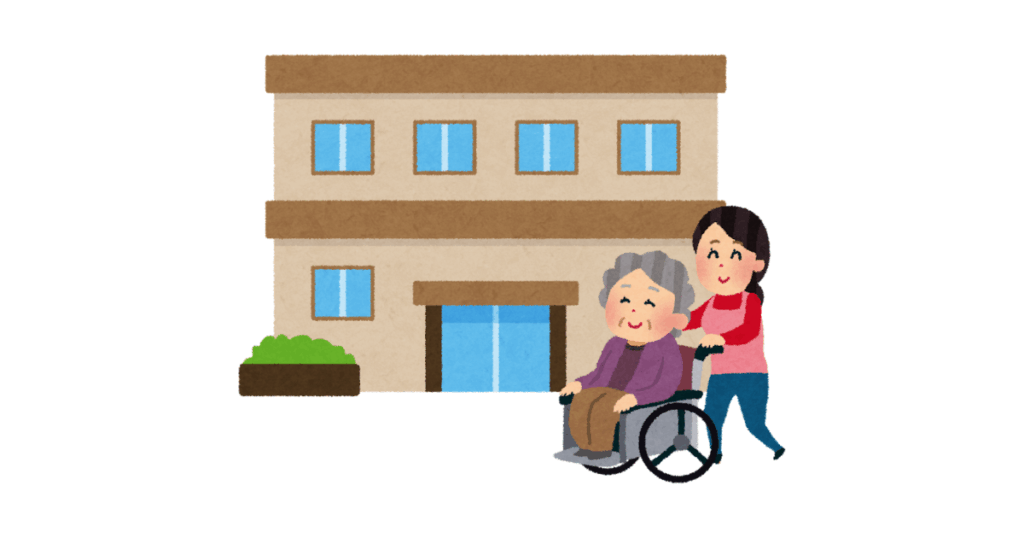
障害のある人が部屋が借りられない現実
制度の隙間に落ちやすい
障がいのある人は、「部屋を借りる」ということさえも、難しい現実があります。
- 民間賃貸 → 障がいがある、保証人がいない、収入が少ない、もしくは生活保護で審査落ち
- 公営住宅 → 抽選に落ちる or 条件に合わない(車いすだけど物件にエレベーターがない、など)
- シェアハウス → 障がい者向けがみつからない
- 福祉施設 → 空きがない、長期間入居できない
このような場合、「住む場所がない人」になってしまう危険性があります。
借りられずに困った時は、公的な支援機関の力を借りよう
住まいがなかなか借りられない時、公的な支援機関の力を借りることも重要です。
相談員さんやケースワーカーさんがいる場合は、相談してみたり、以下のような団体・制度を活用することで、住まい探しの負担を軽減できます。
1.グループホームの活用
精神・知的障がいのある方が少人数で暮らせる制度。自由度やプライバシーの面で制限もありますが、支援体制が整っています。
浜松市障がい者グループホームについて:🔗グループホーム
2.障がい者相談支援センター
自治体が設置する窓口で、障がい福祉サービス全般に対応。住宅に関する相談も可能です。
「○○市 障がい者 相談」で検索してみましょう。
🔗浜松市障がい者相談支援センター一覧
<相談支援センターについて、当ブログでも紹介していますので、参考にしてみてください。>
「相談支援事業所」のしくみと利用方法
3.社会福祉協議会の生活支援
家具・家電の提供や引越し費用の補助など、生活立て直しを支援する制度があります。一度相談してみるのも◎。
🔗全国社会福祉協議会
障がいのある方の住まい探しは、「一人で頑張らない」が成功のカギ
つらい所ですが、障害のある方が、部屋探しを一人で進めると、「お断り」の連続で心が折れてしまうことも。
「一人で頑張りすぎない」ことが重要です!
でも、支援者や専門の団体と一緒に動くことで、これまで閉ざされていた扉が開くことがあります。住まい探しは、信頼できる人たちとチームで取り組みましょう。
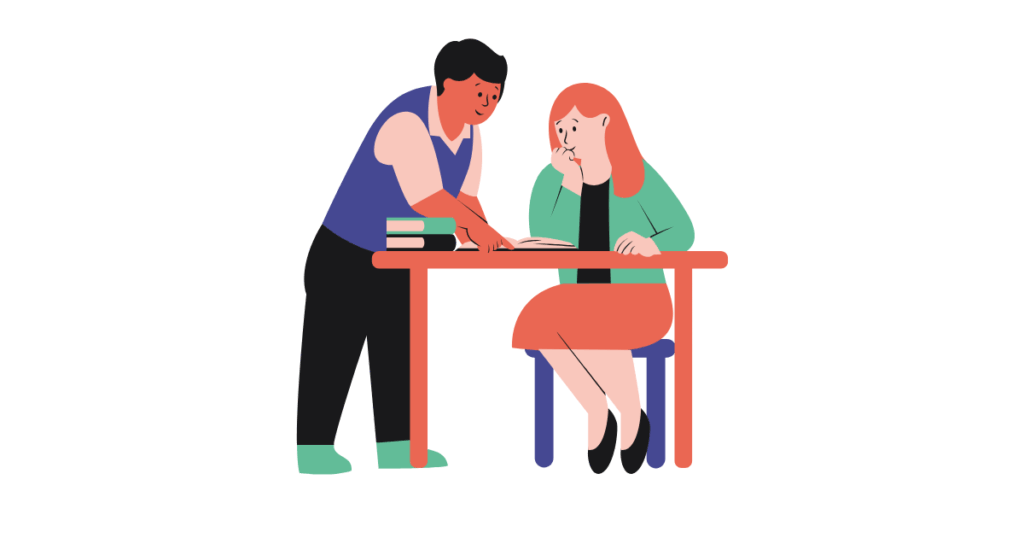
【まとめ】むずかしい住まい探し、それでも「選べる道」はある
障がいがある方の住まい探しは思った以上に大変です。
住みたいと思っても、体の状態に合わなかったり、審査に通らなかったり、生活保護や保証人なしの条件で選べる部屋が限られてしまうこともあります。それでも、少しずつ道を広げていく方法はあります。
- 民間の賃貸:保証会社や福祉に詳しい不動産会社を利用する
- 公営住宅:定期的な募集をチェックし、あきらめずに応募を続ける
- 支援機関:相談することで物件を紹介してもらえることも
今すぐ見つからなくても、動き続けることで次のチャンスが生まれます。
一人で悩まず、相談員さんやケースワーカーさんにも力を借りながら進めていきましょう。
障がいのある方にとって、住まいは安心して過ごすための大切な場所です。
心からくつろげる住まいと出会えることを願っています。