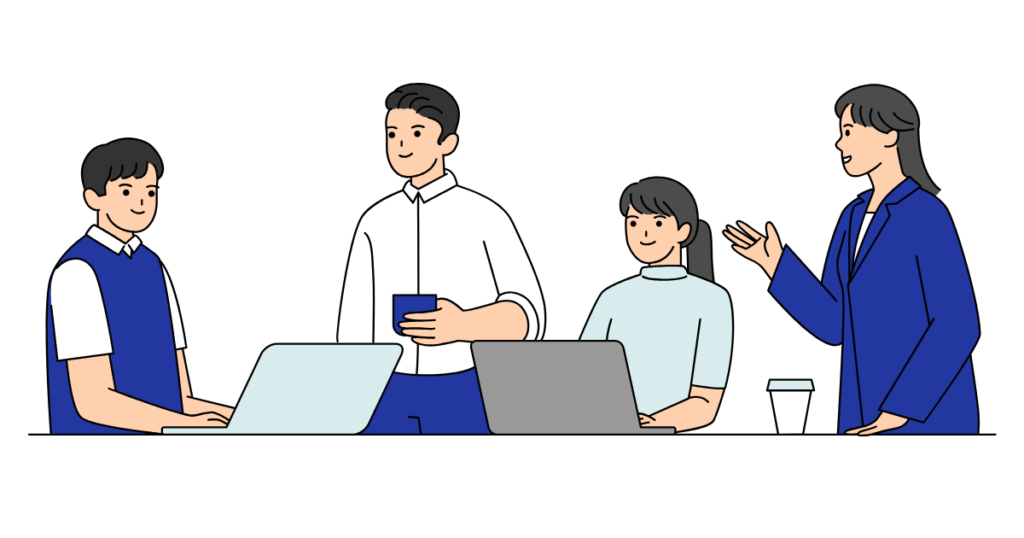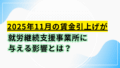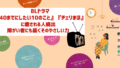2025年10月から2026年3月にかけて、日本全国の各都道府県で最低賃金が大幅に引き上げられる予定です。静岡県でも、これまで県の最低賃金は「1,034円」でしたが、11月1日から「1,097円」に改定されました。👉🔗令和7年度「静岡県最低賃金」の改正を決定しました
特にパートやアルバイトとして働く方にとっては、「生活はどう変わるのか」「税金などの〇〇万円の壁とか大丈夫かな?」など、気になるポイントは多いでしょう。本記事では、今回の最低賃金改定の内容をわかりやすく整理し、メリット・デメリット、そして改定を最大限に活かす方法を解説します。
あわせて読みたい!!:🔗2025年11月の賃金引き上げが就労継続支援事業所に与える影響とは?
※この記事は、2025年10月時点での国の税制度に基づいて作成しています。
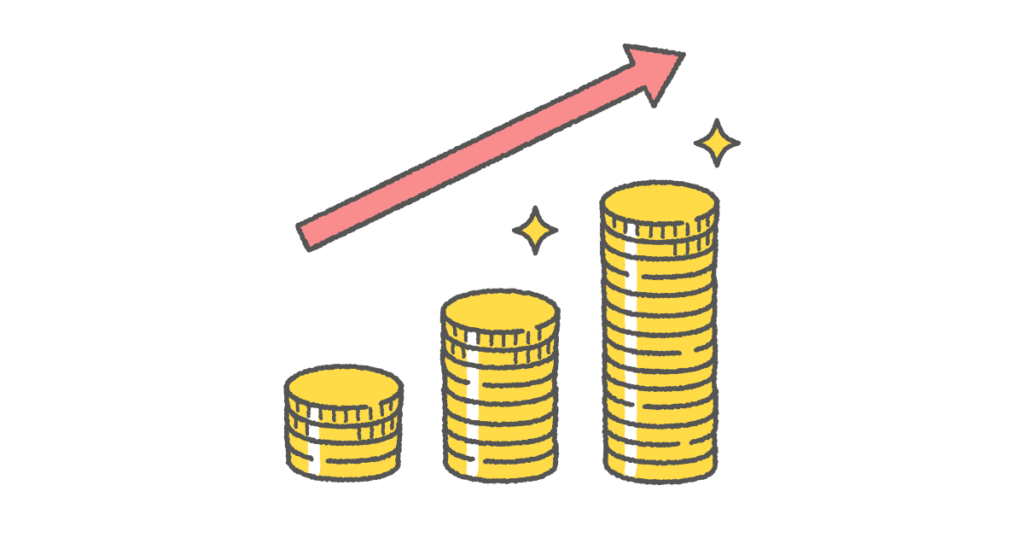
💰最低賃金とは?
最低賃金とは、働く人が1時間働いたときにもらえる「最低限のお給料」です。
これは法律で決められており、会社やお店などの事業主は、この金額より少ないお給料で支払うことはできず、最低賃金の金額は、物価や生活費などを考慮して、都道府県ごとに決められています。
この制度は、働く人が安心して暮らせるようにするための仕組みです。
また、みんなの収入が一定以上あることで、買い物などの消費も増え、経済の活性化にもつながります。
☝️今回の改定のポイント
厚生労働省によると、令和7年10月~令和8年3月にかけて都道府県ごとに賃金の引き上げが徐々に行われ、全国平均で60円~80円の上げ幅になる予定で、例年に比べて大きな上げ幅となっています。特に上げ幅が大きい都道府県(東京都、神奈川県、大阪府)は、生活費の増加が大きい都市部や物価上昇率が高い地域です。
厚生労働省:🔗地域別最低賃金の全国一覧
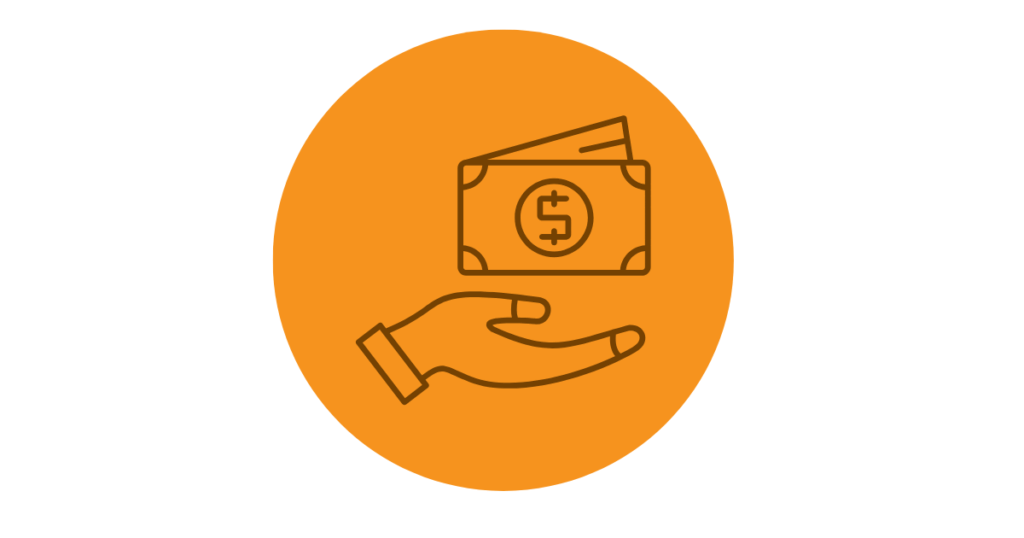
🙋♂️働く人への影響とメリット・デメリット
賃金が上がるということは、単純に働く人にとってはうれしいように感じますが、製造業では製品の価格が上がったり、実はデメリットも多いかも?しっかり両方を把握しておきましょう。
最低賃金が上がるメリット
最低賃金が上がると、手取りが増えて生活に余裕が生まれます。
時給が70円上がると、週20時間働く場合は月に約5,600円アップ。ちょっとした余裕ができるだけで、暮らしも気持ちも少し楽になります。安定した収入は、前向きな気持ちにもつながります。
最低賃金が上がるデメリット
働く時間を削ったり、採用枠が少なくなる可能性
雇用主は人件費の負担を減らすために勤務時間を短くしたり、新しい採用を見送る可能性が増えます。
未経験者や、シフトの柔軟性が弱い人は採用が難しくなる可能性
研修などにあまり時間をさけなくなるため、未経験の方や短時間しか働けない方は、採用が難しくなることもあります。
自動化・省力化になる可能性
製造や物流の現場では、AIやロボットを使って自動化を進める動きが広がる可能性もあります。

👛忘れちゃいけない!所得税・住民税・年金保険の「〇〇万円の壁」
最低賃金が上がるということは、「〇〇万円の壁」についても頭に入れておく必要があります。それぞれ、以下にご紹介します。
<💡知っておくべき用語(間違えやすいポイントに注意!)>
・「控除」:税金などの計算で差し引かれる金額
・「給与収入」:税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与額(いわゆる「総支給額」)。
・「手取り」、「手取り額」、「差引支給額」:税金・社会保険料などが差し引かれたあと、実際に口座に振り込まれる金額。
・「給与所得控除」:自営業者が確定申告で「基礎控除」を差し引くのと同じ考え方で、会社員やアルバイト・パートの人が受けられる給与に対する基礎的な控除。
・「給与所得」「所得金額」:「給与収入」から「給与所得控除」を差し引いた、実際の所得額。
・「課税所得」:所得から給与所得控除などの各種控除(基礎控除・扶養控除など)を差し引いたあと、実際に税金がかかる金額。
まずは「所得税」。その仕組みとは?
お給料から引かれる所得税は、次の流れで計算します。
- 給与収入から「給与所得控除」を引きます。
- さらに、「社会保険料控除」、「基礎控除」や「扶養控除」「障害者控除」などを引きます(この時残った額が「課税所得」です)。
- 「課税所得」に税率をかけます。所得金額が195万円超の場合は、さらに所得金額に合わせて控除額を引きます。
税率や控除額は以下の表のとおりです。課税所得での計算なので、間違わないように気をつけましょう。
所得税の速算表(2025年4月現在)
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 194万9000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万円9000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万円9000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万円9000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万円9000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
実際の計算方法 「例:課税所得が200万円の場合」
- 税率の確認
課税所得200万円は「195万円超330万円以下」の区分に該当するため、税率は10%、控除額は9万7,500円です。
- 所得税額の計算
2,000,000円×10%−427,500円=95,500円 課税所得200万の場合は、所得税は95,500円となります。
国税庁:🔗所得税の税率
所得税の「障害者控除・障害者特別控除・同居特別障害者控除」(2025年4月現在)
※住民税の控除もありますが、ここでは所得税のみ紹介します。
障がいのある人の税金を軽くする制度です。障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者控除の場合は75万円)が控除されます。本人や家族が対象の場合は、事前に勤務先へ申請するか、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。
※配偶者控除と併用できます。
<障害者控除>
・身体・精神・療育の各障害者手帳を持つ人:27万円の「障害者控除」
・各障がい者手帳を持つ、重度の障害者(1級・A判定など):40万円の「特別障害者控除」
・特別障害者と同居して扶養している人場合:75万円の「同居特別障害者控除」
国税庁:🔗障害者控除
所得税の「配偶者控除・配偶者特別控除」(2025年4月現在)
※住民税の控除もありますが、ここでは所得税のみ紹介します。
配偶者(夫や妻)を扶養している人の税金を軽くする制度です。
例として、会社員の太郎さんが、花子さんと結婚している場合で説明します(事実婚や内縁関係の場合は適用外)。なお、控除の説明であるため、以下の花子さんの収入の部分は、手取り額ではなく、給与収入での説明となります。
<配偶者控除>
花子さんがパートに出て、1年の給与収入が「123万円」以下で、太郎さんの合計所得金額が1,000万円以下の場合は、最大38万円の控除が適用されます。(これが「123万円の壁」)
<配偶者特別控除(その1)>
花子さんがパートに出て、1年の給与収入が「123万円超〜160万円以下」で、太郎さんの合計所得金額が1000万円以下の場合は、最大38万円の控除が適用されます。(これが「160万円の壁」)
<配偶者特別控除(その2)>
さらに、花子さんのパートの1年の給与収入が「160万円超〜201万6,000円以下」で、太郎さんの合計所得金額が1000万円以下の場合は、配偶者の収入が増えるにつれて、控除額が段階的に減額されます。
太郎さんの合計所得金額が1,000万円を超えたり、花子さんのパートの1年の給与収入が201万6,000円以上になると、配偶者控除・配偶者特別控除ともになくなります。
太郎さんが会社員、花子さんが自営業者の場合
花子さんの合計所得金額(売上-経費)が、58万円以下で、太郎さんの合計所得金額が1000万円以下の場合は、最大38万円の控除が適用されます。
太郎さんが自営業者の場合
花子さんが太郎さんの仕事を手伝っていない(軽く手伝っていて、お給料も発生していないも含む)と、配偶者控除を受けられる場合があります。
しかし、花子さんが太郎さんの仕事をあきらかに手伝っている(お給料の発生あるなしいずれも含む)と、「事業専従者控除」での控除となり、配偶者控除が適用されません。
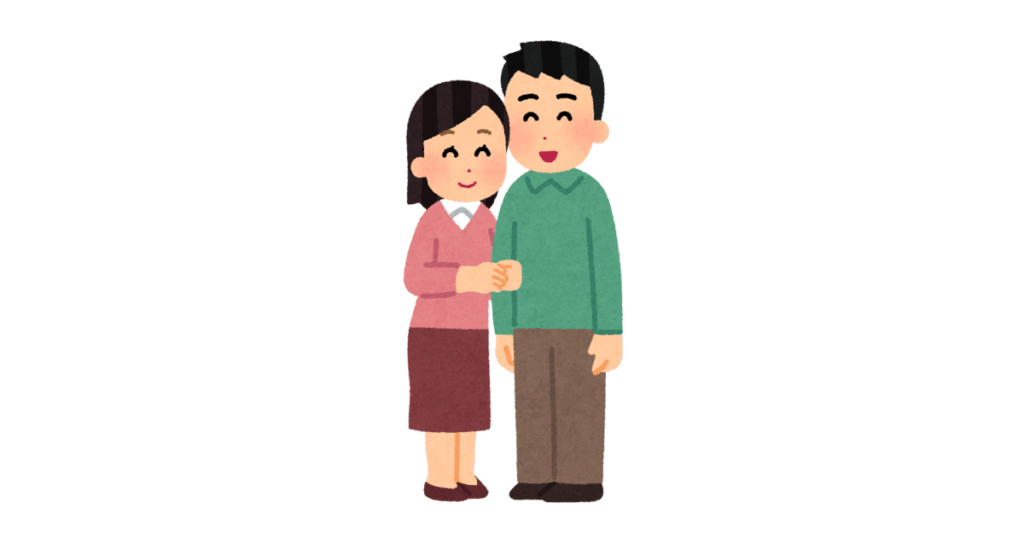
所得税の「特定扶養親族(扶養控除)」(2025年4月現在)
※住民税の控除もありますが、ここでは所得税のみ紹介します。
家族を養っている人(=働いて家族を養っている人)の税金を軽くする制度です。
扶養している家族の年齢や所得によって、控除額が変わります。事前に勤務先へ申請するか、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。
<子供などの扶養控除>
・一般の扶養親族(16~18歳・23歳~、被扶養者の給与収入が123万円以下):38万円
・特定扶養親族[大学生など](19~23歳未満):63万円
・特定親族特別控除(納税者と生計を一つにしていて、アルバイトなどをする19歳以上23歳未満の親族):63万円
※子の1年の給与収入が149万9000円までは満額の控除。150万円超~188万円の場合、控除額が段階的に減ります。
☝️同居の有無は問わない。16歳未満の子は扶養に入れますが、税金上の扶養控除はなし(代わりに児童手当の対象)。年齢は1月1日時点で計算。
<親の扶養控除>
・同居していない老人扶養親族:48万円
・同居している老人扶養親族(親など):58万円(同じ敷地内など、完全同居でなくても生計が一緒であればこちらに該当)
☝️70歳以上の親や祖父母などで、扶養している人と生計を一にしていて、年間の所得が48万円以下(年金だけなら年金収入約158万円以下)であること。年齢は1月1日時点で計算。
三菱UFJ銀行:🔗扶養控除とは?配偶者控除との違いや年収の壁、改正後の控除額をわかりやすく解説!
所得税「103万円の壁」→「160万円の壁」に改定
ここでの「160万円の壁」は、前述の配偶者特別控除の話とは別物です!混同しないように注意しましょう。
2025年度の税制改正で、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」に変わりました。
これまで所得税がかからない年収の上限は「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円」でしたが、改正後は「給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円」となり、所得税がかからない範囲が拡大。
ただし、基礎控除95万円が適用されるのは、給与収入が200万円以下の人だけ。200万円を超えると、控除額は段階的に少なくなります。
たとえば、2025年秋の全国平均時給(約1,121円)で考えると、160万円 ÷ 1,121円 ≒ 1,428時間。
1日6時間・週5日ペースだと、1年で約1,440時間になり、少し働きすぎると壁を超えてしまう計算です。
三菱UFJ銀行:🔗160万円の壁とは?103万円の壁からいつ変わる?メリット・注意点も解説
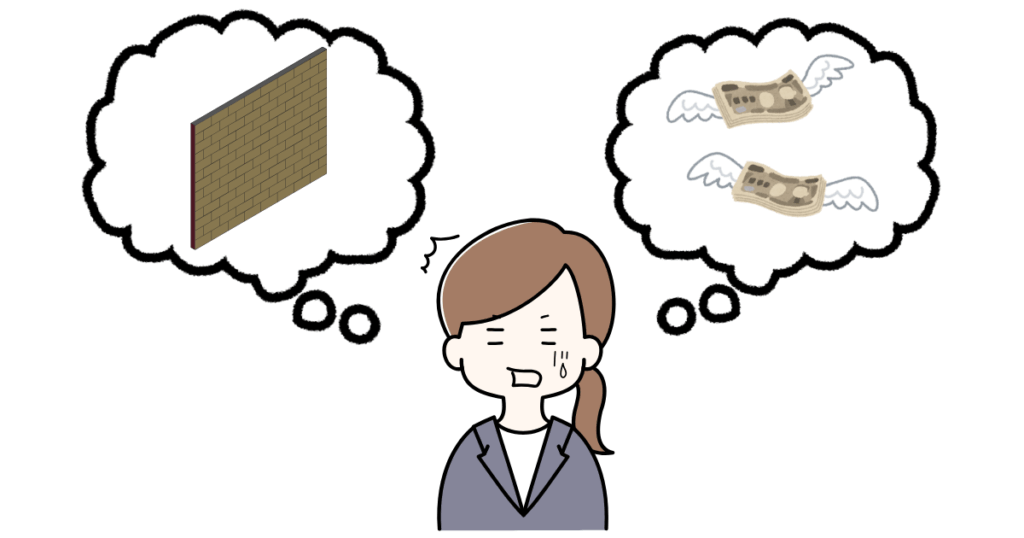
次は住民税!2026年度分から「110万円の壁」登場!?
これは 住民税の課税基準 の話であり、配偶者控除とは別制度です。混同しないようにしましょう。
2026年度課税分(2025年中の収入を元に、2026年度住民税が課税)から、これまで「100万円前後」が目安だった住民税の非課税ラインが「110万円あたり」まで引き上げられる見込みです。
住民税の障害者控除
障がい者や生活保護を受けている方は、住民税が非課税になる場合があります。ただし、条件は自治体によって異なるため、確認が必要です。
たとえば、2025年10月時点で、浜松市では障がい者手帳を持つ方は、前年の収入が135万円以下だと非課税ですが、東京都23区では手帳を持っていれば収入に関係なく非課税です。
住民税の配偶者控除・扶養控除
住民税の配偶者控除・扶養控除は、自治体ごとに基準や非課税枠が異なるため注意が必要です。
先程のとおり、2026年度以降は住民税の課税対象が110万円あたりと推定されますが、自治体によって若干差があります。
また、2025年の最低賃金改定で年収換算が変わると、控除の対象範囲にも影響する可能性があります。年収が壁に近い場合は、控除対象になるかどうかを事前にシミュレーションしておくと安心です。
【実はここが一番大きな壁】年金保険は「106万円」と「130万円」の壁
これは 国民保険・社会保険(社会保険・厚生年金)の課税基準 の話であり、所得税や配偶者控除とは別制度です。混同しないようにしましょう。
<社会保険(社会保険・厚生年金)の場合(106万円の壁)>
扶養の有無を問わず、週20時間以上働き、月の給与が8.8万円以上(年収約106万円)になると、従業員51人以上の会社では社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
この「106万円の壁」は、2025年6月から3年以内に撤廃される予定です。さらに、2026年10月以降は、従業員50人以下の会社にも段階的に社会保険の適用が広がる見込みです。
<国民保険(国民保険・国民年金)の場合(130万円の壁)>
扶養に入っている人が、年収130万円を超えると、自分で国民健康保険・国民年金を払わなければならなくなります。
そのため、扶養に入っているパート・アルバイトの人は、手取りが減らないように収入を壁内に抑えることが多いです。つまり「これ以上働くと損になる」目安の金額です。
<💡ここで配偶者特別控除や特定親族特別控除との矛盾が!!>
配偶者特別控除は、給与収入が160万円、特定親族特別控除は150万円未満までは満額の控除が受けられるのに、その前に106万円や130万円の年金保険の壁を超えると、自分で健康保険・年金を払わなければならなくなる!ここは頭に入れておきましょう。
独り暮らしなどの扶養に入っていない人は、収入に関係なく、勤務先の社保に入るか、国民健康保険に入る必要があります。(これが「国民皆保険」)
あわせて読みたい!!:🔗【手取りが減る?】A型事業所利用者にも影響する「106万円の壁」とは?

☝️派遣社員や在宅ワークの場合の注意
派遣社員は、通常、派遣元の人材派遣会社からお給料が支払われますが、派遣元ではなく派遣先の企業の所在地の最低賃金が適用されます。また、在宅ワークをしている場合、勤務先の所在地の最低賃金が適用されます。そのあたりが間違いがないかを確認しましょう。
例:人材派遣会社の所在地は東京都で、派遣されている勤務先企業が神奈川県の場合、神奈川県の最低賃金が適用となります。また、愛知県で在宅ワークをしていても、勤務先の所在地が静岡県であれば、静岡県の最低賃金が適用となります。

💴最低賃金アップを賢く活かす方法
最低賃金が上がると、働く時間が減ってしまうこともあります。
そんなときは、空いた時間をスキルアップや資格取得に使ってみるのもおすすめです。増えた収入を貯金したり、副業を考えたりするのも良いかもしれません。変化のときこそ、自分の時間やお金の使い方を見直すチャンスです。
😧壁の種類
壁の種類を表にまとめました。最低賃金引き上げによる「壁対策」は、しっかり行っておきましょう。
| 壁の金額 | 主な影響内容 | 該当制度 | 補足・説明 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | – | 所得税(旧制度) | 2025年改正で廃止 |
| 106万円 | 2025年6月以降~3年以内に消滅する可能性 | 社会保険(106万円の壁) | 従業員数51人以上などの条件で厚生年金や健康保険に加入義務が発生 |
| 110万円※(※2026年度分の住民税以降) | 住民税(所得割)が課税 | 地方税(住民税) | 多くの自治体で住民税が発生。非課税枠あり(自治体差あり) |
| 123万円 | 配偶者控除/扶養控除の対象外 | 配偶者控除/扶養控除 | 103万円から引き上げ |
| 130万円 | 扶養から外れる(保険料自己負担) | 社会保険(130万円の壁) | 国保や国民年金に自分で加入する必要がある |
| 150万円 | 特定親族特別控除の満額対象外 | 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満の同居親族を対象に新制度が創設 |
| 160万円 | 所得税課税開始/配偶者特別控除の満額対象外 | 所得税/配偶者特別控除 | 所得が増えると配偶者特別控除額が段階的に減少 |
| 201万6千円 | 配偶者特別控除の対象外 | 配偶者特別控除 | 所得133万円超(給与換算201万6千円以上)で控除対象外 |
| 1,000万円(本人) | 配偶者控除・特別控除の適用不可 | 納税者本人の制限 | 給与収入換算で1,195万円超の場合、控除は不可 |
【まとめ】最低賃金アップの今こそ、働き方と税金を見直そう
2025年10月から最低賃金が引き上げられ、働く人にとっては収入アップや生活の安定につながるチャンスです。一方で、企業には人件費の増加という課題もあります。
でも、賃金の引き上げ後も“年収の壁”を意識せずに働くと、知らぬ間に税金や社会保険料の負担が大きくなっていて、手取りが増えず、結果的に損をしてしまうことも考えられます。
税金や控除の仕組みは少し分かりにくいですが、今回の賃金アップをきっかけに、自分の働き方や節税の方法を見直してみませんか?