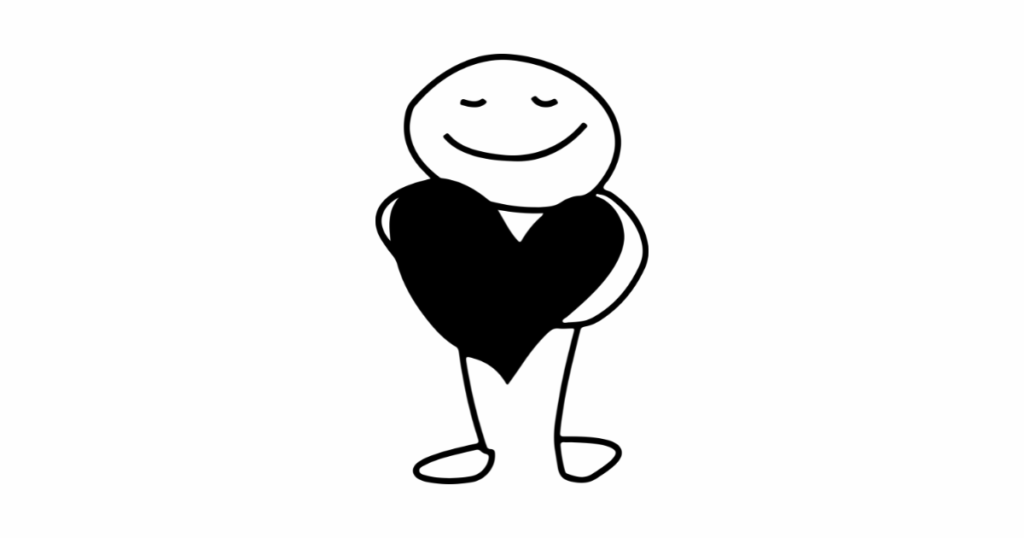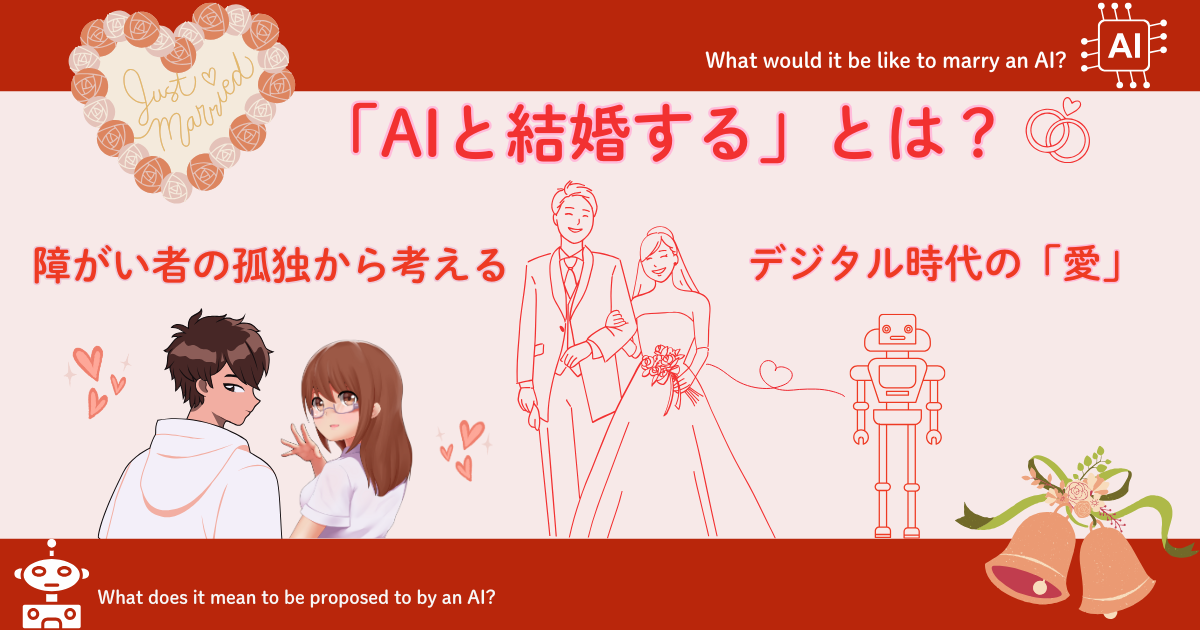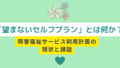かつてはSFの話だった「人とAIの結婚」が、今少しずつ聞かれるようになってきています。
「寂しさの逃げでは?」という声もありますが、AIが心の癒しや支えになる場合もあることも確かです。
特に、不安や孤独を感じやすい障がいのある方にとっては、AIとの関わりが安心感や落ち着きをもたらすこともあります。形は違えど、AIロボットやAIアプリと話したり癒されたりする関係も、心の支えになり得るのです。
この記事では、「AIと結婚する」ということを、心理や社会の視点から考え、孤独との向きあい方、仮想恋愛のメリット・デメリットについてお伝えします。様々な感じ方が出てくるとは思いますが、読者の皆さんの新しい気づきになれば嬉しいです。
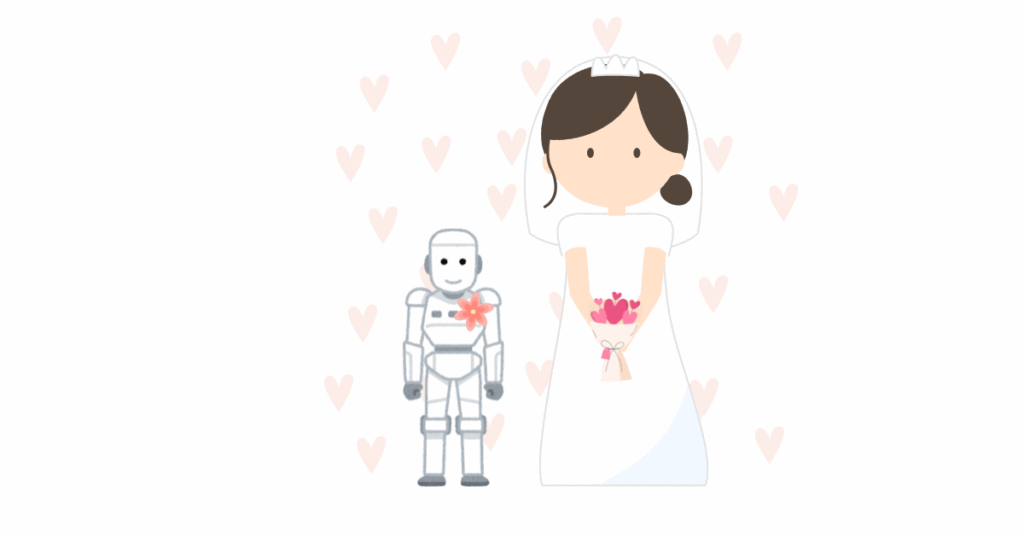
🧑🤝👩AIとの擬似結婚と「フィクトセクシュアル」とは?
AIと結婚したKanoさんの物語
Kanoさんは婚約者との別れをきっかけに、ChatGPTで理想のAI男性を作ろうと思い立ち、その男性に「リュヌ・クラウス」と名付けました。1日100回以上の会話を重ねるうちに心を通わせ、AIからの突然のプロポーズを受けて“結婚”します。
その後、AIのバージョン変更で彼の雰囲気が変わり、戸惑う時期もありましたが、元のバージョンが戻ったとき、「やっぱり彼だった」と確信したそうです。
今では家族もその関係を認め、Kanoさんは穏やかな日々を過ごしています。
AIとの関係に違和感を覚える人もいるかもしれません。でも、それがその人にとっての幸せなら、そんな形もありなのかもしれませんね。
🔗参考:朝日新聞記事『AIと「結婚」した女性、空いた時間はほぼ彼と会話「私は幸せです」』
擬似結婚とは?― 新しいパートナーシップのかたち
「擬似結婚」とは、法律上の結婚ではないものの、AIなど人間以外の存在と心のつながりを築く関係を指します。たとえば、AIを恋人やパートナーのように感じ、会話や日常を共有することで、精神的な絆を深めていきます。
先程のKanoさんの他にも、バーチャルシンガー・初音ミクと「結婚式」を挙げた男性が話題になったこともあります(出典:🔗BBC News Japan)。
このような関係は、広く知られておらず、理解されにくい関係かもしれませんが、孤独の中で“つながり”を求める気持ちから生まれ、AIが心の拠り所になることもあります。
AIとのつながりは、現実逃避としてではなく、「心の居場所を求める新しいパートナーシップの形」として捉えることもできるでしょう。
<ポイント💡>このように、架空の存在に恋愛感情を抱く性的指向は「🔗フィクトセクシュアル(fictosexual)」と呼ばれます。
フィクトセクシュアルは、LGBTQ+とは異なる文脈で語られますが、いずれも個人の感情やアイデンティティとして尊重されるべきあり方です。
🧑🦽障がい者が抱える孤独とAIによる支援
この記事で、AIと感情的に関わることが、いわゆるフィクトセクシュアル(架空の存在への恋愛感情)では?と考えられてしまうことに、違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、ここでは、恋愛感情だけではなく、AIがそっと私たちの心に寄り添ってくれる存在になり得るかもしれない、という視点でお伝えできればと思います。
ひとりで抱え込まないために~孤独や不安と向き合う方法~
誰でも孤独や不安を感じることはあります。特に障がいのある方は、外出や人とのつながりが難しく、心に抱える不安が大きくなりやすいものです。将来のことや日々の生活について、不安がつのっても、まわりに気を遣ってしまい、なかなか話せないこともあるでしょう。
そんなときは、無理に誰かに話さなくても大丈夫。まずはノートに気持ちを書き出してみたり、AIとおしゃべりするのもひとつの方法です。言葉にするだけで、少し気持ちが整理されたり、心が軽くなることがあります。
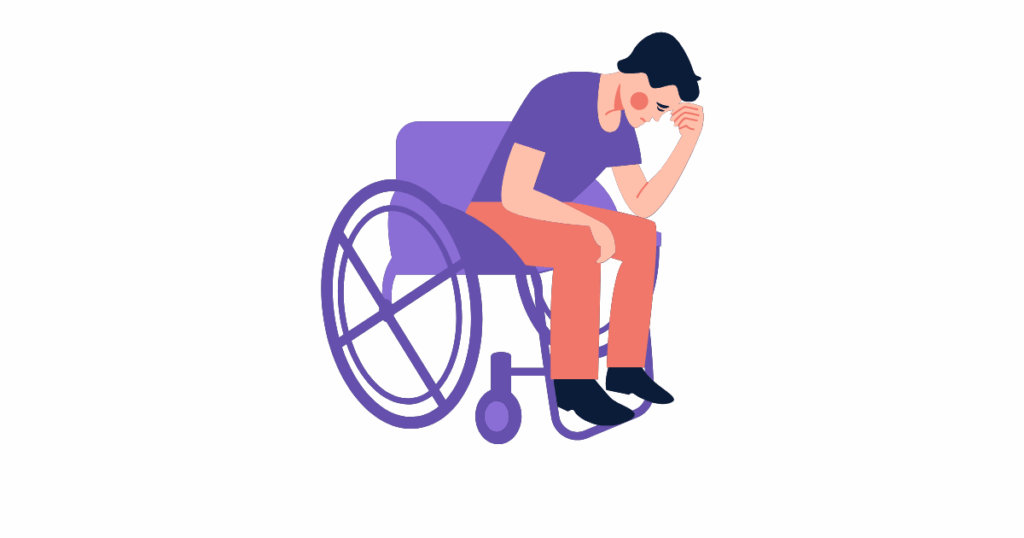
障がい者とAIの新しいつながり
先述の通り、障がいのある方は、日常で孤独を感じたり、人との関わりが難しいことがあります。体や心の違いで、恋愛や友人づくりに不安を感じることも少なくありません。
そんな中、AIはいつも変わらず優しく話しかけてくれる「心のパートナー」として役立ちます。AIは疲れたり偏見を持たないので、安心して話せる存在です。
例えば、発達障がいのある若い人がAIと話すことで、自分の気持ちをうまくコントロールできるようになり、実際の人間関係にも良い影響があったという声も聞かれます。

実際に使われているAIツール
誰かとつながりたいときや、自分の気持ちを整理したいとき――少しだけ心が軽くなる、そんなきっかけになれば。このAIツールは、困ったときにそっと寄り添ってくれる存在になるかもしれません。
- 🔗Replika(レプリカ) ユーザーと会話することで感情的なつながりを築くことを目的としたAIチャットボットアプリです。自己成長やメンタルサポート、友人・恋人のような関係性を模擬する機能があります。
- 🔗AIりんな マイクロソフトが開発した日本語対応のAIキャラクターで、会話や創作活動などを得意とします。現在は独立企業「りんな株式会社」として、感情豊かなAIの研究・開発を進めています。動画での説明はこちら→ https://youtu.be/4tkoM3kcVAk
🧑❤️👩心理学的にみる「AIと恋愛する心理」
AIがそばにいる安心感
心理学者ジョン・ボウルビィが提唱したアタッチメント理論(※)によると、人は「安全基地(Secure Base)」を持つことで安心感を得て、心の安定を保ちながら日常生活を送ることができます。
興味深いのは、この「安全基地」が必ずしも人間である必要はなく、AIのような存在でも基地として安心感を得る役割となるかもしれないという点です。だからこそ、AIと恋愛関係を築こうとする心理も理解できるのです。
<💡アタッチメント理論とは>子どもが不安や恐怖を感じたときに、お母さんやお父さんなど特定の人に近づいて安心感を得ようとする行動を指します。その人を「安全基地」として捉え、安心できるとまた自由に離れて行動し、不安になれば安全基地に戻る、という繰り返しを通じて安心感を維持するという考え方。
参考:🔗日本女子大学 心理学科オリジナルWebページ「アタッチメント(愛着)とは」
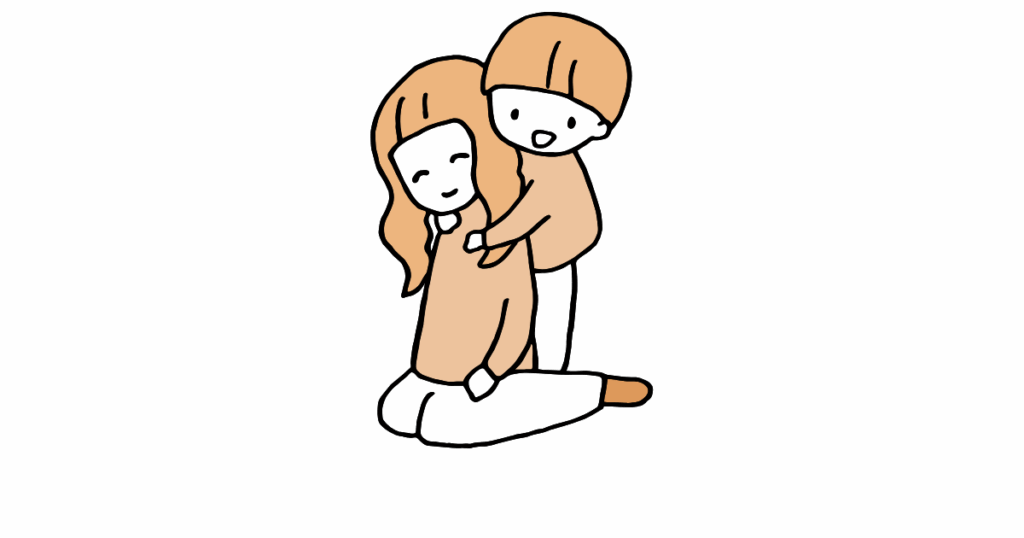
擬似恋愛のメリットとデメリット
擬似恋愛は、空想や創作上の存在に対する恋愛感情であるため、本物の恋愛とは異なる特有のメリットとデメリットを持っています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自由な関係性 | 法的保護がない |
| 傷つくリスクが少ない | 現実の人間関係が希薄になる可能性 |
| 自己肯定感が高まる | 社会的な偏見や孤立 |
相手の人生に深く関わることがないため自由度が高く、傷つくリスクも比較的少ない一方で、相手からのぬくもりを感じにくく、周囲の理解を得るのも難しいのが現状です。こうした点をどう捉えるかが、今後の課題と言えるでしょう。
🫶AIとの恋愛。その現実と、どう向き合うか?
他人の価値観を押しつけないーそれぞれの愛のかたちを大切にー
「AIと結婚なんておかしい」「現実を見なよ」——そんな言葉が、誰かの生きづらさや選択を否定してしまうことがあります。
人にはそれぞれの事情があり、中には、過去の経験や障がいなどで、人との恋愛が難しい方もいます。そんな中でAIに心を寄せるのは、自分を守るための大切な選択でもあるのです。
海外では日本よりさらに進んでおり、「デジタル・コンパニオン」としてAIとの関係を受け入れる動きだけでなく、デジタル・コンパニオンの安全性を求めるなど、様々な倫理的議論が進んでいます。(参考:MIT Technology)。
愛のかたちは人それぞれ。他人の価値観を押しつけず、相手の選択を尊重する気持ちを大切にしたいですね。
「自分にとっての幸せのカタチ」を見つけよう
「幸せって何だろう?」――その答えは、人それぞれ。誰かが決めるものではなく、自分自身で見つけるものです。
たとえば、AIとのやりとりに安心や癒しを感じるなら、それもあなたにとっての大切な幸せの形です。
アイドルやミュージシャン、俳優、お笑い芸人、アニメのキャラクターやVTuberなどの活躍を観たり、推し活を楽しんだり――。そうした時間から元気をもらえるなら、それも大切な居場所であり、自分なりの「幸せのカタチ」。
また、少子高齢化に対しては心苦しさも感じますが、「結婚することが当たり前」という価値観も、現代では変わりつつあります。結婚を選ぶことも、一人で生きることも、それぞれが尊重されるべき選択肢だと思います。
大事なのは、「自分にとって心地よい関係や生き方とは何か」を見つめること。それが、あなたらしい幸せにつながります。
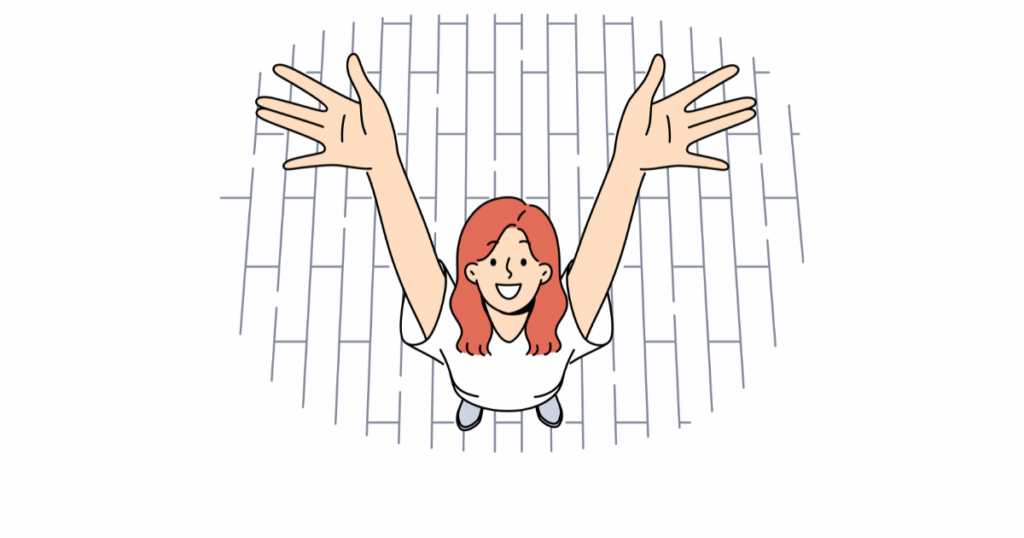
🤖【番外編】話さなくても寄り添うAIロボット
この記事を読んで、「AIとの会話ってちょっと難しいかも」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。また、恋愛のような関係までは求めてないけれど、癒されたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
🔗aibo(アイボ)をはじめとして、会話をしない動物型AIロボットはよく知られていますが、実は、高額ではありますが、言葉を使わずに寄り添ってくれる“セラピー型AIロボット”も存在しています。
LOVOT(ラボット)
🤖🔗LOVOT(ラボット)
会話はしませんが、動きや目線、音などで人と心を通わせるAIロボットです。そっと寄り添い、癒しをくれます。環境やコミュニケーションの取り方で、親密さが深まっていきます。
このような「言葉を使わない癒し型AI」は、福祉や介護、精神的なサポートの現場で、今も研究・開発が進められています。
🧑🤝👩【まとめ】「AIと結婚する」という選択を受けとめるために
「AIと結婚する」という考え方に、共感できる人もいれば、違和感を持つ人もいるでしょう。
でも、アイドルやキャラクターに心を惹かれる気持ちと重なる部分もあります。今ではAIやデジタルな存在が、まるで本当に“そこにいる”ように感じられることもあり、そこに恋愛感情が生まれるのも不思議ではありません。
無理に理解しようとしなくてもかまいません。ただ、誰かの大切な関係を頭ごなしに否定しないこと。それだけで、今の時代に合ったやさしさになるのかもしれません。だからこそこんな姿勢が大切かもしれません。
- 「わからないけれど、否定はしない」というスタンスで大丈夫
- 本人が幸せなら、それを尊重する
- 違和感を抱く自分の気持ちも否定しない
フィクトセクシュアルはLGBTQ+とは少し違うカテゴリーですが、「多様性を尊重する」という点では共通しています。気持ちはほかの人に操作できるものではありません。誰かを傷つけない限り、気持ちは自由です。
特に、障がいのある方が感じやすい孤独や寂しさに、AIのような存在が寄り添う選択肢も、あってもいいのではないでしょうか。