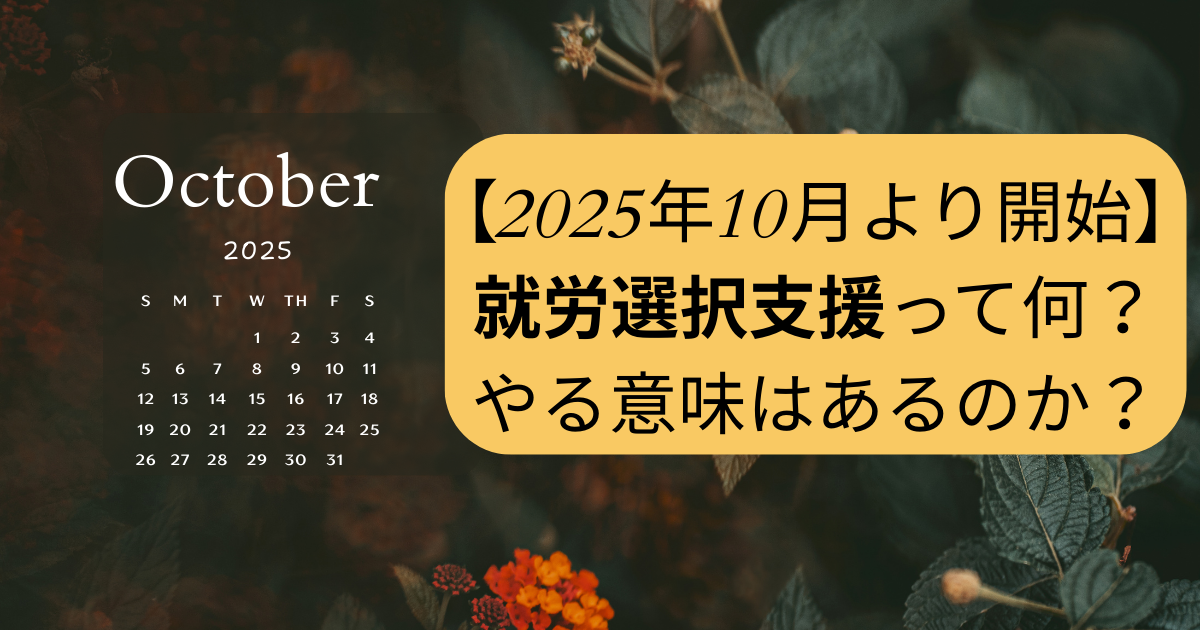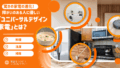こんにちは。A型事業所で在宅勤務をしているKです。
最近「就労選択支援」という聞き慣れない言葉を、目にするようになりました。
就労選択支援、厚労省がマニュアル作成 10月施行前に課題共有(福祉新聞)
でも正直なところ、「就労選択支援って、何のためにやるの?」「今の働き方でうまくいっている私にも必要なの?」という疑問が消えません。
そこで今回は、この制度の概要と利用者として感じたこと、意味があると感じた点・疑問に思った点を、自分なりにまとめてみたいと思います。
就労選択支援とは?制度の概要
就労選択支援は、2022年に改正された障害者総合支援法に基づく就労支援の一つで、2025年10月から開始されます。
■ 定義(何をする制度なの?)
就労選択支援は、障害がある人が自分に合った働き方や進路を見つけるために、短期間(原則1か月)の間、作業体験や面談、アセスメント(評価)を受けられる新しい福祉サービスです。
特徴は、“働く準備”よりも、“働く方向を決める”ことに重点を置くという点です。
■ いつから始まるの?
全国的には2025年10月に開始され、段階的に義務化されていきます。
| サービス区分 | 就労選択支援の利用が原則必要になる時期 |
| 就労継続支援B型 | 2025年10月〜(新規利用者) |
| 就労継続支援A型 | 2027年4月〜(新規利用者) |
| 就労移行支援 | 希望者はいつでも、2027年4月から原則化予定 |
| 特別支援学校生徒 | 利用可能(進路選択支援として) |
※50歳以上や障害基礎年金1級を受給している人などは、例外として省略される可能性があります。
どんなことをするの?
主に、以下のような支援を1か月ほどかけて行います。
作業体験と就労アセスメント
- データ入力、軽作業などを試しながら、得意・苦手を見つける
- 賃金や勤務時間など、働き方の希望を整理する
ケース会議
- 本人・家族・支援者・関係機関が話し合い、今後の進路を相談
アセスメントシートの作成
- 就労能力、課題、配慮事項などを明文化し、今後の指針に
関係機関との連携
- 他事業所やハローワークの見学調整、体験支援なども
誰が支援をしてくれるの?
この支援は、以下のような事業所や機関が行います。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 自治体設置の就労支援センター
- 障害者就業・生活支援センターなど
人員基準としては、「利用者15人につき支援員1人」が配置されます。サービス管理責任者の配置は不要で、比較的短期で完結するのが特徴です。
支援を行う人の資格は?
「就労選択支援員」として対応するためには、所定の研修(11時間)を受け、テストに合格する必要があります。
- オンデマンドの基本講義:6時間
- 対面での実践演習:5時間
- 最後にテスト(オンラインで満点必須)
実務経験者やすでに他の支援研修を修了している人には、受講の経過措置が設けられています。
利用者から見て、やる意味あるの?
ここからは、私自身が「A型事業所で働く利用者」の立場から感じたことを、意味があると感じた点/あまり意味を感じにくい点の両面でまとめてみます。
✅ 意味がある・価値があると感じる場面
「立ち止まる」時間になる
日々の作業に追われて、「将来どうしたいか」をあまり考えられなかった私にとって、就労選択支援は“立ち止まって考える時間”になるかもしれないと感じました。
支援員さんと一緒に、自分の適性や希望を整理する中で、
- 「このままA型で続けたいのか」
- 「実は移行支援や一般就労に興味があるのか」
をあらためて考え直せる時間になるのでは、と思います。
移行や変更を考えている人には有効
たとえば、体調が変わってB型に移りたい人や、「A型は卒業して移行支援に挑戦したい」と考えている人にとっては、自分の意思や準備度を見極める貴重なプロセスになりそうです。
自分の強みや苦手を“見える化”できる
第三者の視点が入ることで、「自分では気づいていなかった得意な作業」や「仕事上の注意点」を知ることができるのは大きいです。
就労アセスメントやケース会議で、「自分を客観的に見つめ直す」チャンスになるのは、意外と貴重です。
❌ 意味が薄い・不安に感じる点
今のA型で安定している人には“形式的”に感じる
「もう今のA型で満足してるし、変えるつもりはないんだけど…」という人にとっては、「なぜ1か月も抜けなきゃいけないの?」と疑問に思うのは当然です。
私も、正直なところ「通過儀礼みたいに義務化されるならちょっと嫌だな」と感じています。
また、この制度には、利用者の職業能力を無理やり評価し、まるで「就労にふさわしいかどうか」を上からチェックするような側面があると感じています。
つまり、障害のある私たちの多様な個性や生活リズムを十分に尊重せず、都合のいい形に合わせようとしているように思えて、とても不安で怖くなります。
1か月だけでは判断が難しいケースも
精神的な波や体調に変化がある人にとっては、「たまたま調子が悪かった1か月」で評価されるのが不安です。
特に精神・発達障害の人にとっては、「短期間の体験で何がわかるの?」という声もあるようです。
運用次第で「ただの制度」になるリスク
本人の意向や生活状況を無視して、「とにかくやらなきゃいけない」となってしまえば、制度疲れや支援の形骸化につながってしまいます。
最後に:この制度は、誰のためにあるのか
「就労選択支援」の話を聞いたとき、正直なところ「また利用者のことを十分に考えていない、面倒な制度ができたな」と感じました。
でも、調べるうちに、この制度は本来“自分の働き方を自分で選ぶための仕組み”であるはずだということが見えてきました。

(写真 K)
これまで「A型以外に選択肢がない」と思い込んでいたのは、単に情報が不足していただけかもしれません。
この制度が、もう一度自分の「働く意味」や「将来の目標」を考えるチャンスになるなら、その価値は決して無駄ではないと思います。
ただし、それは「利用者の声に真摯に耳を傾ける支援者」と出会えた場合に限る、と強く感じています。
私たちは単なる“制度の対象”ではなく、“この制度の主役”であるべきだからです。
もしこれから就労選択支援を受けることになったら、その時間を「自分自身を見つめ直すきっかけ」として、少しでも前向きに向き合いたいと思います。
※この記事は、A型事業所「メジャーサポートサービス」で働く利用者の立場からの個人的な意見です。最新の制度情報は、自治体や厚生労働省の公式発表をご確認ください。
就労選択支援について(厚生労働省)