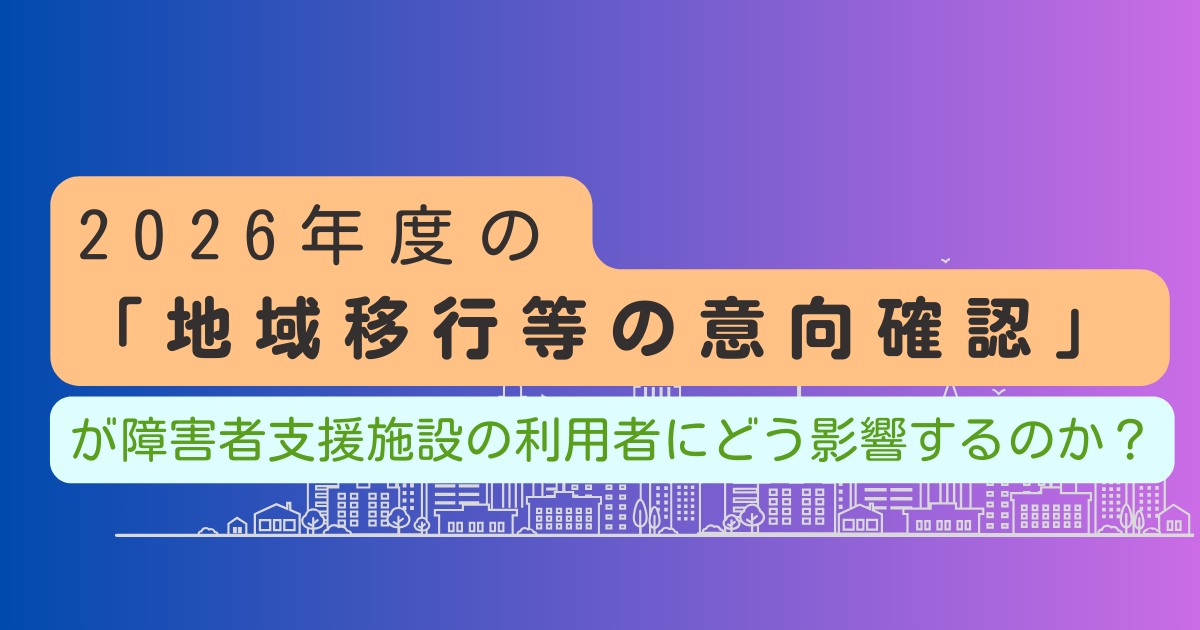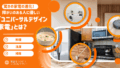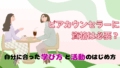今回は、2026年度から義務化される「地域移行等の意向確認」について、支援施設にどんな影響があるのか、そして利用者にとってどのように支援が変わるのかについて詳しくお話ししたいと思います。
障害者施設入所者の意向確認 厚労省がマニュアル作成(福祉新聞)
そこでは、厚生労働省が新たに発表した
「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」
が重要なポイントになります。
本記事でこれからの支援がどう変わるのかを知っておくことで、皆さんの生活がより良い方向に進むための一歩を踏み出せると思います。
地域移行に関する意向確認が義務化される背景
2026年度から、地域移行に関する意向確認が障害者支援施設に対して義務化されることが決まりました。これにより、施設入所者の地域移行に向けた意思や希望がきちんと確認され、その意向を尊重した支援が提供されることが求められます。
具体的には、担当者の選任、指針の作成、そして個別支援計画への反映が義務づけられます。これによって、施設の支援がより個別化され、利用者一人ひとりの希望に合った生活支援が行われるようになります。

(写真 K)
どんなことが義務化されるのか?
- 担当者の選任:地域移行の意向確認を行うため、各施設には担当者が選任され、その担当者が利用者の意向を確認し、支援計画に反映させる責任を負います。
- 指針の作成:施設は、地域移行に関する支援の方法や方針を定めた指針を作成し、それに基づいて支援を行います。この指針は利用者のニーズに合わせて、柔軟に対応できる内容が求められます。
- 個別支援計画への反映:地域移行に関する意向確認の結果を基に、利用者一人ひとりの個別支援計画を更新します。これにより、利用者がどのような支援を受けるべきかが明確になり、地域での生活に向けたステップを踏みやすくなります。
地域移行支援が利用者に与える影響
これまで、地域移行に関する意向確認は必ずしも全施設で行われているわけではなく、そのため支援が偏っている場合もありました。しかし、義務化されることにより、以下のような利用者への具体的な影響が予想されます。
地域移行を希望する利用者の支援が強化される
地域移行を希望する利用者は、自立した生活を目指して様々な支援を必要とします。例えば、地域で生活するための住まいの確保や生活スキルの習得、地域で働くための職業訓練などが必要です。これらはすべて個別支援計画に基づいて、支援者が適切に提供することになります。
意向確認を通じて個別支援が実現
これからは、利用者の希望や意向がより正確に反映された支援が提供されることになります。例えば、「地域で生活したい」と考えている利用者には、そのために必要な支援(住居の確保、生活スキルのトレーニング、就職支援など)が手厚く行われ、支援の質が向上することが期待されます。
「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」の活用
厚生労働省は、「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」(28ページ)を作成し、ウェブサイトで公開しています。このマニュアルは、地域移行に向けた意向確認を支援するための重要な資料です。
マニュアルの主な内容
- 意向確認の手順
地域移行の意向確認を行う際の基本的な流れや、どのように情報を収集し、利用者の希望を反映させるかが具体的に示されています。これにより、支援者が迷うことなく適切な支援を行えるようになります。 - 個別支援計画への反映方法
利用者の意向確認の結果をどのように個別支援計画に反映させるか、計画書の記入方法や内容が解説されています。これにより、支援計画がより利用者のニーズに即したものになります。 - 支援者の役割と責任
支援者が地域移行に向けてどのような支援を行うべきか、また、意向確認を通じて利用者に対してどのようにサポートを提供するかが説明されています。
利用者にとってのメリット
この義務化によって、利用者一人ひとりが希望する生活に向けて確実にサポートを受けられるようになります。そこでは、地域移行支援加算や意向確認の実施が支援計画にきちんと反映されるため、以下のようなメリットが考えられます。
- 地域での生活への移行がスムーズに
施設での生活から地域での自立した生活へ移行するために必要な支援が計画的に行われます。住居探しや生活支援、就労支援などがスムーズに進み、安心して地域での生活を始めることができます。 - 支援が個別化される
各利用者の希望に合わせた支援が行われるため、無理なく自立に向けて進むことができます。例えば、就職を希望する場合には、適切な職業訓練や就職支援が行われます。 - 地域社会とのつながりが強化される
地域移行に向けた意向確認や支援が進むことで、地域社会とのつながりが深まり、利用者はより自立した生活を送れるようになります。
想定されるデメリット・課題
一方で、この義務化には課題や注意点もあります。支援の仕組みが整うことで前向きな効果が期待できる反面、実際の運用や環境によっては利用者や施設側に負担が生じることも少なくありません。ここでは、想定されるデメリットや現場で起こり得る課題について整理します。
- 利用者の負担感
意向確認が形式的に繰り返されると、「毎回聞かれてしんどい」「本音を言いづらい」と感じる人も出てくる可能性があります。 - 希望がすぐ実現するわけではない
住まいの確保や就労の場など、地域の資源が不足している場合は、希望を支援計画に書いても実現に時間がかかることがあります。 - 施設側の負担増
新たに担当者を配置し、計画を更新する事務作業が発生します。支援員の負担が増え、人員不足の施設では実施に苦労することも予想されます。 - 地域格差
サービスや支援体制が整っている都市部と、選択肢が限られる地域では、意向を実際の支援につなげる難易度に差が出ることも懸念されます。
まとめ
2026年度からの「地域移行等の意向確認」の義務化は、利用者の希望を尊重し、自立を支援する重要な制度改革です。

(写真 K)
一方で、支援体制や地域資源の不足によって「希望は確認されたが実現できない」という事態も起こり得ます。制度の導入はゴールではなく、支援の実効性をどう高めるかが今後の課題です。
利用者としては、自分の希望を正直に伝えることが第一歩。支援者としては、マニュアルを活かし、形式的にならない本当の意向確認を目指すことが大切です。