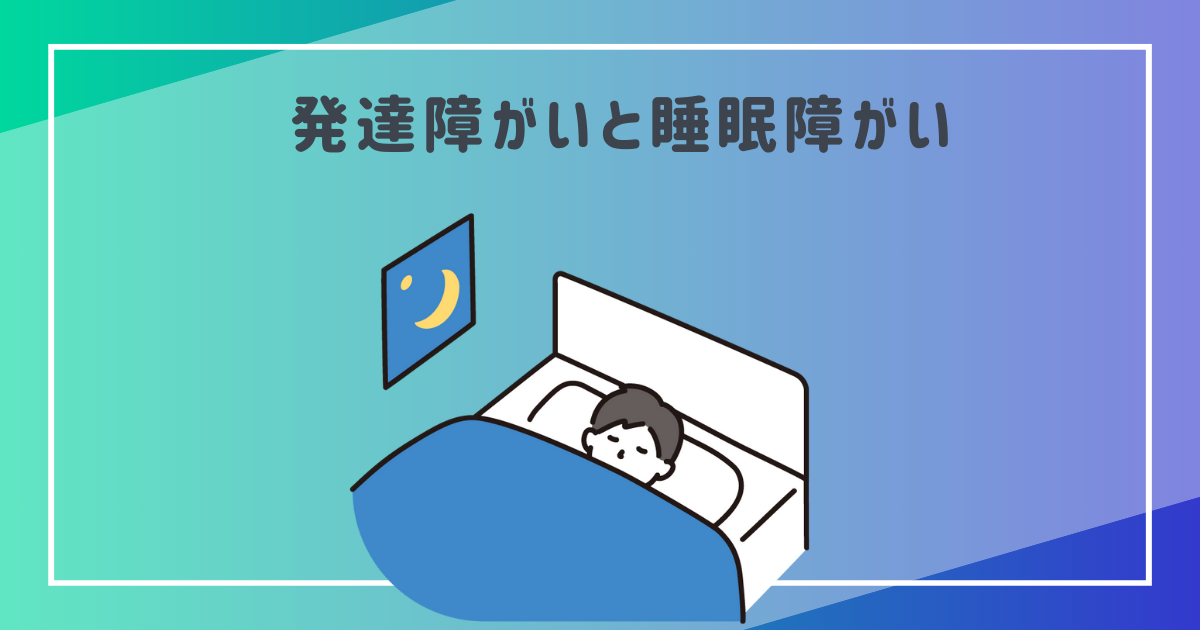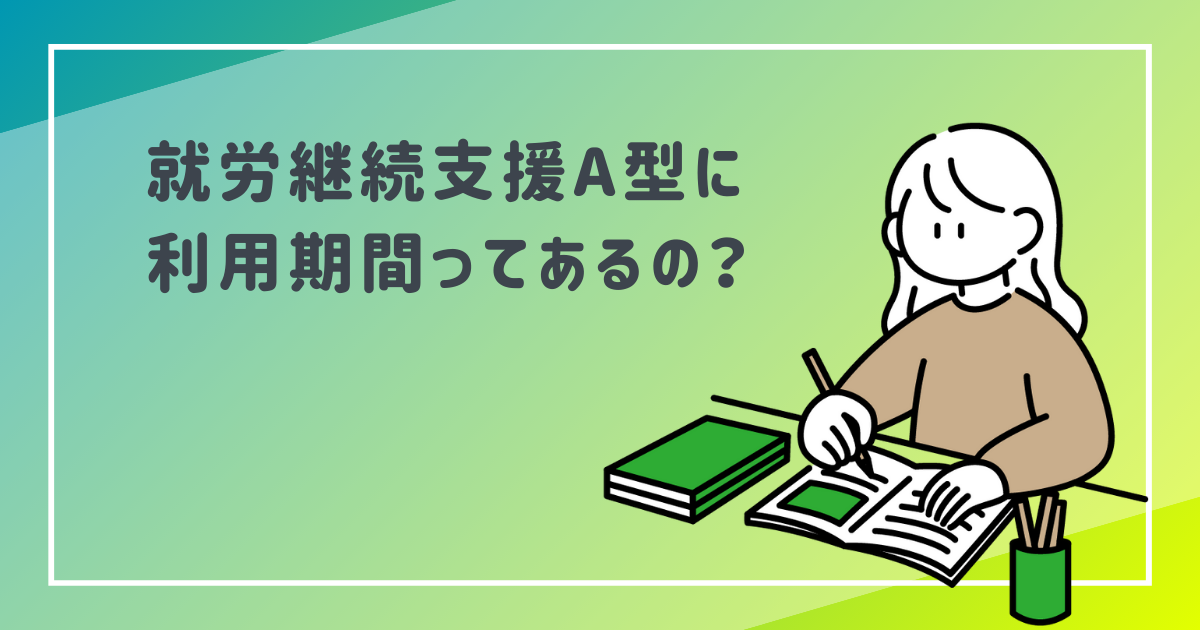発達障がいのある人で、眠気や睡眠に関する困りごとを抱えている人は多いのではないでしょうか?
本記事では、睡眠障がいについて解説します。
こころの病気と睡眠障がいは併存しやすい

一般的にこころの病気がある人は睡眠障がいを併存している割合が高いとされています。
こころの病気の特性と睡眠障害の両方があることで、生活や仕事などでの困りごとが増えたり深まったりするかもしれません。
特に発達障害と睡眠障がいの併存については、発達障害の特性には睡眠を含む生活全般のリズムが乱れやすいという側面があります。
またADHDやASD、睡眠障害は神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンという覚醒状態を維持するためにも必要な物質と関連があるとも考えられます。
ADHDやASDではこれらの物質の分泌量が調整不十分または機能不全により低下しているとされています。
このように発達特性に伴う生活リズムの乱れと睡眠と覚醒を調性する能の中枢神経における機能不全が相まって、発達障害と睡眠障害が併存しやすいのではないかと考えられています。
睡眠障害の種類
睡眠障害とは睡眠に関連する様々な病気の総称で、不眠症・過眠症・睡眠リズム障害などが含まれます。
- 不眠症
寝つきが悪い、眠りが浅い、睡眠を保てない(睡眠中に目が覚める)朝早く目が覚める、などといった不眠の状態が続き、日中に眠気や疲れといった不調が表れる病気です。 - 過眠症(中枢性過眠症)
睡眠を妨げる病気がなく、夜間に眠っているにもかかわらず日中に強い眠気を感じる病気で、ナルコレプシー、突発性過眠症などに細分されます。 - 睡眠リズム障害
体内時計を調節できず睡眠と覚醒のリズムが乱れてしまい、寝つきが悪くなったり日中に眠気を感じる病気です。 - その他
睡眠関連呼吸障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害など
発達障がいがある人の眠気の特徴

発達障害の人では幼少期から日中に強い眠気を感じる人が多いとされています。
また、小児期には特に問題に至らなかったものの思春期以降に支障が出始めたという人もいるでしょう。
発達障害と睡眠障害の両方があると、興味・関心のあることにこだわる・集中するという特性から夜遅くまで続けてしまい寝つきがより悪くなったり、あるいは興味・関心のない授業や仕事に退屈してしまうことでより眠気を感じやすくなったりします。
睡眠障害への対処法
睡眠障害の種類や程度、困りごとは人それぞれです。
そのため対処法においても普段の生活を見直したり便利なアイテムを用いたり自分に合った対処法を探して実践することが重要です。
毎日何時に入眠・起床しているか、夜間に目が覚めるか、日中に眠気があるかどうかなどを把握することは生活習慣改善・睡眠時間調整のきっかけになります。
ご自身でノートなどに記録するほか、睡眠の記録をとることが出来るアイテムを用いることもいいと思います。
それでも治らなかったら精神科に受診してみるといいかもしれません。
まとめ
- こころの病気と睡眠障がいは併存しやすく、特に発達障がいは睡眠のリズムが乱れやすい。
- 睡眠障がいには、不眠症・過眠症・睡眠リズム障がいなどがある。
- 発達障がいがあると、夜間の過集中による夜更かしや、興味・関心のない事に退屈してしまうことが原因で日中でも眠気を感じやすい。
- 睡眠障がいには、自分に合った方法で対処するのが良い。
- どうしても改善しない場合には精神科に受診することも選択肢の1つである。
眠りと向き合うのはつらいですよね。
お一人で悩まずに、専門家に受診してみるのも一つの方法だと思います。

あなたが安眠出来ますように。