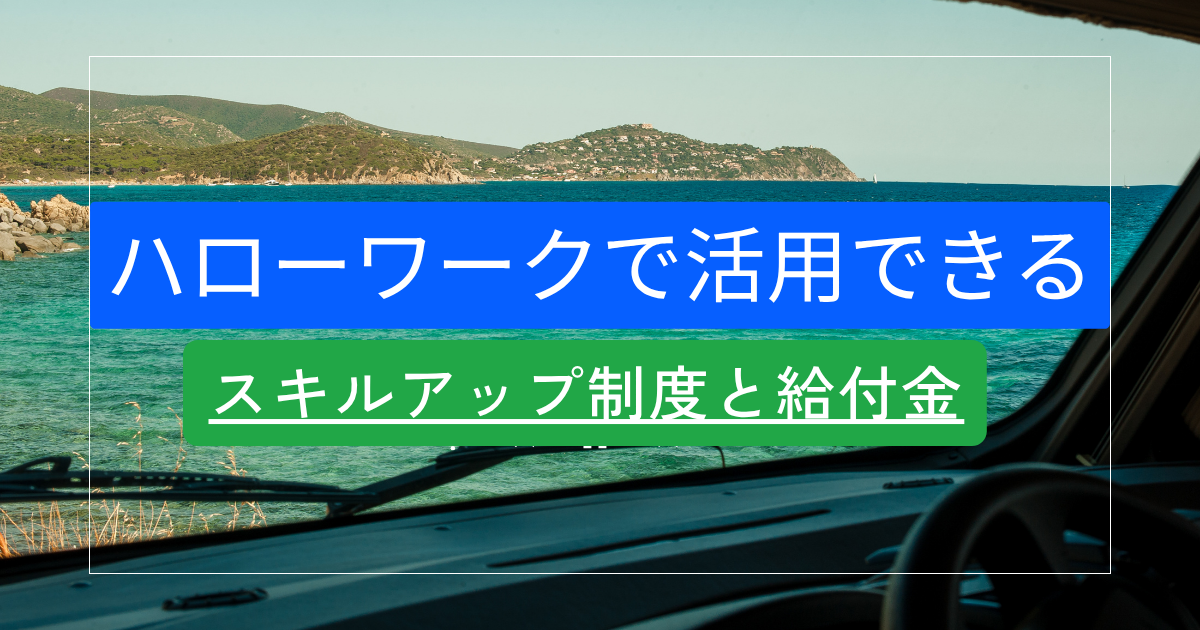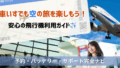A型事業所は、業務にまだ慣れていない方や就職経験が少ない方にとって、一般就労に向けた準備の場になります。しかし、いざ「もっとスキルを身につけたい」と思っても、費用や生活面の不安から一歩踏み出せないことも少なくありません。そこで頼れるのが、ハローワークを通じて利用できる「スキルアップ制度と給付金」の各種制度です。
特に、就労継続支援A型は、雇用契約があるゆえに、条件を満たせば 雇用保険にも加入 できるため、万が一のときにも公的なセーフティネットが働きます。このように、雇用と保障の両面を備えたA型サービスは、働きたいと願う方にとって「使わない手はない」支援制度がいくつかあります。
特に注目したいのは、次の4つです。
- 教育訓練給付金(雇用保険加入者が対象)
- 公共職業訓練(離職者訓練)受講中の失業手当(雇用保険加入者が対象)
- 求職者支援訓練給付金(雇用保険未加入者も対象)
- 教育訓練休暇給付金(雇用保険加入者向け・2025年10月1日施行)
これらの制度を活用すれば、業務未経験者でも、費用や生活の不安を軽減しながら、一般就労に必要なスキルを体系的に学ぶことが可能です。
教育訓練給付金
対象者
- 雇用保険に一定期間加入している方
- 一般教育訓練:通算1年以上
- 専門実践教育訓練:通算2年以上
- 一般教育訓練:通算1年以上
内容
- 資格取得やスキルアップのための講座費用の一部を給付
- 支給率や上限額は講座内容により異なるが、数万円~最大100万円以上も支給される場合がある
- 対象講座は幅広く、PCスキル、事務スキル、接客、介護など、業務未経験者でも取り組みやすい内容が多い
活用のポイント
- 訓練費用を自己負担する前にハローワークで相談すると安心
- 訓練の終了後、修了証明書を提出することで給付金が支給される
- 業務未経験者は、まず基礎スキルを習得できる講座から始めると、一般就労へのステップがスムーズ
- 雇用保険に加入していれば、生活費の補助があることで、学習に専念できる
制度の背景
教育訓練給付金制度は、国が「働く人のスキルアップを支援する」という目的で設けた制度です。特に、正社員やフルタイムの経験が少ない方でも、自己負担を抑えつつ資格や技能を身につけられる仕組みになっています。昨今の労働市場では、基礎スキルや資格が就職の条件になることも多く、この制度を活用することで、就職活動時の競争力を大幅に高められます。
公共職業訓練(離職者訓練)受講中の失業手当
対象者
- 雇用保険加入者で、失業中の方
- 就職に必要なスキルを学びたい方
内容
- ハローワークが提供する公共職業訓練を受講しながら、失業手当を受給可能
- 訓練内容は、PC操作、事務スキル、接客、介護など、業務未経験者でも基礎から学べる内容が多い
- 訓練中も生活費を確保できるため、学習に専念できる
注意点
- 「自己都合退職」の場合でも、訓練受講により給付制限が緩和されるケースあり
- 失業手当の待期期間(通常7日間)や、給付制限は離職理由によって異なる
- 訓練に参加する場合は、事前にハローワークでスケジュールや受給条件を確認すること
制度の背景
公共職業訓練は、国と自治体が連携して、労働市場で必要とされる人材を育成するために行っています。特に業務未経験者や離職直後の方にとっては、職場に直接入る前に基礎スキルを習得できる貴重な機会です。失業手当を受けながら訓練を受けられるため、生活費の不安を抱えずに集中して学べます。
活用のポイント
- 受講期間中も就職活動が可能
- 訓練終了後、ハローワークが就職支援を行ってくれる
- 訓練内容を履歴書や職務経歴書に書くことで、応募時のアピール材料になる
- 早めに訓練計画を立てることで、希望の分野・講座に確実に参加できる
求職者支援訓練給付金
対象者
- 雇用保険に加入していない方でも利用可能
- 仕事を探したい、スキルを身につけたいと考える方
内容
- 訓練受講中に「生活支援のための給付金」が支給される
- 訓練費用は原則無料
- 交通費やテキスト代も補助される場合がある
- 訓練後はハローワークによる就職支援も受けられる
活用のポイント
- 訓練は、PC操作や事務、接客、介護など、一般就労に直結する内容が多く、業務未経験者でも安心して学べる
- 訓練で得たスキルを活かし、就職活動の際のアピールポイントにできる
- 訓練を通じて、業務に必要なマナーやコミュニケーション力を身につけられる
制度の背景
求職者支援訓練給付金制度は、雇用保険に加入していない求職者やフリーター、離職経験の少ない方を対象に、スキルアップと就職を支援するために設けられた制度です。訓練費用の負担がなく、さらに生活支援も受けられるため、経済的に不安がある方でも安心して受講可能です。社会的にも、業務未経験者が安定した職に就くことを後押しする重要な制度となっています。
教育訓練休暇給付金(雇用保険加入者向け・2025年10月1日施行)
この制度は新しく、2025年10月1日から施行された支援制度です。
対象者
雇用保険の「一般被保険者」で、かつ次のような要件を満たす方。
- 休暇開始前の2年間に、12か月以上の賃金支払いの基礎となる日数を有すること。
- 休暇開始前に、雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
- 就業規則等に基づく社内制度により、教育訓練を受けるための30日以上の連続した無給休暇を取得していること。
内容
労働者が離職せずに教育訓練に専念するため、自発的な無給休暇を取得した場合に、 離職した場合に支給される基本手当(失業手当)相当額が給付される制度です。
給付日数は、被保険者期間に応じて「90日/120日/150日」のいずれかとなっています。
活用のポイント
- 「無給休暇を取得できるか」「社内制度(就業規則や労働協約)にその制度があるか」をまず確認しましょう。
- 休暇取得のためには、業務命令ではなく「自己の意思で」「教育訓練を目的として」休暇を取得する必要があります。
- 事業主側にも整備・協力の義務があります。就業規則の改定や届出・確認書類の対応が必要です。
- 一歩踏み出して、スキルアップに専念できる環境を整えるための制度として、ぜひハローワーク等で相談してみることをおすすめします。
- A型事業所での勤務経験や雇用保険加入状況を活かして、「教育訓練休暇給付金」を視野に入れると、より安心してスキルアップに取り組めます。
制度の背景
厚生労働省では、誰もが安心して教育訓練に取り組める環境づくりを進めるため、無給休暇中の生活面を支える新たな仕組みとして本制度を創設しました。これにより、働く人が自分の意思でまとまった休暇を取得し、専門学校・大学・職業訓練などの本格的な学習に専念できるようになります。
制度を最大限活かすためのポイント
- まずはハローワークで相談
- 自分がどの制度の対象になるか、給付金や訓練条件を確認する
- A型事業所の勤務状況も考慮して、最適な制度を選択
- 自分がどの制度の対象になるか、給付金や訓練条件を確認する
- 自分に合った訓練を選ぶ
- 業務未経験者は、PC・事務・接客・介護など、一般就労に直結する講座がおすすめ
- 訓練の難易度や期間を確認し、無理なく受講できる講座を選ぶ
- 業務未経験者は、PC・事務・接客・介護など、一般就労に直結する講座がおすすめ
- 生活と学習を両立
- 各種給付金を活用すれば、費用や生活面の不安を減らせる
- 訓練に通いながら、自宅で復習や課題に取り組むことで、学習効果を高められる
- 各種給付金を活用すれば、費用や生活面の不安を減らせる
- 訓練後の就職も視野に
- 訓練で得たスキルは職務経歴書や面接でアピール可能
- ハローワークの就職支援も活用して、安心して次のステップに進める
- 訓練で得たスキルは職務経歴書や面接でアピール可能
- 将来を見据えたスキル計画を立てる
- まずは基礎スキルを習得し、その後に専門スキルや資格取得に挑戦する
- 労働市場で需要のあるスキルを選ぶと、就職の幅が広がる
- まずは基礎スキルを習得し、その後に専門スキルや資格取得に挑戦する
まとめ
- 教育訓練給付金:雇用保険加入者が資格取得やスキルアップに活用できる
- 公共職業訓練受講中の失業手当:失業中でも訓練を受けながら生活費を確保できる
- 求職者支援訓練給付金:雇用保険未加入者でも訓練費・生活費をサポート
- 教育訓練休暇給付金:雇用保険加入中の方が、無給の休暇を取得して教育訓練に専念できるよう、2025年10月から使える制度。
事業所利用者にとって、就労移行支援を経ての一般就労や、A型事業所での雇用経験を活かした就職以外でも、ハローワークの制度を活用すれば、安心して学び、将来に向けてステップを踏むことができます。特に、基礎スキルから始めて徐々に専門スキルや資格取得に進むことで、一般就労への道が大きく開けます。もちろん、こうした道は「一つの選択肢」に過ぎません。自分の状況や希望に合わせて、最適なステップを選ぶことが大切です。
※本記事の情報は執筆時点の内容です。給付額や対象条件は講座や自治体によって異なります。また、教育訓練休暇給付金を利用する場合は、会社側の就業規則等の整備が必要です。最新情報はハローワークでご確認ください。
参考サイト
教育訓練給付金 – ハローワークインターネットサービス
ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)
教育訓練休暇給付金(令和7年10月1日施行)