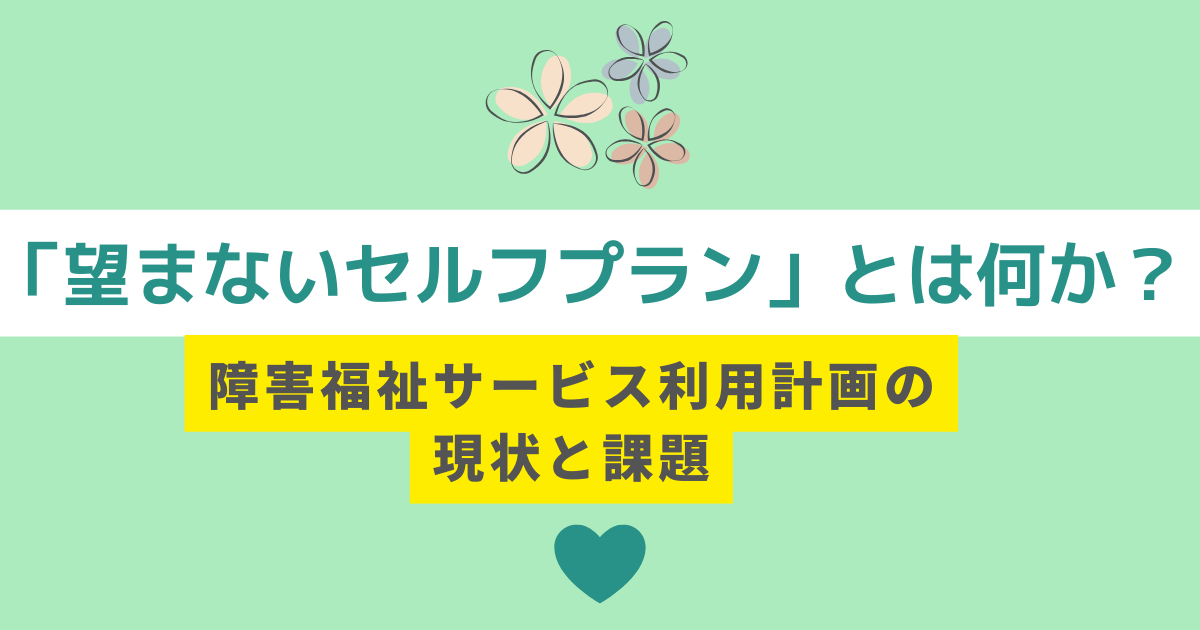◆厚労省が動き出した「望まないセルフプラン」問題
2025年10月1日、厚生労働省は社会保障審議会・障害者部会で、「望まないセルフプラン」に関する懸念を正式に表明しました。
厚労省、障害福祉の「望まないセルフプラン」解消へ 相談支援体制の強化を検討
「本人や家族が本意ではなく、やむを得ずセルフプランを選んでいるケースがある」
「全国の自治体に対し、改善に向けた取り組みを促していく」
今回は、「望まないセルフプラン」が何を意味するのか、どうして起こるのか、また今後の制度の課題や改善の方向性について解説したいと思います。
「セルフプラン」とは?
まず前提として、障害福祉サービスを利用するためには「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」というものを作る必要があります。これはサービス利用にあたっての「設計図」のようなもので、どんなサービスをどのくらい、どのタイミングで使うかをまとめるものです。
通常、この計画は「相談支援事業所」という専門機関が作成します。相談支援事業所には、特定相談支援事業者や障害児相談支援事業者などがあります。彼らは専門の相談支援員がいて、利用者一人ひとりの状況やニーズを丁寧に聞き取り、最適なプランを作り、サービス提供事業者と調整しながら計画を管理します。

(写真 Canva)
しかし、地域によっては相談支援事業所が少なかったり、サービスが単純だったり、利用者や家族が自分で計画を作りたいと希望したりする場合があります。そうしたときに、自分たちで計画を作成して提出することが認められているのが「セルフプラン」です。
セルフプランは、以下のような場合に認められることが多いです。
- 相談支援事業所が近くにない、もしくは利用が難しい場合
- 本人や家族が自分で計画を作成したいと希望している場合
- 利用するサービスが単純で、複雑な調整が不要な場合
参考サイト:【障害福祉】セルフプラン利用の流れとサービス事業所がすべきことを解説
「望まないセルフプラン」とは?
「望まないセルフプラン」とは何でしょうか? それは、利用者や家族が本当は相談支援事業所の専門的な支援を受けたいのに、事情や制度の不備などで仕方なくセルフプランを選ばざるを得ない状況のことを指します。
望まないセルフプランが生まれる例
| ケース | 状況 | なぜ「望まない」となるか |
| 地域に相談支援事業所がない | 近隣に専門の相談支援事業所が存在せず、交通の便も悪い | 利用者は相談支援を受ける選択肢がなく、セルフプランを選ばざるを得ない |
| 相談支援体制が脆弱・人手不足 | 相談支援専門員が不足し、受け入れ態勢が整っていない | 予約が取れず、専門支援を受けられないためセルフプランに誘導される |
| 説明や情報提供が不十分 | 申請段階でセルフプランが「簡単」と説明され、相談支援のメリットが伝わらない | 本来選択肢があっても知らされず、セルフプランを使わされた感覚が生まれる |
| 相談支援事業所が計画作成依頼を断る | 定員オーバーや事業所方針で受け入れ拒否される | 他に選択肢がなく、セルフプランに強制される |
| 事業所間連携ができない | サービス間のスケジュール調整が困難で調整支援が得られない | 利用者が希望のサービスを使いこなせず、プランが形骸化する |
このような状況で、本人や家族は「専門家の助けが欲しい」「第三者の目線での調整をしてほしい」と切実に願っていても、現実にはセルフプランを選ばざるを得ない。これが「望まないセルフプラン」です。
現行制度・運用の課題
なぜこうした問題が生まれてしまうのか? 私自身が感じ、また調べた現行の制度や運用の課題を整理してみました。
相談支援体制の不足・地域格差の大きさ
- 相談支援専門員が慢性的に不足し、一人あたりの担当件数が過多。過重労働により十分な支援が難しい。
- 地域によって相談支援事業所や専門性に大きな差があり、都市部に比べて過疎地や地方では相談支援を受けにくい。
- 委託方式で相談支援事業所が少なく、または一部地域で全く存在しないこともある。
制度的インセンティブや報酬面の制約
- 相談支援におけるモニタリングや調整支援への報酬が低く、事業者が十分な支援を提供しにくい。
- セルフプラン利用者には報酬加算がつかず、事業者が積極的に支援しづらい制度設計になっている場合がある。
- 制度改正のたびにセルフプラン対応の加算や補助が後手に回るケースもある。
モニタリングやフォローアップの欠如
- セルフプランを選んだ利用者に対しては、定期的な見直しやモニタリングがほぼ実施されないか、限定的。
- そのため、計画が現実的に機能しているか、利用者の意向が反映されているかの検証ができず、サービス利用の質の担保が難しい。
選択・説明・意思確認の不徹底
- 利用申請時にセルフプランを推奨するような説明が優先され、相談支援との違いやメリットが十分に伝えられない。
- 利用者・家族の意思確認が曖昧で、実質的に「選択の自由」が保障されていない場合も報告されている。
- 地方自治体によっては「セルフプランを作ってきなさい」といった指示的な対応が行われ、利用者が選択権を失うケースも。
調整支援機能の制限
- セルフプランではサービス間の調整支援が行われず、スケジュール調整やサービスの組み合わせの最適化が困難。
- その結果、利用者が希望するサービスを最大限に活用できず、計画の柔軟な変更や追加も制約されがち。
制度運用の過度な負荷
- 相談支援事業所は計画作成に忙殺され、日常の相談支援や地域連携に十分に手が回らない。
- 数値目標や計画作成件数の優先が質の向上を妨げる場合もある。
「望まないセルフプラン」をなくすための制度改善の方向性
「望まないセルフプラン」という言葉には、制度のはざまで支援を十分に受けられず、不本意な選択を強いられている当事者や家族の苦しさがにじんでいます。本来、障害福祉サービスはその人らしい暮らしを支えるためにあるはずなのに、現実には制度や地域の支援体制の不備によって、その入り口でつまずいてしまうケースが少なくありません。

(写真 Canva)
私自身、この問題について考える中で、単に「数を増やす」や「効率化する」といった対症療法ではなく、もっと根本的に制度のあり方を見直す必要があると感じています。相談支援の体制整備、制度的なインセンティブの改善、情報提供のあり方、地域間格差の是正、そして利用者が本当に納得して選べる仕組みから、いくつかの改善策を提案したいと思います。
相談支援体制の強化・拡充
- 相談支援専門員の増員と研修充実により、支援の質と量を両面で強化することが不可欠です。
- 過疎地や支援体制が不十分な地域には、新たな拠点設置支援やICTを活用した遠隔相談体制の構築が望まれます。
- 相談支援事業所同士の連携で負担を分散し、安定した支援提供体制の構築も重要です。
制度的インセンティブ・報酬体系の見直し
- セルフプラン利用者にもモニタリングや調整支援がしっかり提供できるよう、報酬制度の整備が必要です。
- 事業所間連携加算や訪問支援加算の対象拡大、地域間格差解消のための財政支援強化も進めてほしいポイントです。
計画の実効性担保と調査強化
- セルフプラン利用者に対しても、定期的な計画見直しや進捗確認の義務化が必要です。
- 自治体による実態調査や利用者満足度調査を強化し、サービス向上につなげていくべきです。
説明の透明性向上と利用者の主体的選択支援
- 相談支援とセルフプランの違いやメリット・デメリットをわかりやすく説明することが重要です。
- 選択過程の記録や意思確認の手続きをしっかり行い、利用者が主体的に選択できる体制を整備すべきです。
サービス間調整支援の提供とICT活用
- セルフプラン利用者にもサービス間の調整支援を一部提供し、サービスの質を向上させることが必要です。
- ネットワーク型の連携やICTの活用による情報共有も効果的です。
ハイブリッド型プランの導入
- 利用者の状況や希望に応じて、セルフプランと相談支援を組み合わせた柔軟なプラン作成を認める制度の導入が望ましいです。
- 特に初めてサービスを利用する方には、相談支援からのスタートができる仕組みを整備することが重要です。
地域ごとの状況把握と目標設定
- 自治体ごとにセルフプラン利用状況や「望まないセルフプラン」の発生状況を把握し、課題解消の目標を設定することが必要です。
- 利用者団体や関係機関を巻き込んだ地域協議会で意見を反映し、地域に合った運用改善と情報公開を進めていくべきだと考えます。
まとめ
この問題は単に制度の不備だけでなく、相談支援体制の不足や利用者への十分な情報提供がなされていないこと、さらには地域ごとの環境や支援体制の差異など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じています。そのため、単一の対策だけで解決することは難しく、多面的な取り組みが求められています。
また、利用者自身の声や経験は、制度改善において非常に重要な役割を果たします。利用者の実態やニーズを丁寧に把握し、それを政策や運用に反映させていくことが、真に利用者本位の支援体制を築く鍵となるからです。地域の利用者団体や関係機関が協力し合い、現場の課題を共有しながら改善策を検討していくことも、今後ますます重要になってくるでしょう。
関連記事
【2025年10月より開始】「就労選択支援」って何?やる意味はあるのか?
2025年10月から新たにスタートする「就労選択支援」制度について詳しく解説。そもそもどんな制度なのか、導入の背景や目的、企業や利用者にとってのメリット・デメリットまでわかりやすくまとめています。制度の全体像をおさえたい方は必見です。
【2026年度より実施】「地域移行等の意向確認」が障害者支援施設の利用者にどう影響するのか?
2026年度から本格的に始まる「地域移行等の意向確認」。障害者支援施設の利用者に対してどのような変化や影響があるのか、制度の背景や国の狙い、現場の課題とともに丁寧に解説します。今後の対応を考えるうえで知っておきたいポイントをまとめました。