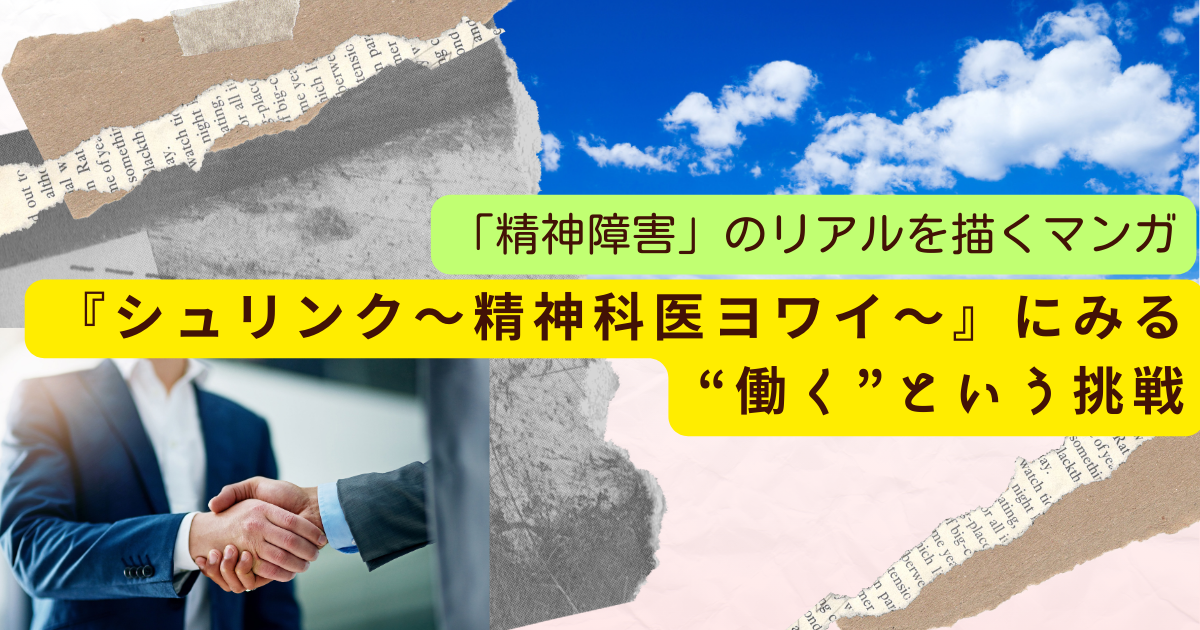こんにちは。就労継続支援A型事業所で働いているKです。
今回は、精神障害者の「働く」ことをテーマに、実際の福祉現場の視点と、マンガ『Shrink(シュリンク)~精神科医ヨワイ~』第8巻(精神障害者雇用編)で描かれたリアルな職場の葛藤を重ねながら考えていきたいと思います。
マンガ『Shrink~精神科医ヨワイ~』とは?
『Shrink~精神科医ヨワイ~』(原作:七海仁/作画:月子)は、精神科医・弱井幸之助を中心に、さまざまな精神障害とその背景にある“生活・社会・偏見”を描く医療×社会派ヒューマンドラマです。2019年から『グランドジャンプ』(集英社)で連載中で、2025年9月現在、既刊16巻。2024年にはNHKで実写ドラマ化もされ、話題になりました。
本作品は、単に病名を描くのではなく、その背後にある家庭環境や仕事、社会的ストレスまで丁寧に描写している点が特徴です。医療の視点にとどまらず、社会制度や雇用、人間関係など幅広い要素を取り上げ、精神障害にまつわる偏見やスティグマに真正面から挑む構成となっています。
第8巻のテーマ:精神障害者の就労と職場のリアル
第8巻では、精神障害者の職場復帰/障害者雇用枠の現実が中心テーマ。これは福祉現場で働く私にとっても、極めて現実的で、切実なテーマです。
8巻の主人公:夕霧 昇の挑戦
うつ病を発症して離職し、数年引きこもっていた夕霧昇。
彼は就労継続支援を通じて、障害者雇用枠で復職を目指します。
しかしその先には、理想と現実のギャップが待ち受けていました。
- どこまで自分の特性を伝えるべきか?
- 配慮されすぎると「仕事を任せてもらえない」ことにもなる
- 周囲との距離感や、雇用者側の“よかれと思った”対応のズレ
…まさに、現場でよく起こる問題が、リアルに描かれています。
配慮=甘やかしではない。「対等な関係」を築く難しさ
作中で特に印象に残るセリフのひとつに、弱井医師のこの言葉があります。
「皆さんは一方的に守られる存在ではいられないんです」(8巻 P119)
このセリフには、精神障害のある人たちに対して、“ただ配慮されるだけ”では本当の意味での共生にはならない、という重要な視点が込められています。
つまり、配慮される側にも「自分のことを伝える力」や「助けを求める勇気」が必要であり、その両者の歩み寄りによって初めて対等な関係性が築かれるのです。
物語の中では、主人公・昇もまた、自身の苦手なことや不安を少しずつ口にするようになります。それは決して弱さではなく、自分自身と向き合い、他者との関係を築こうとする“強さ”の表れです。
この描写は、福祉や教育などの現場でも重視されている「合理的配慮」の考え方と深くつながっています。合理的配慮とは、障害のある人が他の人と同じように生活や学び、働くために必要な環境調整を行うことですが、それは一方的な支援ではなく、本人の自己表現と周囲の理解があって初めて成り立つものです。
雇用する側の“苦悩”も丁寧に描く
昇を障害者雇用として迎え入れた企業の上司・朝比奈課長の葛藤も、作品の中で非常にリアルに描かれています。
彼は「配慮や支援が必要だ」と言われても、具体的にどのように接すればいいのか分からないという戸惑いを抱えています。また、周囲の社員からは、「昇だけが特別扱いされているのではないか」という不満や違和感の声も上がり、配慮の必要性と現場の空気の間で板挟みになる姿が印象的です。
このエピソードは、精神障害者の雇用において、雇用する側=企業や現場の管理職に対しても、具体的で実効性のある支援や情報提供が不可欠であるということを、非常に説得力のある形で伝えています。障害者雇用は、当事者だけでなく、周囲の理解と準備があってこそ機能する。
その現実を、本作は丁寧に描き出しているのです。
精神障害者雇用の制度的背景と現実
精神障害者の就労は、法律的には「障害者雇用促進法」に基づき、一定の法定雇用率が企業に課されています。2024年時点では、従業員43.5人以上の企業に対し、2.5%以上の障害者を雇用する義務があります。
しかし現場では…
- 精神障害は「見えにくい」ため配慮が難しい
- 本人も配慮を求めにくい(言語化が困難)
- 定着率が低い(厚労省調査では1年後定着率は50〜60%台)
- 配属先の理解不足や業務調整の困難さ
などが障壁になります。
作中では、助成金を得るのみの雇用を行っている、とある企業の実態が描かれています。
こうした内部の葛藤を描きながら、登場人物たちはそれぞれ異なる価値観を持ちつつも、自身の本来の目的や社会的責任に気づき、成長していくのです。
支援現場で実感する「現実」と『Shrink』の価値
当事者として感じるのは、制度はあるが“つなぎ”が弱いことです。
就労支援を利用しても、企業側が本当に理解していないと、本人の努力だけでは続きません。それは、実際にリアルな数字として現れています。また、職場に「メンタル不調者が働く経験」が蓄積されないと、同じ失敗が繰り返されてしまいます。
だからこそ、この作品のように――
- 雇う側・雇われる側の両方を描き
- 配慮のあり方を考え
- 「働く」とは何かを問いかける
そして、どちらも変わっていかなければならないという視点を持つことが重要なのです。
読後に残る問い
『Shrink~精神科医ヨワイ~』第8巻を読み終えて、心に深く残ったのは、いくつもの問いでした。
「働ける」とは、一体誰が決めるのか?
医師や企業、人事担当者なのか、それとも本人自身なのか――その判断の基準は本当に公平で、正確なものなのか。
本当に必要な配慮とは、どこまでを指すのか?
どこまでが「合理的配慮」で、どこからが「特別扱い」と受け取られてしまうのか。配慮する側・される側の間に生じる温度差は、どう乗り越えられるのか。
制度と現場の“ねじれ”は、果たして解消できるのか?
法律や方針が整っていても、現場では戸惑いや誤解が生まれやすく、支援がうまく機能しないことも多いのが現実です。
こうした問いに対して、すぐに明確な答えを出すことは難しいのかもしれません。しかし、だからこそ、問い続けること自体が大切なのではないかと思わされます。
支援する立場の人々にも、雇用する企業にも、そして社会全体にも、「考え続ける責任」がある。
作品を通じて、そんなメッセージを強く感じました。
まとめ:制度・支援・人間関係を見つめ直す一冊
『Shrink~精神科医ヨワイ~』第8巻は、精神障害者の就労というセンシティブかつ重要なテーマに真正面から向き合っています。
支援現場で働く立場から見ても、その描写の正確さ・誠実さに驚きました。

(写真 Canva)
「働きたいけど、不安がある」
「支援したいけど、どう接すればいいか分からない」
「職場で困っている人を見て、何かできないか考えている」
…そんな人にこそ、ぜひ読んでほしい一冊です。
『Shrink~精神科医ヨワイ~』は全巻にわたって心の問題と向き合う人々の姿を描いています。例えば、第1巻では、精神科医としての弱井の人間性やパニック障害の患者との関わりが描かれ、シリーズ全体の基盤が築かれています。また、第4~5巻では、パーソナリティ障害を抱える患者との関わりを通じて、心の病と家族や他者との関わり方が丁寧に描かれています。これらの巻を通じて、心の問題に対する理解が深まります。
個人的には第1巻から順を追って読むことをおすすめしますが、特定のテーマに興味がある場合は、その巻から読むことも可能です。例えば、精神障害者雇用に関心がある場合は第8巻から、パニック障害に興味がある場合は1巻から読むと良いでしょう。ただし、シリーズ全体を通して読むことで、登場人物の成長や物語の深みをより一層感じることができます。
『Shrink~精神科医ヨワイ~』は、心の問題に対する理解を深め、精神障害を抱える人々への共感と支援の重要性を再認識させてくれる作品です。ぜひ手に取って、その魅力を感じてみてください。