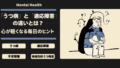中国で生まれ、IT業界を中心に広まった「996勤務制」──週6日・9時から21時まで働かされる過酷な労働スタイルは、単なる現地の話ではなく、グローバルな潮流のひとつとなりつつあります。実際、米国の一部テック企業でもこの考え方が浸透し始めているとの報道もあります。
社畜時代へ逆戻り、「996勤務」過酷な長時間労働が米国で広がる テック業界で顕著
この“長時間・成果至上”型の文化が日本にも波及すれば、障害者雇用や福祉的就労の現場にも大きな影響を受ける可能性があります。なぜなら、支援や配慮を前提とする就労環境では、「時間で計る成果」が蔓延する風潮と相容れないからです。法制度、社会意識、支援者・利用者双方のバランスが崩れるなかで、日本の「働きやすさ」は揺らぎかねません。
本記事では、「996勤務制」の概念とその国際的展開を紐解きながら、それが日本の障害者雇用・福祉就労に及ぼす潜在リスクと、そこから守るための方策を探ります。
「996勤務制」とは?
「996勤務制」とは、「996工作制」とも呼ばれ、朝9時から夜9時まで、週6日間働くことを強いる過酷な労働形態です。名前の由来はそのまま「9時から21時まで、6日間」の意味で、中国のIT・テック業界で広がりました。残業代未払いが常態化し、労働者の健康と権利を著しく損なうブラック労働の象徴です。
2019年には、この過酷な労働環境に抗議する「996.ICU(集中治療室)」運動が世界的に話題となり、「996=過労死直行=集中治療室入り」という悲痛な実態を暴露しました。
中国ではさらに過酷な「807勤務」(午前8時から午後7時まで、週7日)や「716勤務」(午前7時から午後4時まで、週6日)なども報告されており、労働者を“人間として扱わない”労働環境が深刻な社会問題となっています。
なぜ今、「996勤務制」が再び注目されているのか?
AIやスタートアップ(ここでは、技術・IT分野を中心に動く新興企業の意)は、急成長を追い求める性質があるため、効率、スピード、成長率を最優先する文化が強まりやすい傾向にあります。こうした価値観のもとでは、「成果を出すには長時間働くのは当然だ」という逆戻り的な発想が、徐々に浸透してくる可能性を大いに含んでいます。
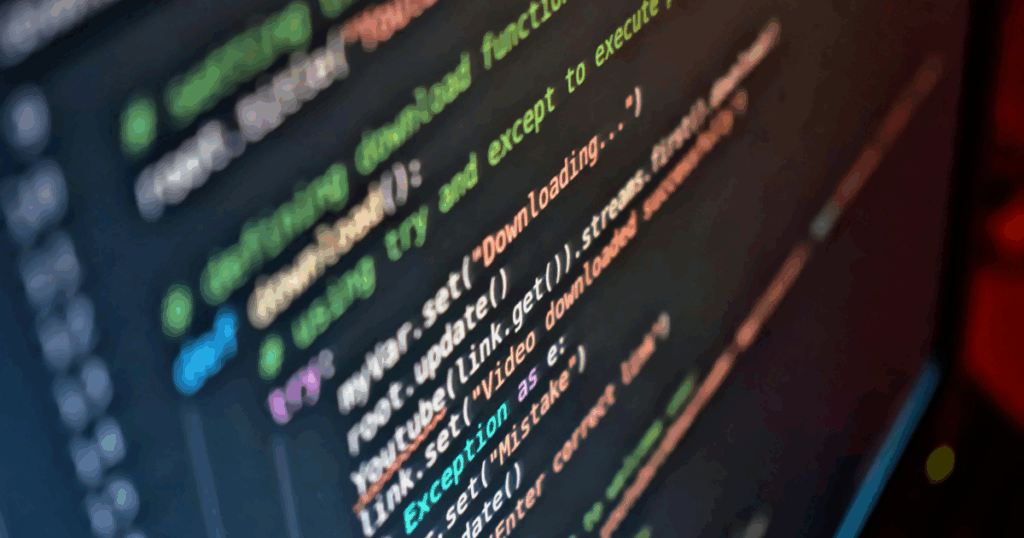
(写真 Canva)
日本ではまだ「9時~21時・週6日」のような本格的な“996勤務制”は広く根付いているわけではありません。ただし、IT・ベンチャー業界などを中心に、プロジェクトの緊急性や競争プレッシャーによって長時間稼働が「例外から一時期的に常態化」する傾向は見られます。スタートアップでは立ち上げ期や資金調達期等のタイミングで、構成メンバーに強いコミットメントが求められることが多く、そこに“実質的な長時間労働”の芽が潜んでいるのです。
このような過剰成長主義的な風潮は、労働者全体に圧力をかけるだけでなく、障害者雇用・福祉就労の現場にも波及する可能性があります。支援や配慮が前提とされる環境下で、「長時間=価値」の思考が浸透すれば、無意識のうちに働きづらさが増すリスクが高まるからです。
ただし留意すべき重要ポイント
法的枠組みと福祉的就労の現状
障害者雇用や就労支援の分野では、労働時間や配慮義務が法的に明確に規定されています。したがって、「996勤務制」のような過酷な働き方を障害者に直接強制することは違法です。
さらに、精神・発達障害のある人を中心に「働きやすさ」や「安心感」を最重要視する職場づくりが進められており、福祉・支援業界ではむしろ「996的働き方」とは真逆の価値観が主流となっています。

(写真 Canva)
「996勤務制」が日本の障害者雇用や福祉的就労にもたらす“脅威”
無意識の「健常者基準」強化
社会全体で長時間労働や高い生産性が美徳とされる風潮が強まると、障害者にも「もっと働け」「配慮は甘え」といった無言の圧力が及びやすくなります。
- 「週5日6時間は働けなければ就職は難しい」
- 「配慮を求めるのはやる気の問題だ」
- 「A型事業所にいるのに生産性が低い」
こうした意識は、障害者が自分の特性や体調に合わせて無理なく働くことを困難にし、就労の門戸を狭めてしまう恐れがあります。
就労継続支援事業所の“居場所”が揺らぐ
就労継続支援A型・B型事業所は、障害者が「働きながら社会とつながる」大切な場ですが、996的な労働観が浸透すると、
- 「もっと売上をあげろ」「もっと工賃を上げろ」といった過剰な成果主義の圧力が強まる
- 事業所の助成金見直しや報酬単価の引き下げなどで運営が厳しくなる
- 利用者に過度な作業負担を強いるリスクが高まる
これにより、本来の目的であるリハビリや自信回復の場としての意義が薄れ、障害者自身の精神的・身体的負担が増す可能性があります。
支援者のバーンアウト(燃え尽き)リスク
支援者もまた、長時間労働や成果主義の圧力で疲弊しています。
- 多様な障害特性に対応する難しさ
- 報酬単価の厳格化に伴う効率重視のプレッシャー
- 相談支援や精神ケアの負担増
こうした負担の積み重ねにより、支援者が燃え尽きるケースが増加し、人材不足がさらに深刻化する悪循環が懸念されます。
対策:「人間らしい働き方」を守るために
多様な働き方を尊重する社会づくり
「8時間×5日勤務」が唯一の正解ではありません。障害の有無や体調、生活事情に応じた柔軟な働き方こそが、成熟した社会の証です。
就労継続支援は単なる「働く場」ではなく、リハビリや自己肯定感の回復の場でもあります。成果主義に偏らず、多様性と人間性を尊重する意識を社会全体で共有しましょう。
法制度と報酬体系の見直し・維持
- A型・B型事業所の報酬単価を適正に設定し、質の高い支援を継続できるようにする
- 成果だけでなく、過程や個人の尊厳を評価する柔軟な制度設計
- 設備投資やICT化、人材育成への継続的な支援で働きやすい環境を整備
これらが、障害者の安心した就労を支えます。
AI・テクノロジーとの共生
また、AIの導入は単純労働の自動化を促進しますが、それは障害者の仕事を奪うのではなく、支援者の負担を軽減し個別支援を高度化するチャンスです。
- スケジュール管理や作業支援にAIを活用し、支援者の負荷軽減を図る
- EC運営やデザインなど創造的な作業へのシフトを支援し、新しい働き方をつくる
テクノロジーを「代替」ではなく「補完」として活用することが重要です。
おわりに:「996勤務制」は未来の働き方ではない
中国で拡大した「996勤務制」は、過労死や精神疾患を引き起こし、多くの労働者の健康を脅かす深刻な問題です。日本でも同様に、長時間労働や成果主義の圧力が再び強まりつつあり、障害者雇用や支援現場に間接的な影響が及ぶ可能性があります。

(写真 Canva)
障害者の就労は、単なる労働時間や効率だけでなく、「働きやすさ」や「安心感」を重視した支援が不可欠です。無理なく続けられる多様な働き方を認めることが、本人の自立や社会参加を支える鍵となります。また、支援者自身も健康を保ちながら質の高いサポートができる環境が求められています。
これからは「長く働くこと」よりも「幸せに働くこと」を大切にし、多様性を尊重する社会を目指すべきです。「996勤務制」は決して理想の働き方ではなく、誰もが自分らしく働ける環境づくりを進めていくことが重要です。
関連記事
【2025年10月より開始】「就労選択支援」って何?やる意味はあるのか?
2025年10月から新たにスタートする「就労選択支援」制度について詳しく解説。そもそもどんな制度なのか、導入の背景や目的、企業や利用者にとってのメリット・デメリットまでわかりやすくまとめています。制度の全体像を押さえたい方は必見です。
【2026年度より実施】「地域移行等の意向確認」が障害者支援施設の利用者にどう影響するのか?
2026年度から本格的に始まる「地域移行等の意向確認」。障害者支援施設の利用者に対してどのような変化や影響があるのか、制度の背景や国の狙い、現場の課題とともに丁寧に解説します。今後の対応を考えるうえで知っておきたいポイントをまとめました。
就労継続支援A型でアニメ・漫画の仕事はできる?その現実と可能性を解説!
就労継続支援「B型」では、実際にアニメ業界への実践的な就労が行われています。では、労働契約のある就労継続支援「A型」でアニメ制作やイラスト、漫画といったクリエイティブ業界に関われるのか?憧れの職種と福祉制度のリアルな関係を、実例や支援の仕組みとともに解説。就労支援と創作分野の接点を探る方におすすめの内容です。