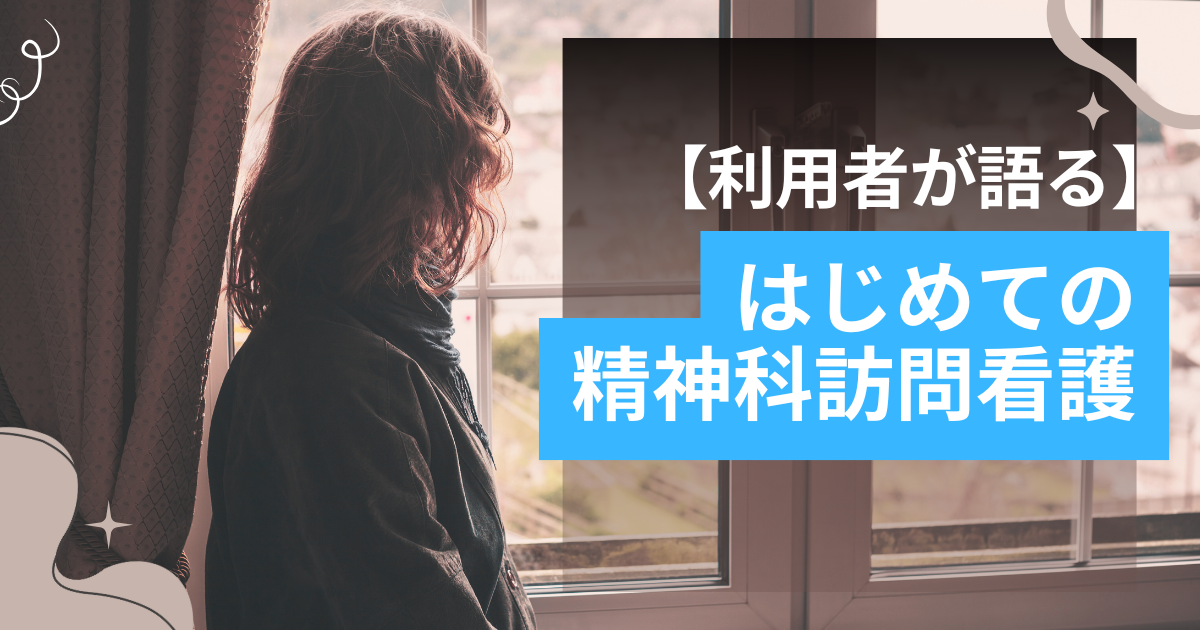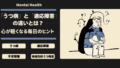こんにちは、Kです。
今日は、私の暮らしに大きな安心をくれた支援のひとつ、「精神科訪問看護」について少しお話したいと思います。
この記事を読んでくださっているあなたは、もしかしたら「精神科訪問看護って、なに?」と感じているかもしれませんし、「ちょっと気になってるけど、誰かの体験を聞いてからにしたい」と思っているかもしれません。
この記事では、私自身が初めて精神科訪問看護を利用したときの不安や戸惑い、そして実際に支援を受けてみて感じた安心感や変化について、率直にお伝えします。
精神的な不調と向き合いながら、ひとりで抱え込まずに暮らしを続けていくために。
精神科訪問看護は、そんな日々を支える心強い手段のひとつです。
「ちょっと気になる」「使ってみようかな」と思っている方にとって、少しでも参考になるような情報をお届けできれば幸いです。
精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護とは、看護師さんや精神保健福祉士、作業療法士などの専門職が、自宅まで来てくれて、心や体の状態を見守りながらサポートしてくれる医療サービスです。
病院やクリニックに通うのがしんどいときでも、自宅にいながら必要な支援を受けられるのが大きな特徴です。
たとえば、こんなことをしてくれます
- バイタルチェック(血圧・脈拍・体温など)
毎回、心と体の状態を一緒に確認してくれます。無理なく「今の自分」を知ることができます。 - 服薬の確認・アドバイス(服薬指導)
飲み忘れがちな薬の管理や、薬の副作用についての相談もできます。薬に対する不安も受け止めてもらえます。 - 傾聴とメンタルケア
ただ話を聞いてもらうだけで、心がふっと軽くなる。そういう時間をつくってくれます。 - 一緒にお散歩に行くことも
調子が良ければ、一緒に外に出て軽く散歩をすることも。季節の風を感じるだけでも、リフレッシュになります。 - 病院や主治医との連携
症状の変化を共有し、必要があれば診察や治療につなげてくれます。
私が訪問看護を始めるまで
精神科訪問看護を利用することになった経緯は、当時はまったく予想していなかったものの、振り返ると自分にとって必要なタイミングだったのだと感じています。
私は精神科に定期的に通院しながら、就労継続支援A型事業所で働いていました。
しかし、ある時期から精神的に不安定な状態が続き、出勤することが非常に難しくなってしまいました。感情が抑えられず涙が止まらなくなったり、仕事を続けること自体が負担に感じる日々が増えていきました。
そんな状況に気づいた事業所の生活支援員さんは、私の担当の相談支援専門員さんに状況を相談してくださいました。その結果、精神科訪問看護を利用してみることを提案していただきました。
初めて聞くサービスであったため、正直なところ戸惑いや不安もありました。自宅に知らない人が来ることに対して抵抗感や緊張感を感じてしまい、果たして自分に合うのだろうかと考え込んでしまったのです。
しかし、相談支援専門員の方や主治医と話を進める中で、訪問看護は私の状態に合わせて無理のない形で支援が受けられるものであると知りました。主治医からも「訪問看護はあなたに合っている」と言われたことで、安心して利用する決心ができました。
こうして私は少しずつ精神科訪問看護を生活に取り入れていくことになったのです。
24時間対応体制の契約に
契約にあたって、担当の訪問看護ステーションの代表の方が24時間対応体制を組んでくださいました。
とてもありがたいことですし、恐縮してしまうほどでした。
もちろん、「24時間いつでも連絡できる」ことが目的ではなく、それがあることで「いざという時にも見捨てられない安心感」が得られる。そんな、“お守り”のような存在だと私は感じています。
実際には、まだ夜間や休日に連絡をしたことはありません。
それでも、「いざというとき、誰かに助けを求められる」体制があるだけで、日々の暮らしの中で深く息ができるようになりました。
看護師さんとの“関係性”に救われた日々
今、週に1回、看護師さんが私の家に来てくれています。
毎回だいたい30〜40分ほど、体調のこと、睡眠や食事の様子、心の動きについて話したり、必要があれば軽く散歩をしたりします。
初回の訪問では、丁寧にバイタルを測りながら「今日はよく眠れましたか?」「食事はとれていますか?」と、やさしく声をかけてくれました。
普段ならうまく言葉にできない不調も、こうしたやりとりの中で、自然と出てくるんです。
そして何より、私が一番助けられたのは「傾聴してくれる時間」でした。
うまく言えなくても、
涙が出てしまっても、
無言になってしまっても、
看護師さんは待ってくれました。
散歩に出た日、空の色が変わって見えた
ある日、私は「ずっと部屋にいると息が詰まってしまう」と話したことがありました。
その日、看護師さんが「今日は少し外を歩いてみませんか?」と誘ってくれたんです。
最初は少し戸惑いましたが、近くの公園までゆっくり歩いてみることにしました。

(写真 K)
ほんの15分ほどでしたが、久しぶりに「生きている感覚」を思い出させてくれました。
看護師さんと並んで歩く時間は、「支援」というより「同行」でした。
そんな存在が、どれほど大きな力になるか、実感しました。
利用するにはどうすればいい?
もし「私も使ってみたいかも」と思った方のために、簡単に流れをご紹介します。
利用までの流れ
- 主治医に相談する
訪問看護には「訪問看護指示書」が必要です。診察のときに「訪問看護について相談したい」と伝えてみてください。 - 相談支援専門員や支援者に話してみる
支援計画を一緒に立ててくれる人がいれば、訪問看護の調整や事業所探しをしてくれます。主治医より先にこちらから相談しても大丈夫です。そのあとで主治医から訪問看護利用の同意を得られれば利用することができます(私がそうでした)。 - 訪問看護ステーションと面談し、契約
不安なことはこのときに聞いてOK。私はこのとき、24時間対応の体制も一緒に契約させていただきました。 - 定期的な訪問がスタート
看護師さんと一緒に、自分のペースで関係を築いていきます。
※費用については、医療保険や自立支援医療制度、障害福祉サービスが利用できる場合があります。サービスの利用や費用などにつきましては、各自治体の相談支援事業所にお問い合わせ下さい。
まとめ:精神科訪問看護は、「安心の灯り」
私は定期的な訪問看護を受けながら無理のない生活と仕事のバランスを探し続けています。
症状がゼロになるわけではないけれど、「誰かが見守ってくれている」という感覚が、何よりも大きな支えになっています。
支援って「がんばるため」じゃなくて、「がんばりすぎないため」にあるんだな、と今では思います。
もしこの記事を読んで「少し気になる」と思ってくれた方がいたら、それだけで十分です。
そして、もし「今はまだ無理」と思っても、それも大丈夫。
あなたのペースで、必要なときに、必要な支援とつながれますように。

(写真 K)
あなたはひとりじゃありません。
精神科訪問看護は、そっとそばで灯りをともしてくれる支援です。
無理なく、少しずつ、自分に合った形で受け取ってみてくださいね。
最後に:読んでみて欲しい関連記事
支援のしくみについてもっと知ってみたくなったら、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
あなたにとって“話しやすい支援者”を見つけるヒントが、きっとどこかにあります。
支援職や制度の仕組みを知ることで、安心感や選択肢が広がります。
▶ 精神障がいを持つ方を支える職種まとめ〜自分に合う支援者を見つけるために〜
支援職にはどんな人がいて、それぞれどんな役割を担っているのか?全体像を知りたい方におすすめのまとめ記事です。
▶ 相談支援事業所とは?
福祉サービスを利用する際の“最初の窓口”になるのが相談支援事業所。具体的な役割や、どんなふうに関われるのかをわかりやすく解説しています。
▶ 障がいのある人の安心な暮らしをサポート!「相談支援事業所」のしくみと利用方法
実際の利用の流れや申請手順、相談支援専門員さんとの関わり方など、実用的な情報をまとめています。
▶ 当事者同士だからできる「ピアカウンセリング」とは?
同じ経験を持つ“ピア(仲間)”だからこそできる支援のかたち。温かく寄り添うピアカウンセリングの魅力に迫ります。
▶ ピアカウンセラーになるためには?
ピアとして支える側になりたいと思った方へ。必要な準備や資格、実際のステップについて紹介しています。
▶ピアカウンセラーに資格は必要?自分に合った学び方と活動のはじめ方
上記のピアカウンセラーの記事から、さらに一歩進めてピアカウンセラーの民間資格の種類や選び方について詳しく紹介しています。
そのほか、訪問看護に関するまとめ
精神科訪問看護とは?算定要件や訪問看護でできること、病院との違いも解説
自律神経失調症とうつの違いを症状・原因・診断治療で徹底解説
気になるテーマから、ぜひ気軽に読んでみてくださいね。
支援について知ることは、「自分のことをより深く知る」ことにもつながります。
焦らず、少しずつで大丈夫。一歩ずつ、自分に合った支援の輪が広がっていきますように。