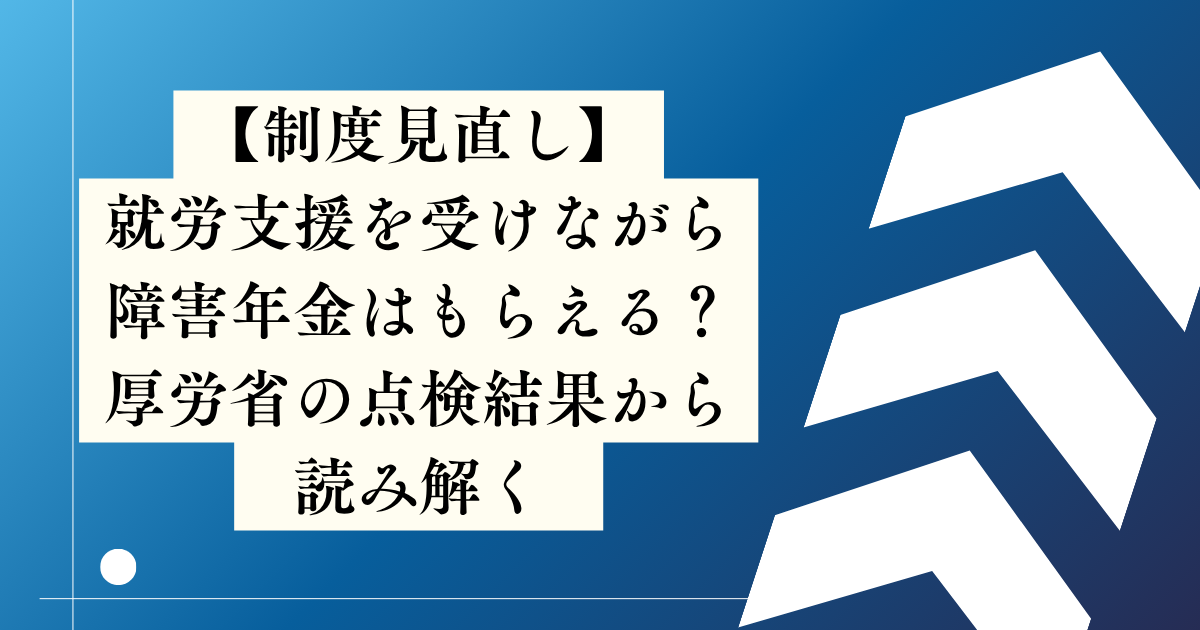「働いているから障害年金はもらえないのでは?」
「就労継続支援A型でも申請できるの?」
こうした質問や疑問は、就労支援の現場で多く寄せられます。障害年金は障害の程度に応じて支給される制度ですが、実際には就労の有無だけで受給が左右されるわけではありません。
近年、障害年金の審査基準や運用に変化が生まれていることをご存じでしょうか?
2025年9月に厚生労働省が公表した調査結果では、これまで不支給となっていた精神障害の申請について、再点検を行った結果、124件が支給に変更されるという注目すべき動きがありました。
124件が支給に変更 障害年金判定を点検〈厚労省〉
本記事では、この厚労省の点検結果を丁寧に解説し、就労支援を受けながらでも障害年金がもらえる可能性について、最新の制度動向を踏まえてご説明します。
厚労省による障害年金の再点検調査とは?
調査の概要
厚生労働省は2024年度に、精神障害に関する障害年金の申請のうち、不支給判定となった2,895件を無作為に抽出し、内容を精査しました。
調査結果
その結果、約4.3%にあたる124件の不支給判定が取り消され、支給に変更されました。これは「不支給と判断されていた中にも、本来は障害年金を受け取るべきケースがあった」ことを示しています。
調査実施の背景
この点検調査は、「精神障害の障害年金申請で不支給判定が増えているのではないか?」という指摘や社会的な懸念を受けて行われました。2024年度の不支給率は約13%と、前年よりも4.6ポイント増加しており、特に精神障害に関しては支給判断の見直しが求められていたのです。
なぜ「働いている=障害が軽い」と誤解されがちなのか?
精神障害や発達障害の場合、外からは「働けている=問題がない」と見えやすいことが、誤解の大きな原因です。しかし実際には、多くの方が以下のような形で支援を受けながら、辛うじて働き続けています。
- 毎日の服薬や体調管理に家族や支援者のサポートが欠かせない
- 通勤に送迎や付き添いが必要である
- 週に数回の短時間勤務や、体調不良による欠勤が多い
- 職場でも常にスタッフが支援や配慮をしている
こうした状況は、「障害が軽い」とは言えず、むしろ日常生活や社会参加に多大な困難があることを示しています。障害年金は、そのような支援の必要性を評価する制度であり、「働いている」という事実だけで支給が否定されるものではありません。
厚労省点検で変わった「障害年金審査」の評価軸
これまで障害年金の審査では、主に「発現状況」が重視されていました。発現状況とは、障害の症状や障害が日常生活・就労にどの程度影響しているかを指します。
しかし、今回の厚労省の再点検では、これに加えて以下の多角的な視点から審査が行われました。
| 新たに評価された視点 | 具体的内容 |
| 症状の経過や予後 | 長期的な症状の持続や悪化の可能性 |
| 治療歴 | 入退院歴、服薬の継続状況、通院状況 |
| 日常生活の支援状況 | 家族や支援者による援助の必要度 |
| 就労の形態と支援内容 | 就労頻度、仕事内容、支援付き就労の有無 |
このように、「今現在働いているか」だけで判断するのではなく、「どのような支援や配慮を受けて働いているのか」が審査の重要なポイントになりました。
就労継続支援(A型・B型)と障害年金の関係
福祉サービスとしての就労継続支援は、一般的な就労が難しい方に対して、支援付きの働く場を提供しています。
就労継続支援B型(非雇用型)
- 雇用契約なし、工賃制
- 比較的軽い作業で、精神的・身体的負担が少ない内容が中心
- 支援が厚く、障害の程度が比較的重い方が多い
- 障害年金の等級目安:基礎年金2級に該当する可能性が高い
就労継続支援A型(雇用型)
- 雇用契約があり、最低賃金以上の給与が支払われる
- 出勤日数や作業量は調整されていることが多い
- 労働者としての立場を持つが、就労に対する支援は続く
- 障害年金の等級目安:厚生年金3級が中心だが、条件により基礎年金2級に該当する場合もある
注意点
これらはあくまで目安であり、障害年金の等級判定は、医師の診断書、本人の生活状況、支援内容の具体性などを踏まえて個別に判断されます。
障害年金申請における制度上の重要要件
障害年金を申請し支給されるためには、障害の程度だけでなく、次の制度上の要件も満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
| 初診日要件 | 障害の原因となった病気やけがの初めての診察日を証明できること |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日時点で、一定期間にわたり年金保険料を納付していること(免除期間も含む) |
これらの要件を満たしていなければ、たとえ障害の程度が重くても支給対象外となるため注意が必要です。
障害年金申請を前向きに考えるべき人のチェックポイント
以下のような状況に心当たりがある方は、障害年金の申請を積極的に検討する価値があります。
- 職場で支援や配慮がないと仕事が続けられない
- 週数回しか出勤できず、体調不良による欠勤が頻繁にある
- 金銭管理や服薬管理を一人で行うことが困難である
- 通勤や日常生活で家族や支援者の援助が欠かせない
- 医療機関や行政手続きの際に支援者の付き添いが必要である
まとめ:就労支援を受けながらでも障害年金はもらえるのか?
タイトルにある「就労支援を受けながら障害年金はもらえる?」という問いについてですが、
はい、就労支援を受けながらでも障害年金をもらうことは可能です。
これまで「働いているから障害年金は受け取れない」と考えられてきましたが、障害年金の審査基準が見直され、実際には「支援なしには働けない」「日常生活に支援が欠かせない」といった状況が重要な判断基準になっています。特に就労継続支援A型やB型を利用している場合、その支援内容が障害年金申請において重要な要素となります。
したがって、「働いている」という事実だけではなく、「どのような支援を受けて働いているのか」「どの程度の支援が必要か」といった点が障害年金を受け取れるかどうかに影響を与えます。支援を受けながら働いている方は、適切に申請を行うことで障害年金を受け取る可能性が高まりますので、あきらめずに制度を活用することをおすすめします。
今後も障害年金の審査基準は、働く人々の実態に寄り添った柔軟な見直しが期待されます。支援を受けながらの就労を続けている方は、最新の制度情報を確認しつつ、専門窓口などに相談しながら申請を検討してみてはいかがでしょうか。
また、以下の記事では、精神障がいを抱えながらA型事業所で働く利用者が障害年金制度の課題と矛盾に切り込んだ内容をお届けしています。
見落とされがちな制度のギャップに関心のある方は、ぜひこちらもご覧ください。