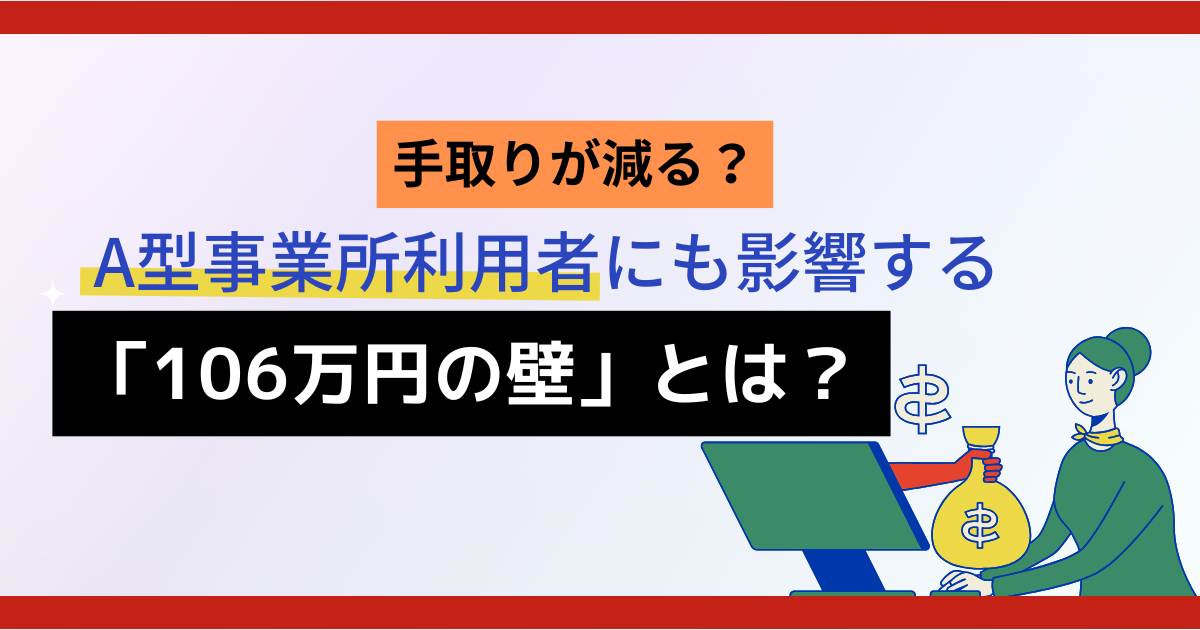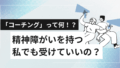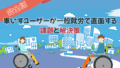こんにちは。精神障がいを抱えながら、現在はA型事業所で在宅勤務をしているKです。
今回は、ニュースなどで見かける「106万円の壁」や「社会保険の適用拡大」についてお話ししようと思います。
制度の仕組みは難しく感じるかもしれません。でもこれは、ただの法律の話ではなく、「どう生きていくか」「どんな働き方ができるか」に関わってくる、すごく大事な話です。
「106万円の壁」ってなに?
これまで多くの障害者就労支援A型事業所では、利用者の労働条件が社会保険(健康保険・厚生年金)の適用要件を満たさないケースが多く、実質的に加入の義務がないことが一般的でした。
一方、民間企業などでは、以下の条件に該当する人が社会保険に加入する必要があります:
- 従業員51人以上の企業に勤めている
- 週20時間以上働いている
- 月収8.8万円以上(年収で約106万円以上)
- 勤続見込みが2か月を超える
これらの条件がそろうと、社会保険の「加入が義務」となり、いわゆる「106万円の壁」が意識されるようになります。多くの人が「106万円を超えると手取りが減る」として働く時間を調整する、いわゆる「働き控え」につながっていました。
※106万の壁のほかにも、「103万の壁」「130万の壁」「150万の壁」「201万の壁」などの「年収の壁」があります。どれも似ていますが、内容は異なりますので注意が必要です。
参考:厚生労働省 『年収の壁について知ろう』(PDF)
制度がどう変わるの?
政府は、2026年10月からこの適用基準を見直し、年収約106万円の賃金条件の撤廃や小規模な事業所(従業員51人未満)にも社会保険加入義務を段階的に広げる予定です。
これにより、これまで対象外だったA型事業所の利用者も、一定の条件を満たせば社会保険の加入対象になる見込みです。
朝日新聞 年収「106万円の壁」「130万円の壁」、年金法案でどう変わる
🟡 注意:この制度改正は現在「予定」であり、正式に施行されるまでに詳細や時期が変更される可能性もあります。最新の公式情報を確認するようにしましょう。
なぜ制度が変わるの?
この見直しの目的は、「働くことを制限せず、自由に収入を得られるようにすること」です。年収を調整して社会保険加入を避けるような働き方をなくし、将来の安心につながる制度を広げることが狙いです。
どんな影響があるの?
◉良くなること
- 年収を気にせず働けるようになる:これまで年収制限を気にして働き方を調整していた人も、自分の体調を優先しながら、無理のないペースで収入を得られるようになります。
- 社会保険に加入することで、将来の年金や医療の保障が手厚くなる:老後や病気のときの備えが増え、安心して働き続けられます。
- 病気やケガによる休業時の保障(傷病手当金など)も受けられるように:体調を崩しても収入が途絶える不安が軽減されます。
◉気をつけたいこと
- 手取りが減る可能性がある:社会保険料は会社と本人が折半するため、給料から一定額が差し引かれます。
- 事業所の運営への影響:会社側の負担も増えるため、経営が厳しくなる事業所が出てくる可能性があります。つまり、今後「制度変更後の負担に耐えられない」として事業継続を断念(廃止またはA型からB型といった、別の就労支援等へ移行)する事業所が出始めるかもしれません。
まとめ
- 社会保険の適用が広がり、障害のある労働者にも加入義務が及ぶ可能性が高まっています
- 手取りは減るかもしれませんが、保険による保障は充実します
- 事業所運営に与える影響は大きく、制度変更を受けて廃止される事業所もあるかもしれません
- どんな働き方を選ぶかは一人ひとり異なります。将来を見据えて、早めに情報を集め、備えていきましょう
おわりに:私たちにできること
この変化は「損か得か」だけでなく、「自立して働き、生きていく」という将来の選択にも関わってきます。
もし今のA型事業所がなくなるとしても、他のA型・B型事業所や、一般就労への移行支援、福祉的なサポートも用意されています。不安がある場合は、支援者や関係機関と相談しながら、自分に合った働き方を一緒に考えていくことが大切です。
……私はこれまで、退職や職場不適応でたくさんつまずいてきました。それでも今、「働ける場所」に出会えて生活を少しずつ立て直しています。
社会保険の拡大は時に厳しい現実を突きつけてきます。でも、それを「終わり」ではなく、「次のステップ」だと思えるように周りと話し合いながら前を向いていけたらと思います。
あなたもどうか一人で抱え込まず、信頼できる支援者や家族と一緒に、この変化を乗り越えていけますように。。
📌 制度の詳細や最新の情報については、厚生労働省の公式サイトもあわせてご確認ください