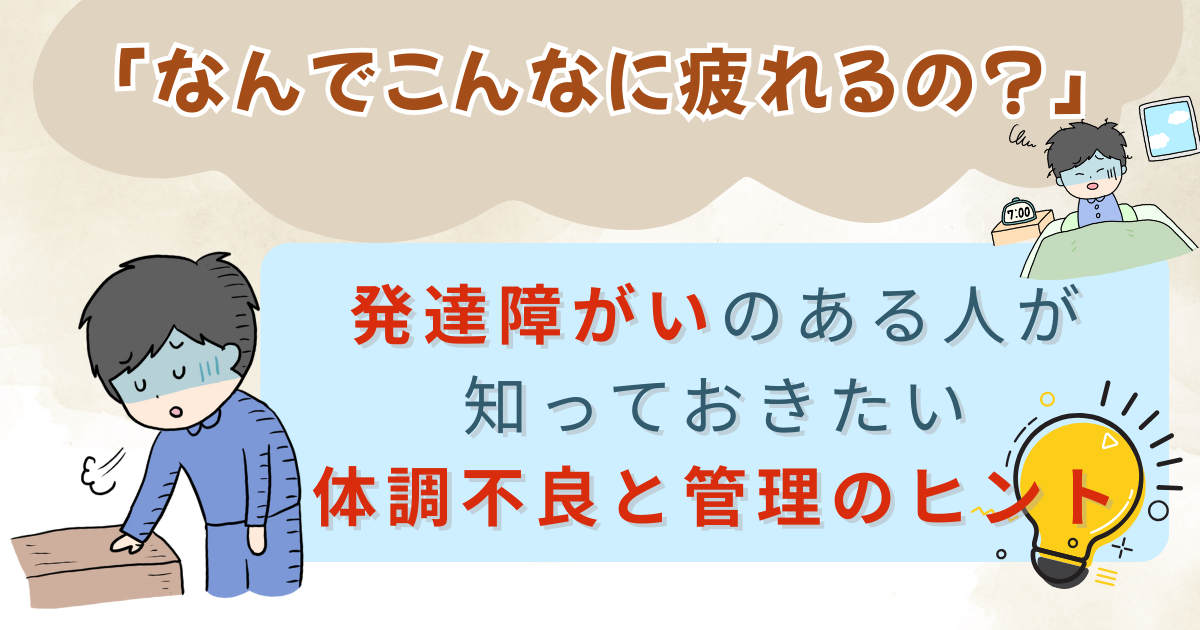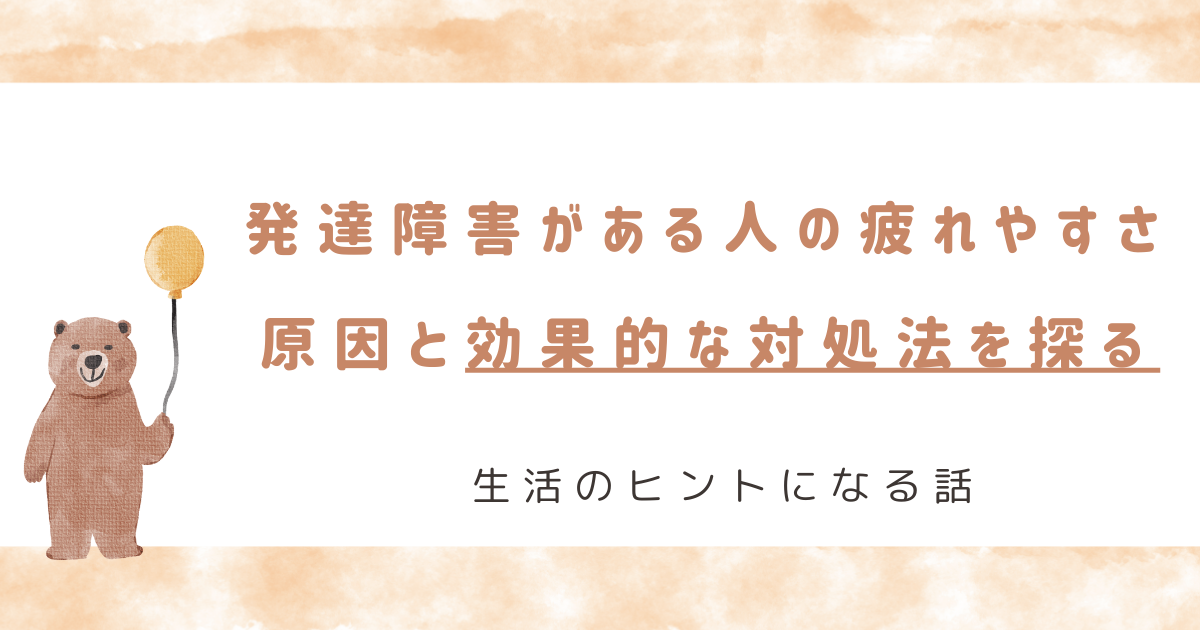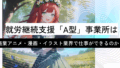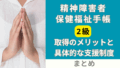はじめに:こんなお悩みありませんか?
発達障がいの方で以下のチェックリストに、思い当たることはありますか?
➡ 2つ以上当てはまった方は、「体調管理に困りやすい傾向」があるかもしれません。

発達障がいのある人の体調に関わる特性と困りごと
発達障がいのある人は、体の調子をうまく管理するのがむずかしいことがあります。これは、いくつかの特性が関係していて、日常生活や仕事に影響することもあります。
ここでは、体調に関係する主な特性と、よくある困りごとをご紹介します。
❶ 感覚にとても敏感、または鈍いことがある
以前こちらの記事でもご紹介していますが、発達障がいのある人の中には、暑さや寒さ、疲れなどに気づきにくい人がいます。そのため、体調が悪くなっても気づかず、がまんしすぎてしまうことがあります。
- 例:暑さを感じにくくて、熱中症になるまでがまんしてしまう
- 例:寒さに気づかず、寒いのに上着を着ない
また、音や光、においが気になりすぎてつらくなる人もいます。そうした環境がストレスになって、体調が悪くなったり、集中できなくなったりすることもあります。
❷ ストレスが体に出やすい
発達障がいのある人は、環境の変化や人とのやりとりにストレスを感じやすいことがあります。そして、そのストレスが体に出やすいのも特徴です。
- 胃が痛くなる
- 頭が痛くなる
- お腹の調子が悪くなる(下痢や便秘など)
このような体の不調がくり返し起こると、学校や仕事を休まなければならないこともあります。
❸ 生活のリズムがくずれやすい
発達障がいのある人は、毎日の生活リズムをととのえるのが苦手なことがあります。
- 夜なかなか寝つけない、夜中に目がさめる、昼夜が逆になる
- 食事の時間がバラバラ、好きなものばかり食べる
こうしたリズムのくずれは、日中の元気さや集中力にも影響します。できるだけ決まった生活ができるよう、まわりのサポートが大切です。
❹ がんばりすぎて、体調をくずすことがある
自分の苦手なことをかくして、まわりに合わせようとがんばりすぎてしまう人もいます。その結果、気づかないうちに疲れがたまって、急に体調をくずすことがあります。
- 例:がまんして仕事を続けた結果、ある日いきなり動けなくなってしまう
こうしたことを防ぐには、「ちょっと疲れてきたかも」と早めに気づける工夫やサポートが大切です。
発達障がいのある人が体調をくずさないようにするには、本人が気づきやすくなる工夫と、まわりの理解・支えがとても大切です。
よくある困りごとと背景
| 困りごと | 背景や特性 |
| 毎朝体調が悪くて出勤がつらい | 睡眠の質が悪い・環境変化に弱い |
| 週末は寝込んでしまう | 感覚疲労やストレスの蓄積・休息不足 |
| 季節の変わり目に体調を崩しやすい | 自律神経の調整が苦手 |
| 自分の体調変化に気づけない | 鈍感さ・自己認識の難しさ |

発達障がいの方の体調管理の工夫と支援
毎日元気に過ごすためには、ちょっとした工夫や周りの助けが大切です。
発達障がいのある方が無理なくできる体調管理のポイントをまとめてみました。
❶ 生活のリズムをつくろう
毎日、起きる時間・ごはんを食べる時間・寝る時間をなるべく同じにすると、体も心も安定しやすくなります。予定はスマホのアプリやホワイトボードに書いて見えるようにすると、忘れにくく安心です。
❷ 感覚に合った工夫をしてみよう
暑さや音、光の感じ方は人それぞれです。
- 暑さを感じにくい人は、冷たいタオルや冷感グッズを使ったり、温度を知らせてくれるアラートを使うと安心です。
- 音や光が苦手な人は、ノイズキャンセリングイヤホンやサングラス、遮光カーテンなどを取り入れて、心地よく過ごせる工夫をしましょう。
❸ ストレスはためこまないように
何か気になることがあったら、信頼できる人に話してみましょう。カウンセリングや認知行動療法、必要に応じてお薬を使うことも考えられますよ。
❹ 体調の変化を見えるようにしよう
毎日の睡眠やごはん、気持ちの変化を日記やアプリで記録すると、体調が崩れやすい時期やサインがわかるようになります。早めに対処できて安心です。
❺ 支援やサービスも使ってみよう
仕事や生活のこと、ひとりでがんばりすぎずに、サポートを使ってみるのも大切です。
- 就労支援:仕事に向けた準備や練習ができる場所です。面接の練習や、仕事を始めたあともサポートしてくれることがあります。
- 障害者手帳:自分に合った支援や配慮を受けやすくなる大切な証明書です。通院・交通費の割引や、職場での配慮をお願いしやすくなります。

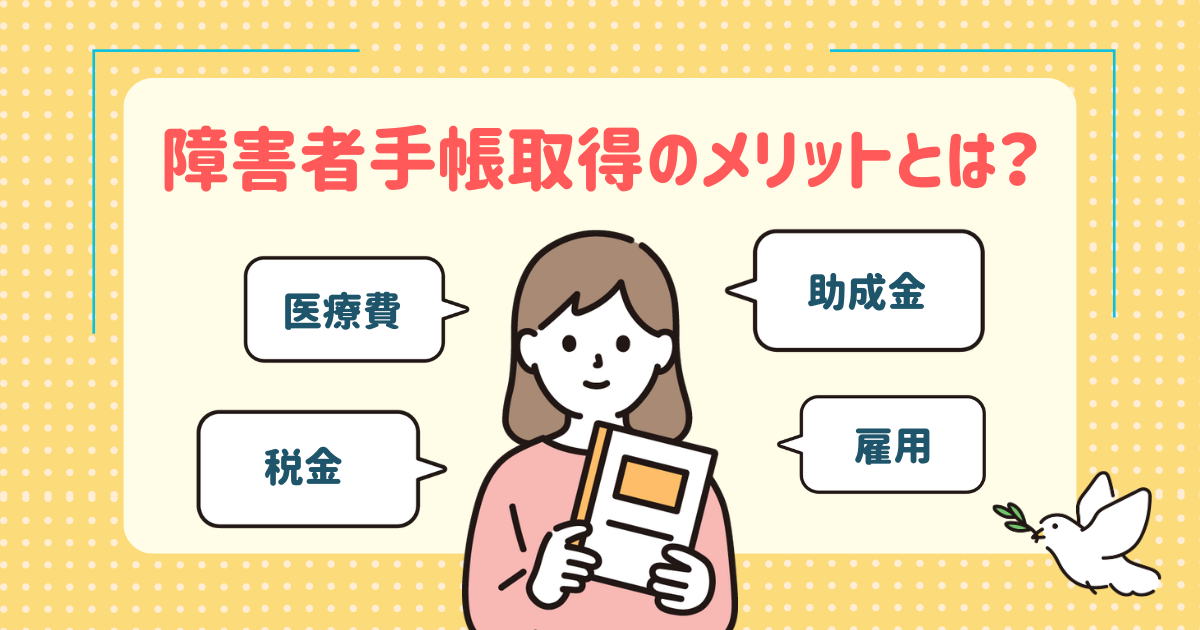
困ったときは、地域の相談支援センターや医療機関に相談してみましょう。あなたに合った支援がきっと見つかりますよ。
(浜松にお住まいの方は浜松市内の相談支援センターにご相談ください。それ以外の方は、市区町村の役所にご相談ください。)
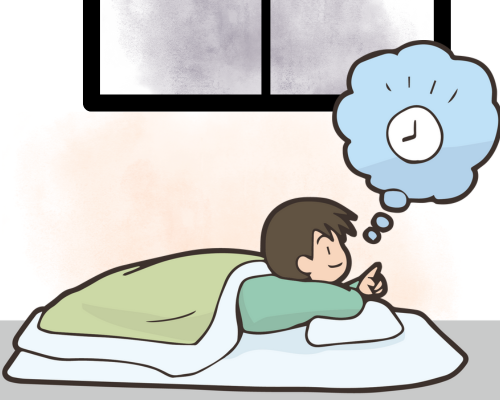
▼こちらの記事でも発達障がいの方の体調管理についてご紹介しています。ぜひあわせてお読み下さい。
職場で、困っていることやお願いを伝えるときのポイント
発達障がいのある方にとって、「体調の変化」や「疲れやすさ」「感覚過敏」などは、見た目には分かりづらいことが多く、周囲にうまく伝えられないことで無理をしてしまうケースもありますよね。そんな時、職場で自分のことを伝えるのに、ちょっとした工夫で伝わりやすくなるコツをご紹介します。
❶ 「困っていること」は、できるだけくわしく伝える
「しんどい」だけでは、まわりの人には伝わりにくいことがあります。
どんなときに、どんなふうに困っているのかを、できるだけくわしく伝えると、わかってもらいやすくなります。
たとえば…
- 「長い会議が続くと、感覚が疲れて頭がぼーっとしてきます。少し休憩が入ると、すごく助かります」
- 「光や音が気になりやすくて、集中しにくくなることがあります。まわりが見えにくくなるように、机に仕切りを置かせてもらえると安心です」
❷ 「こうしてもらえるとうれしいです」と、やさしくお願いする
お願いごとがはっきりしていないと、職場の人もどうしていいか分からなくなることがあります。
「こうしてもらえるとありがたいです」と伝えることが大切です。
たとえば…
- 「お昼休みの時間をちょっと長めにしてもらえると、午後も体調をととのえやすくなります」
- 「体調がよくない日は、在宅勤務に切りかえられると、安心して仕事を続けられます」
❸ 「自分でも工夫しています」と伝える
お願いをするときに、「自分でもできることをがんばっています」と伝えると、相手も気持ちよく受け入れやすくなります。
たとえば…
- 「よく眠れるように、生活リズムをととのえるようにしています。でも、それでも調子が悪くなる日もあります」
- 「毎日、気分の記録をつけて、自分の体調のようすを見ています」
❹ 一人でむずかしいときは、支援の人に手伝ってもらう
職場に自分のことを話すのがむずかしいときは、就労支援のスタッフさんや、相談支援専門員さんに一緒に来てもらうこともできます。
第三者がいてくれると、お話しがスムーズに進むことも多いです。
配慮をお願いすることは、「わがまま」ではありません。
自分らしく、気持ちよくお仕事を続けていくために、とても大切なことです。
できるところから、少しずつ伝えていけたらいいですね。
配慮の例とその効果
| 配慮の内容 | 目的・効果 |
| 定時退社・時短勤務 | 疲労をためずに働ける |
| 静かな席への移動 | 感覚刺激を減らし、体調不良を予防 |
| 報告の頻度を調整(週1回まとめて報告) | 頻繁な対応によるストレス軽減 |
| 作業の見える化(ToDoリスト・マニュアル) | 忘れや混乱を防ぎ、安心して業務に取り組める |

👪支援者・家族の方へ
おわりに
発達障がいのある方にとって、体調管理は「努力だけでは解決しにくい」課題のひとつです。
でも、特性に合った工夫と配慮、そしてまわりの理解があれば、体調の波を軽減し、より自分らしく働き、暮らすことができます。