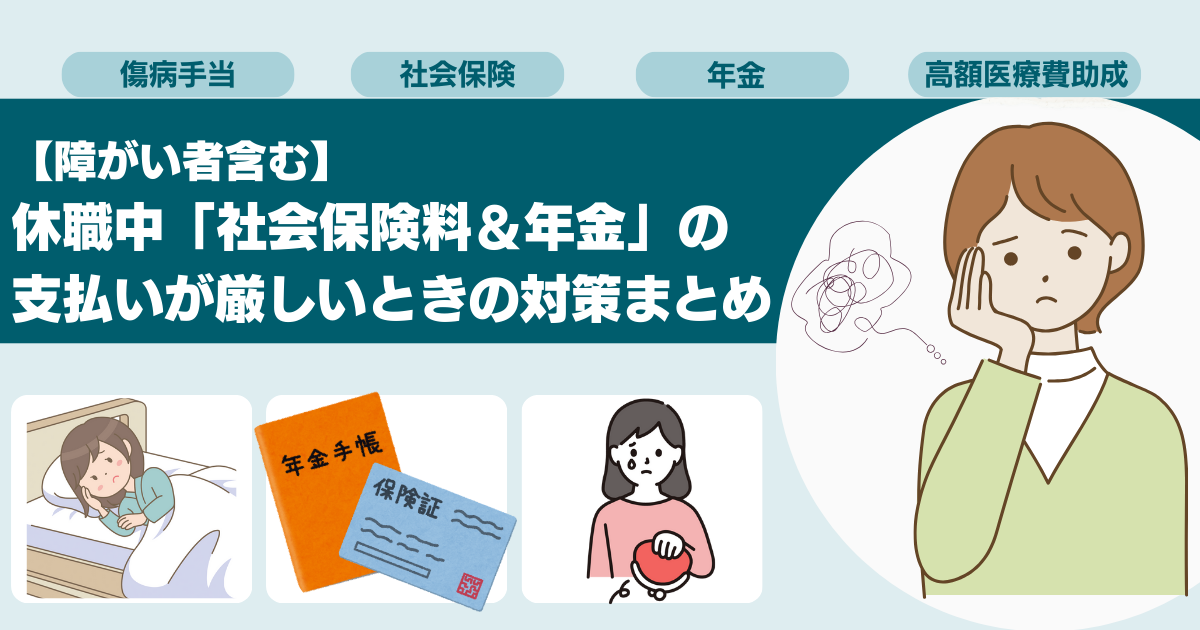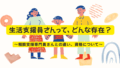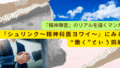「入院で仕事を休まなきゃいけないけど、収入もなくなって医療費もかさむとか。。」「休んでいる間の保険料や年金はどうしよう?」と悩んでいませんか?
この記事では、休職するときに知っておきたい、お金の不安や手続きについてやさしくまとめました。
傷病手当金、社会保険料・年金の支払い、障がい者の助成など、各種制度の減免や申請方法についてご紹介します。参考にしてみてください。
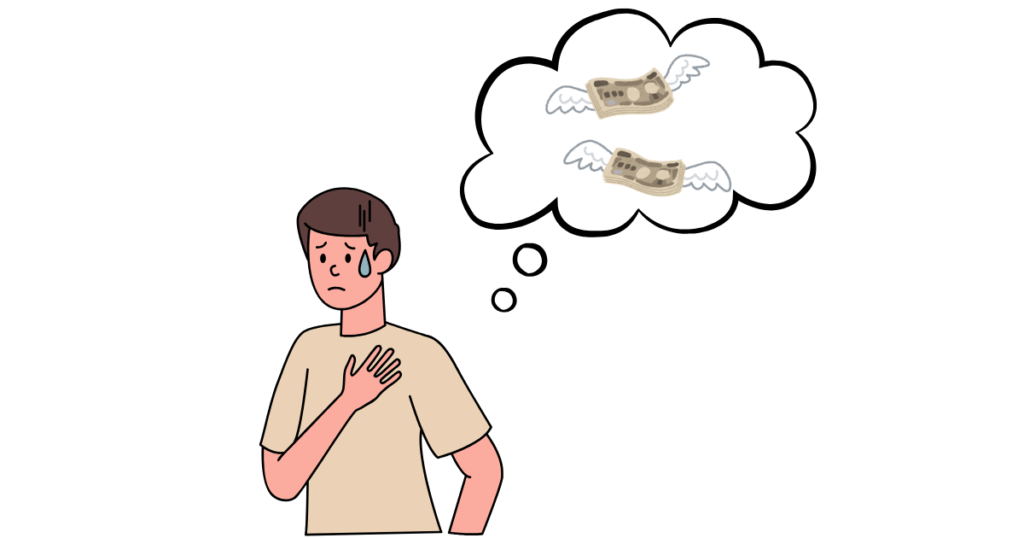
🛌仕事を長期間休む時は「傷病手当金」を申請しよう!
病気やけがで仕事を休むときのサポート「傷病手当金」って?🩼
病気やけがで働けなくなったとき、「傷病手当金」という制度を利用できる場合があります。原則、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険に入っていれば対象になります。
この手当があれば、社会保険料や年金の支払いにあてることもでき、経済的な不安を少し軽くすることができます。条件にあてはまる場合は、忘れずに申請しましょう。
※国民健康保険の方は原則対象外ですが、一部の自治体では独自の支援があることも。詳しくはお住まいの市区町村に確認してみてください。
支給される条件
- 会社員や公務員、パート/アルバイトなどで、勤務先の健康保険組合や協会けんぽに加入している人。
- 連続する3日間を含め、4日以上休んでいる(待機期間あり)
支給内容
- 給料の約3分の2
- 最長1年6ヶ月
パート・アルバイトの場合の主な支給条件🕒
- 週20時間以上働いている
- 月収約88,000円以上(地域差あり)
- 2ヶ月以上の雇用予定がある
- 自分で健康保険に加入している(扶養は対象外)
注意点⚠️
- 健康保険加入前の病気・ケガは対象外となることもあります
- 短期間の雇用だと受け取れない場合もあります
☝️困ったときに助かる制度なので、自身の勤務先での健康保険の加入状況を確認しておきましょう。
詳しくはこちら 🔗全国保険健康協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
「傷病手当金」の申請方法🗒️
傷病手当金の支給を受けるには、次の順番で申請を進めましょう。
カンタン5ステップ!これで申請は完璧!
- 会社に相談
休む前に上司や人事、総務に休む申告と「傷病手当金を申請したい」旨を伝えます。 - 医師の意見書をもらう(もらえるまでに時間がかかることがあるので、早めにお願いしておく。)
通院しているお医者さんに「傷病手当金の申請のために意見書が欲しい」と伝えて書いてもらいます。 - 傷病手当金の申請書を入手
会社から申請書をもらいましょう。協会けんぽの公式サイトからダウンロードもできます。 - 会社に記入してもらう
自分で協会けんぽや健保組合に送付する場合は、事業主の記入欄を会社にお願いしましょう。 - 提出する
書類を会社の総務に提出、もしくは、協会けんぽや健保組合に申請書と意見書を郵送します。
詳細&申請書ダウンロードはこちら🔗 全国保険健康協会
わからないことがある時は、勤務先の総務課などに相談しながら、焦らず手続きを進めましょう。

💰休職中の社会保険料・年金が払えないときの対策
保険料の支払いが難しいときは、免除や猶予の制度も検討しよう☝️
休職中でも、健康保険料は前年の収入をもとに決定され、収入が減ってもその年の保険料の金額は変わらないため、病気だけでなく、お金の面でも不安を感じる人は少なくありません。
もし支払いが難しいと感じたら、無理をせず「免除」や「猶予」といった制度を利用することも考えてみましょう。状況によって使える制度や条件は異なりますが、まずは相談してみることが大切です。
社会保険の免除や猶予は、どこに相談すればいい?
勤務先の健康保険や厚生年金に加入している場合は、まず勤務先の担当部署や健康保険組合に相談しましょう。
厚生年金について詳しく知りたい場合は、日本年金機構でも案内してもらえます。
厚生年金保険料等の猶予制度 🔗厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」
また、長期の休職後に退職し、国民健康保険や国民年金に切り替えた場合は、お住まいの市区町村の役所が相談窓口になります。(この点については、次の項目を参照してください。)
退職する場合は「☝️【厚生年金】休職ではなく退職する場合の大きなポイント!」の項目も併せてご参照ください。
国民健康保険と年金の免除・猶予は、どこに相談すればいい?
国民健康保険と国民年金の免除や猶予を申請したい場合は、それぞれ相談先が異なります。
- 国民年金の相談先:お近くの「年金事務所(日本年金機構)」
- 国民健康保険の相談先:お住まいの「市区町村の役所(市役所・区役所など)」
※健康保険は年金事務所では扱っていないため、必ず市区町村の窓口に相談しましょう。
国民年金保険料等の免除・猶予制度🔗 国民年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
注意!支払いが難しいときは、放置せずに必ず手続きを!⚠️
支払いが厳しいとき、支払わずにそのままにするとリスクが大きくなります。
- 将来の年金が減ってしまう
- 障害年金や遺族年金が受け取れなくなる
- 国民健康保険が使えなくなる可能性も
だからこそ、「払えない」ときはそのままにせず、免除や支払いの猶予など、きちんと手続きすることが大切です。

☝️休職ではなく【退職する場合】の大きなポイント!
退職後すぐに就活せずに休む時は、失業保険の延長申請を忘れずに!
勤務先で雇用保険に加入していた期間が一定期間ある場合、退職後に安心して就職活動ができるようにお金がもらえる制度が失業保険です。ただし、受け取るには実際に就職活動をしていることが必要です。
病気などですぐに就職活動ができない場合は、「延長申請」をしましょう。申請すれば、元気になって就職活動を始めた時、失業保険の支給が受けられます。申請を忘れると、受給できなくなることもあります。
病気や妊娠・出産など正当な理由があれば申請できます。期限があるので、退職時は早めにお住まいの管轄のハローワークで確認してください。しっかり手続きをして、安心して体を休めましょう。
直接ハローワークへ行く方法と、郵送での受付も可能な場合があります。直接ハローワークに行けない場合は、管轄のハローワークへ電話で相談しましょう。
🔗 厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」
退職した月の年金の【二重請求】にご注意を(厚生年金加入者の場合)
厚生年金加入者(勤務先の社会保険加入者)が、月の途中で退職すると、まれに、その月の「厚生年金」と「国民年金」の両方が請求されることがあります。
万が一、二重請求となってしまった場合は、退職した勤務先にその旨を相談しましょう。厚生年金が還付となる場合は、対応してもらえるので安心です。
もし、国民年金が還付となる場合は、退職日がわかる書類(離職票や退職証明書など)を役所に提出すれば、きちんと対応してもらえます。
なお、この二重請求を防ぐためには、退職日を月の途中ではなく、その【月の最後の日とする】と、防ぐことができます。
また、退職後は自分で国民年金への切り替え手続きが必要です。手続きが遅れた場合も、誤って請求が来ることもあるので、早めにお住まいの市区町村で手続きを済ませましょう。
👩💻そのほか休職前に準備できること
医療費が高くなりそうなときは「高額療養費制度」を活用しよう
入院や手術、通院などで医療費が高くなりそうなときは、「高額療養費制度」を利用すると、負担を抑えることができます。
この制度では、1ヶ月(1日~月末)に支払った医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その超えた分があとから払い戻されます。
また、あらかじめ医療費が高くなるとわかっている場合は、「限度額適用認定証」を事前に用意しておくと安心です。入院時に保険証と一緒に提示するか、マイナ保険証を使えば、初めから高額療養費制度の自己負担上限までしか請求されません。これにより、一時的な大きな支払いを避けられます。
※入院時の食事代(病院食)や個室料金などは対象外です。
※入院や手術がなくても、月内の医療費が高額になれば制度の対象になることがあります。
高額療養費制度について🔗 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
「限度額適用認定証」の申請窓口って?
社会保険もしくは、国民健康保険のどちらに加入されているかで申請が異なります。申請から発行までに1週間程度を要する場合もあるので、入院など日付が決まっている場合は、余裕を持って申請しておくのが安心です。(間に合わない場合でも、後から払い戻しを受けることができます。)
・社会保険の場合(会社員や公務員の方)
→ 勤務先の健康保険組合、または協会けんぽ(※詳細は会社の総務・人事部などに確認するとスムーズです)
・国民健康保険の場合(自営業・無職・扶養の方)
→ お住まいの市区町村の役所(国民健康保険の窓口)
限度額適用認定申請書ダウンロードページ🔗 全国健康保険協会「健康保険限度額適用認定申請書」
⚠️被保険者の被保険者の市区町村民税が非課税などによる低所得者の方は、限度額適用認定申請書ではなく、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出する必要があるので注意しましょう。
🔗 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書ダウンロードページ:全国健康保険協会「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
そのほか相談できる支援制度のまとめ💡
病気や収入の減少などで生活が厳しいときは、以下のような支援制度を利用できることがあります。
- 勤務先で有給休暇の残り日数を確認して、収入確保に役立てる。
- 精神疾患や慢性疾患がある場合は、障害者手帳や自立支援医療制度が使えることも。
- 住民税の減免や納付の猶予は、市区町村の税務課へ相談してみましょう。
- 電気・ガス・水道などの支払い猶予も、事情を伝えることで対応してもらえる場合があります。
困ったときは一人で抱え込まず、早めに相談してみよう。

🧑🦽障がい者手帳を持っている人の健康保険と年金
障がい者手帳には、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があり、取得するとさまざまな支援が受けられます。
申請を考えている方は、主治医に相談して、申請できるかどうかや等級の見込みについてアドバイスをもらうと安心です。
なお、手帳を持つことで、医療保年や生命保険への加入が難しくなったり、就職活動に影響することもあります。メリットとデメリットをしっかり確認し、自分にとって必要だと感じた場合に申請するのがおすすめです。
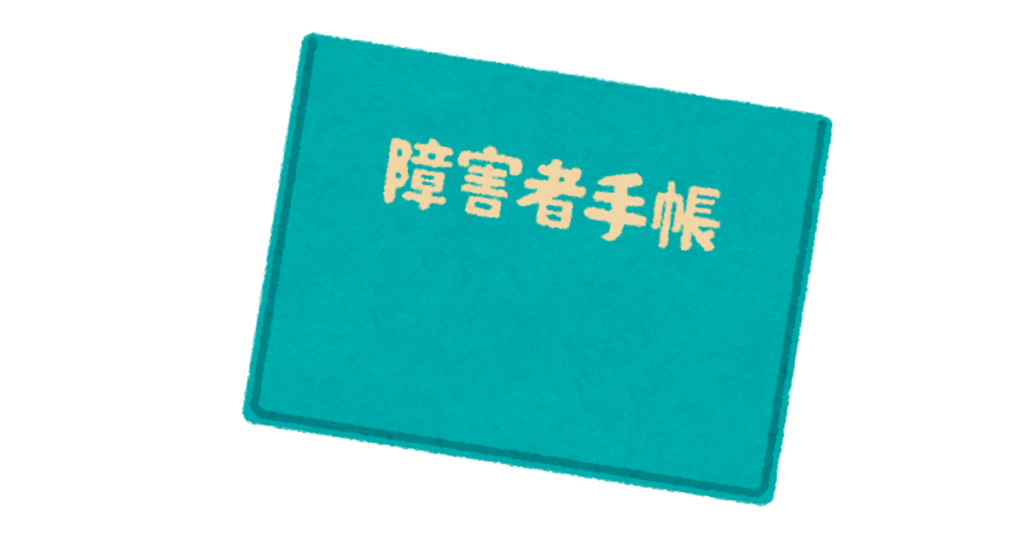
障がい者手帳で年金保険料が免除・減免される制度は基本的に「なし」
障がい者手帳を持っていても、それだけで年金の保険料が免除・減額される制度はありません。
ただし、先述のとおり、収入の減少など、一定の条件に当てはまる場合は、年金の免除や猶予が受けられる可能性があるため、免除や猶予を受ける場合は、お住まいの市区町村の役所の年金課や、厚生年金の場合は勤務先に相談しましょう。
また、障害の状態によって障害年金の1級または2級に認定された場合、申請により国民年金保険料が「法定免除」となる可能性があります(厚生年金は対象外)。
障害年金の対象になるかどうか、免除の申請方法などについては、お近くの年金事務所や市区町村窓口にご相談ください。
障がい者手帳の等級と、障害年金の等級(1級・2級)は、よく似た名前ですがまったく別のものです。つい混同してしまいがちなので、手続きをする際などにはご注意ください。
障害年金を申請する場合、これまでの詳細な治療歴や医師の意見などが必要で、手続きが複雑です。体調がつらい中で一人で進めるのは大変なこともあるので、有識者に手伝ってもらったり、社労士に相談するのがおすすめです。
障害年金についてはこちら🔗 日本年金機構「障害年金」
「法定免除」について
・国民年金の場合
障害年金の1級または2級に認定されると、条件を満たせば国民年金の保険料の支払いが全額免除になる「法定免除制度」が利用できます。生活保護を受けている場合も対象となることがあります。
免除期間中も保険料を「納めたもの」として扱われるため、将来の年金受給資格にはカウントされます。ただし、金額の面では一部しか納めていない扱いになるため、老後にもらえる年金額は減ってしまいます。
満額に近づけたい場合は、追納(あとで支払う)も可能です。
制度の詳細や手続きについては、お近くの年金事務所や市区町村の年金窓口でご相談ください。
・厚生年金の場合
一定期間、厚生年金に加入していた方が、障害年金の1級または2級と認定された場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます(※支給額は加入期間や報酬額により異なります)。
ただし、就労を続けて勤務先の社会保険に加入したままの場合は、厚生年金の支払い義務は継続され、支払免除にはなりません。
また、病気によって障害年金の1級または2級と認定され、一定期間、厚生年金に加入していた期間があったとしても、その病気が20歳以前発症のものである場合、障害基礎年金のみに該当し、障害厚生年金が受け取れないこともあります。
詳細については、お近くの年金事務所や市区町村の年金窓口でご確認ください。
障がい者手帳で国民健康保険料が免除・減免される制度は全国的には「なし」
障がい者手帳があっても、国民健康保険料の免除や減免制度は、全国的にはありません(先述の、通常の減免や猶予のみ)。
しかし、国民健康保険は市区町村ごとに運営されているため、自治体によって対応が異なります。一部の自治体では、たとえば次のような場合に減免されることがあります。
- 障がい者手帳の1級・2級に該当する人の保険料を減額
- 所得が少ない障がい者の保険料を減免
- 生活保護世帯の保険料を全額免除
ただし、こうした減免は自動で適用されることは少ないので、気になる場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険課や福祉課にご相談ください(勤務先の社会保険に入っている場合は、勤務先の総務などへご相談ください)。
障がい者手帳で受けられる主な助成・減免制度
- 自立支援医療(精神通院)制度:医療費の自己負担が1割に
- 重度心身障害者医療費助成制度:一定の等級の障がい者に医療費助成(自治体により異なる)
- NHK受信料免除:免除の種類や条件は、障がいの内容や世帯の構成によって異なります。詳しくは、NHKまたはお住まいの自治体の窓口にご確認ください。
- 自動車税減免:詳細な条件はお住まいの自治体によって異なるので、詳しくは自治体の窓口へ
※基本的に、「自立支援医療」と「重度心身障害者医療費助成制度」は併用できません。詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。
医療関連リンク
- 🔗 厚生労働省|自立支援医療(精神通院医療)の概要
- 🔗 浜松市の場合|重度心身障害者医療費助成制度について
自動車税の減免関連リンク(軽自動車税はお住まいの自治体、自動車税は都道府県へ)
- 🔗 浜松市の場合|軽自動車税(種別割)の減免申請について
- 🔗 静岡県の場合|自動車税種別割の減免について
NHK料金免除関係リンク
- 🔗 NHK|受信料免除の対象となる方について
😌【まとめ】休職中のお金の不安を減らすために、今できること
休職中は、収入が減ることへの不安が大きいもの。でも、制度を知って早めに準備すれば、その不安はぐっと軽くなります。
知っておきたいポイントは以下の通りです
- 傷病手当金は、休職中の生活を支える大切な制度。スムーズに受け取るために、事前に準備しておきましょう。
- 社会保険料や年金の支払いが難しいときは、免除や猶予の制度が使えることもあります。
- 退職を考えている場合は、退職日とその後の手続き(失業保険の延長申請など)にも注意が必要です。
- 障がい者手帳を持っている方は、使える支援が複数あります。自分に合った制度を確認してみましょう。
不安な時こそ、情報を早めに集めて、できることから準備しておきましょう。