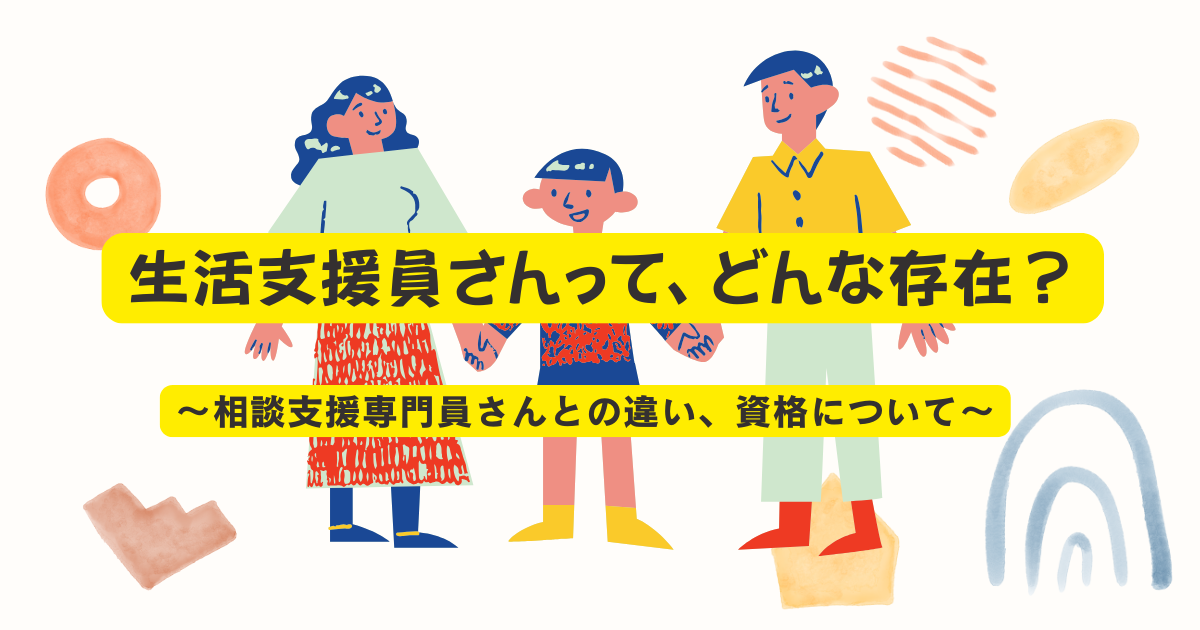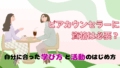こんにちは、Kです。
私は精神障がいを抱えながら、A型事業所で在宅勤務をしている当事者です。
今回は、私の生活に欠かせない存在となっている「生活支援員」さんについて、体験を交えながら書いてみようと思います。
支援の現場には、「就労支援員」「相談支援専門員」「訪問看護師」など、さまざまな職種の方が関わってくださっていますが、
私にとって一番身近で、日々の小さな変化に気づいてくれるのは、いつも生活支援員さんでした。
◆ 生活支援員さんってどんな人?
▶「暮らし」の中にいる支援者
生活支援員さんは、日常の“すぐそば”にいる支援者です。
彼らは、就労継続支援A型・B型、グループホーム、地域活動支援センターなど、障害福祉サービスの現場で働いています。
たとえば、以下のようなことを担ってくれます。
| 役割の例 | 内容 |
| 作業支援 | 作業中の見守り、声かけ、進捗確認など |
| 生活支援 | 着替えや食事のサポート、通院同行など(施設による) |
| 心身のサポート | 気分や体調の確認、必要に応じて他職種へ連携 |
| 相談対応 | 「ちょっと聞いてほしい」話を受け止めてくれる |
支援というと、医師やカウンセラーなどの“専門家”を想像する方も多いと思いますが、
生活支援員さんは、「専門的すぎない、でもちゃんと支えてくれる」存在です。

◆ 資格は必要?生活支援員さんって、どうやってなるの?
▶ 国家資格は“必須”ではない
生活支援員さんは、国家資格がなくても働ける支援職です。
ただし、福祉の現場なので、以下のような資格や経験があると優遇されることが多いです。
💡 よくある資格や経験
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士(PSW)
- 保育士、看護師、臨床心理士など
- 福祉系の短大・大学卒業者(養成校修了)
- 初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者
- 障害福祉サービスの実務経験(無資格可)
一方で、資格がなくても「人の話をよく聴ける人」や「人と関わることが好きな人」が支援員として働くケースもあります。
私は、支援に必要なのは“資格”じゃなく、“関係性を築く力”だと感じます。
◆ 相談支援専門員さんとの違いは?
支援者にはさまざまな職種がありますが、よく混同されやすいのが「相談支援専門員」さん(通称:相談員さん)です。
ざっくり比較表
| 項目 | 生活支援員 | 相談支援専門員 |
| 所属 | 事業所、施設など | 特定相談支援事業所など |
| 関わる頻度 | 毎日〜週3回程度 | 月1回程度(モニタリング) |
| 支援内容 | 見守り、声かけ、日常的な対応 | 支援計画作成、サービス調整 |
| 資格 | 不問(あれば尚可) | 原則、福祉系資格+実務経験 or 養成研修必須 |
| 距離感 | 近くて親しみやすい | 少し距離があり制度寄り |
つまり、生活支援員さんは「毎日の暮らしを支える伴走者」であり、
相談支援専門員さんは「制度的な支援を調整する司令塔」のような存在です。
◆ 経験談:支援がつながった日
私が「訪問看護」というサービスを使うようになったきっかけも、両者の連携によるものでした。
こんな流れでした(実例)
- 生活支援員さんが「最近元気がなさそう」と気づいてくれる
- その状態を相談支援専門員さんに共有
- 相談員さんから「訪問看護を検討しませんか?」という提案
- 主治医と連携し、訪問看護ステーションへつながる
- 現在:週1回、自宅で訪問看護師さんと面談しています
私ひとりでは、どこに相談すればいいのかも分からなかったと思います。
「気づく人(生活支援員)」と「つなぐ人(相談支援専門員)」の存在があってこそ、今の支援があります。
◆ 支援員さんとの関係をうまく築くには?
「小さなこと」ほど、共有してみる
最初は、「こんなこと話していいのかな…」と遠慮していた私。
でも、「昨日ちょっと眠れなくて」「今日ちょっと不安で」
そんなささいな一言でも、言ってみることで関係が深まりました。

◆ まとめ
生活支援員さんは、制度の中ではあまり目立たない職種かもしれません。
でも、私にとっては「いつも見守ってくれている」大切な支援者です。
・支援の最前線にいてくれる人
・ちょっとした変化に気づいてくれる人
・他の支援者につないでくれる人
そして、なにより、「ひとりじゃない」と思わせてくれる人でもあります。
支援者というと、「知識のある人」「資格のある人」を想像しがちですが、
私にとっては「気づいてくれる人」「話せる人」の方が、はるかに心強い存在でした。
今、支援を受けている方の中にも、「誰に相談していいか分からない」と思っている方がいるかもしれません。
そんなときは、まずは生活支援員さんに、小さなことから話してみてください。
きっと、あなたの「支援の扉」が少しずつ開いていくはずです。
◆ 次に読みたい関連記事
「生活支援員さんって、実はこんなに大切な存在だったんだ」と感じた方へ――
支援のしくみや、他にも関われる専門職について、もっと知ってみたくなったら、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
あなたにとって“話しやすい支援者”を見つけるヒントが、きっとどこかにあります。
支援職や制度の仕組みを知ることで、安心感や選択肢が広がります。
▶ 精神障がいを持つ方を支える職種まとめ〜自分に合う支援者を見つけるために〜
支援職にはどんな人がいて、それぞれどんな役割を担っているのか?全体像を知りたい方におすすめのまとめ記事です。
▶ 相談支援事業所とは?
福祉サービスを利用する際の“最初の窓口”になるのが相談支援事業所。具体的な役割や、どんなふうに関われるのかをわかりやすく解説しています。
▶ 障がいのある人の安心な暮らしをサポート!「相談支援事業所」のしくみと利用方法
実際の利用の流れや申請手順、相談支援専門員さんとの関わり方など、実用的な情報をまとめています。
▶ 当事者同士だからできる「ピアカウンセリング」とは?
同じ経験を持つ“ピア(仲間)”だからこそできる支援のかたち。温かく寄り添うピアカウンセリングの魅力に迫ります。
▶ ピアカウンセラーになるためには?
ピアとして支える側になりたいと思った方へ。必要な準備や資格、実際のステップについて紹介しています。
▶ピアカウンセラーに資格は必要?自分に合った学び方と活動のはじめ方
上記のピアカウンセラーの記事から、さらに一歩進めてピアカウンセラーの民間資格の種類や選び方について詳しく紹介しています。
★その他、行政的な手続きや頼れる情報に関してはこちらにまとめております。
気になるテーマから、ぜひ気軽に読んでみてくださいね。
支援について知ることは、「自分のことをより深く知る」ことにもつながります。
焦らず、少しずつで大丈夫。一歩ずつ、自分に合った支援の輪が広がっていきますように。